|
■避難誘導のポイント
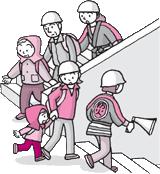
○事前に地域の避難施設・経路、危険箇所などを把握しておく。
○早めの避難を促す。
○1人で避難することが困難な人の避難の手助けの方法を習得しておく。(高齢者、傷病者、視覚障害者、子どもなどの災害時要援護者)
○避難の際にできれば、通電火災などの発生防止措置を行うよう、各世帯に呼びかける。(ブレーカーを落とす、ガスの元栓を閉める)
○エレベーターは使わないよう呼びかける。(エレベーターに乗っていた場合はすべての階のボタンを押して最寄りの階で降りて階段で逃げる)
○徒歩で避難を行うようにする。車は使用しない。
○避難場所・避難経路は複数用意しておき、状況によって最も安全な選択を行う。
○非常持出品は、多すぎると避難に支障をきたすことを住民に伝えて、最小限のものを持ってもらうようにする。(安全な服装と当座の生活必需品)
○一次避難場所では人員を迅速に確認。不明の場合は手分けをして確認する。
○子ども・障害者・高齢者など、災害時要援護者を中心にして避難者がはぐれないよう注意する。
○途中、可能であればラジオなどから災害情報などを入手する。
○避難所に到着したら、人員を確認する。
○夜間・停電による、真っ暗な状態なども想定して訓練を行ってみる。
|