|
1.訓練前に、避難誘導に必要な資機材(人員把握表、筆記具、旗、ロープ、メガホン、担架など)を準備する。
2.本部からの指示を受けて、メガホンなどにより避難指示と地区ごとの一次避難所を伝えて回る。この際、ブレーカーを落とす、ガスの元栓を閉める、という火災発生防止措置を行ってから避難することを必ず伝える。
3.一次避難場所では、人員の点呼、携行品や服装などの点検を行い、病人、負傷者、高齢者、子どもなどに分け、介護者を決めておく。
4.本部に連絡を入れて、避難場所の受け入れ準備完了の確認ができたら、消防団などの協力を得て、訓練参加者の前後に立ち、避難所まで誘導する。避難人員を把握し、要介護者の搬送も実際に行う。
5.避難途中では、事故防止に留意する。倒壊の危険のあるブロック壁などは避け、高齢者や子どもなどの災害時要援護者を列の中心にして、逃げ遅れる人が出ないように注意する。
6.避難場所に到着したら、点呼をとって全員の無事を確認し、本部に避難の完了を報告する。
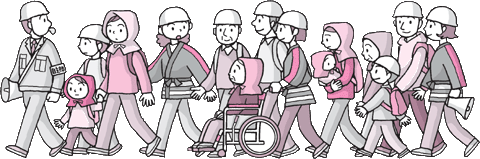
|