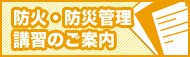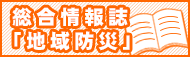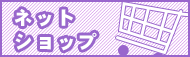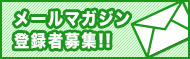「尼崎市婦人防火クラブ連絡協議会研修会」を実施
兵庫県 尼崎市消防局

【運営委員会】 実施風景
尼崎市内には32団体、1401名の婦人防火クラブ員が在籍しており、地域の消防訓練への参加をはじめ、防火・防災に関する研修会や、
住宅用火災警報器の設置・維持促進の広報といった地域活動に参加するなど「安全・安心のまちづくり」に積極的に取り組んでいます。
令和元年6月24日(月)尼崎市防災センター 多目的ホールにて開催した今回の研修会は、
講師として一般社団法人危機管理教育研究所 上席研究員 後藤武志様をお招きし、今後発生が危惧される大規模地震発生時に対する一般家庭での防災対策を学ぶことができました。
地震による直接的な被害から身を守る方法の他にも、被災直後の制限的な生活をしのぐために、
例えば、停電時の情報収集には車載のカーナビを使用する他、非常時の備蓄をスーツケースに備える方法等、普段家庭にあるものを有効利用する視点に、受講者は思わず膝を打ち、目から鱗が落ちた様子でした。
また、震災時は被災者に対する盗難や詐欺など犯罪が発生しやすく、治安が悪化する場合があるとの説明もあり、二次的な被害からも身を守る方法を学ぶことが出来ました。
身近なことから防災減災に取り組めることを学んだ受講者たちは「普段の生活の中で少し心掛けるだけで防災対策が出来ることがわかった」と自信を深めた様子でした。

【研修会】 後藤講師

【研修会】 実施風景 (シェイクアウト体験中)
「江西地区防災フェスティバル2019(防災講演会)」を開催
静岡県 浅間婦人防災クラブ
会長 鈴木 政子

浅間婦人防災クラブ会長による挨拶
令和元年6月30日(日)浜松市立浅間小学校体育館を会場にして、浅間婦人防災クラブ主催による「江西地区防災フェスティバル2019(防災講演会)」を開催いたしました。
江西地区では、平成7年に発生した阪神淡路大震災を期に地域住民を対象として、毎年防災フェスティバルを開催し、体験型イベントと防災講話を隔年ごとに行っています。
今回は、防災思想の高揚と地域の隣保協力体制、連帯意識の高揚を図ることを目的とした防災講話を開催いたしました。
今年度の防災講話は、第57次南極地域観測隊、渡貫淳子先生を講師としてお招きし「南極観測隊での任務経験について!」と題し講演会を実施いたしました。

講師 渡貫淳子先生

貴重な話に耳を傾けた講話風景

浅間婦人防災クラブで使用している
エプロンを渡貫先生へプレゼント
講演会では、地域住民や防災関係者約300人が聴講する中、「料理人としての食材の管理や工夫」「極地ならではの経験」「災害時に役立つもの」等について、約2時間に渡り説明をしていただきました。
特に食材の管理や工夫についての話では、1年に1回の買出しでどのように食材(1年4か月分の食材)を工面するか、
また南極の自然環境に影響を与えないために、如何に食事での排水をなくすか等、
食材不足や水不足が起こる災害時に通ずるものがあり、高い関心が寄せられました。現在、コンビニでも大人気商品となっている「悪魔のおにぎり」ですが、
そうした南極での日々の試行錯誤の中で考案されたそうです。今回の講演で、地域住民が非常食や生活必需品の備蓄の大切さを改めて感じる良い機会となりました。
さあっ「みんなで やらまいか!!」防災の街づくり
第37回気仙沼本吉地区婦人防火クラブ連合大会「防火のつどい」を開催
宮城県 気仙沼本吉地区婦人防火クラブ連合会
「防火のつどい」は、気仙沼市と南三陸町の婦人防火クラブ員が一堂に会し、防火・防災知識の習得と各クラブの交流を目的に令和元年7月7日(日)、
南三陸町総合体育館「ベイサイドアリーナ」にて開催し、今回で37回目を迎えました。

住警器・家庭防火コーナー

意見発表
開会前に東日本大震災で犠牲になられた方々に対し黙祷を捧げ、開会宣言の後、優良婦人防火クラブ表彰、婦人防火クラブ員による意見発表、防火宣言等が行われました。
講演では東北大学災害科学国際研究所の佐藤健教授を講師に迎え、「防災まちづくりを持続発展可能とするための人材育成」と題し、震災後の各小学校や中学校、
各自治会における防災に関する取組事例を紹介され、学校防災と地域防災の連携・融合の重要性について講話をいただき、
災害に強いまちづくりのためには防災活動とともに次世代に向けた人材育成が重要であることを再認識することができました。
また、会場の入口には住宅用火災警報器・家庭防火コーナーを設置し、各種防火パンフレットの配布を行うとともに住警器の設置・維持管理の啓蒙を図りました。

防火宣言

講演
「令和元年度西宮市家庭防火クラブ大会」を開催
兵庫県 西宮市消防局
令和元年7月10日(水)西宮市役所東館 8階大ホールにおいて、日本防火・防災協会との共催による「令和元年度 西宮市家庭防火クラブ大会」を開催しました。

会長あいさつ

市長祝辞
この大会は、西宮市内の家庭防火クラブ員が一同に会することで、クラブ員の団結を図るとともに、
記念講演を実施し、クラブ員の更なる防火防災意識の高揚を図ることを目的としており、今年度は、
甲南女子大学名誉教授日本災害食学会顧問の奥田和子様をお招きし、「災害時の食はどうあるべきか 危機管理は健康管理」というタイトルでご講演をいただきました。
災害時に平時と同じ健康状態を維持するため、栄養面、衛生面、災害弱者の観点から、災害食の自助・共助・公助の在り方について学びました。

消防局長挨拶

消防音楽隊演奏
「自助」では、健康を維持するための災害食を選ぶ上でのポイント、
「共助」では、講師自らのボランティアの炊き出し経験談を交えた、災害食を提供する側の準備や問題点、「公助」では、提供される災害食の内容や提供されるまでの時間等のお話がありました。
クラブ員からは「災害食への考え方が変わった。」「災害食を自ら準備することの重要性に気付いた。」などの声が寄せられ、大変有意義な大会となりました。