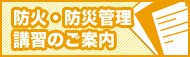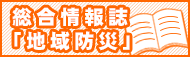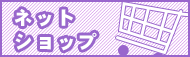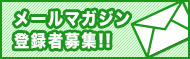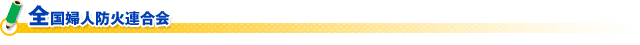
■平成16年度全国婦⼈防⽕連合会総会を開催
平成16年度全国婦⼈防⽕連合会総会が2⽉24⽇(⽊)午前9時30分より、⽇本消防会館5階⼤会議室において、開催されました。
全国婦⼈防⽕連合会は、全国の婦⼈防⽕クラブの組織の拡充・強化、同クラブ相互の連携・協調を強めること及び全国的な防⽕活動を展開することにより、より安全な地域社会の実現に資することを目的としています。
最初に、徳⽥正明⽇本防⽕協会会⻑が、「婦⼈(⼥性)防⽕クラブの持つ役割について、住⺠が幅広い期待を寄せるようになった昨今、新しい時代に合う組織づくりに努めていただきたい。」とあいさつ、続いて、(財)⽇本防⽕協会会⻑表彰が⾏われ、島根県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会会⻑ ⼭⼝洋枝⽒、岡⼭県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会会⻑ 吉岡伸⼦⽒、岐⾩県⼥性防⽕クラブ運営協議会会⻑ 丹⽻政⼦⽒、福井県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会会⻑ ⼩川英⼦⽒、栃⽊県婦⼈防⽕連合会 横 野登代⼦⽒、秋⽥県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会会⻑ 鎌⽥キネ⼦⽒の6名が受賞されました。
林省吾消防庁⻑官による来賓あいさつの後、下河内司総務省消防庁防災課⻑により「最近の消防情勢について」の講演が⾏われ、出席者の都道府県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会会⻑等50名は熱⼼に⽿をかたむけていました。会議では、平成16年度事業経過報告、平成17年度事業計画が⽰され、承認されました。
最後に、福井県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会 ⼩川英⼦会⻑による「福井県地域集中豪⾬災害と全国婦防連による現地⽀援等について」、新潟県⼩千⾕市婦⼈防⽕クラブ連絡協議会 佐藤笑⼦会⻑による「新潟県中越地震災害と全国婦防連による現地⽀援等について」の報告が⾏われました。
また、前⽇2⽉23⽇(⽔)13時30分には第5回応急⼿当普及啓発推進会議が⾏われました。
応急⼿当普及啓発推進会議は今年で5回目を数え、これまでに本年度の20地域を含め、全国90地域で講習会が⾏われ、約20,000⼈の講習修了者を排出しています。
秋本敏⽂⽇本防⽕協会理事⻑あいさつの後、救急振興財団⾚⽻信夫総務部⻑による来賓あいさつが⾏われ、平成16年度救急講習会報告や、救急の現状、AED(⾃動対外式除細動器)の役割について等のお話がありました。最後に、(財)東京救急協会指導課⻑ ⽵内栄⼀⽒により「⾃動対外式除細動器(AED)の活⽤について」、⽇本放送協会解説委員⼭﨑登⽒により「最近の災害取材の現場から」の講演(講演次第につきましては次号掲載予定)が⾏われ、閉会となりました。





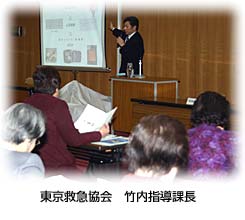
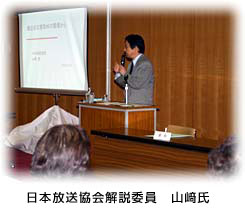
〜 平成16年度(財)⽇本防⽕協会会⻑表彰を受賞した⽅々(平成17年2⽉24⽇) 〜
 ・島根県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会
・島根県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会
会⻑ ⼭⼝ 洋枝⽒
・岡⼭県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会
会⻑ 吉岡 伸⼦⽒
・岐⾩県⼥性防⽕クラブ運営協議会
会⻑ 丹⽻ 政⼦⽒
・福井県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会
会⻑ ⼩川 英⼦⽒
・栃⽊県婦⼈防⽕連合会
会⻑ 横野 登代⼦⽒
・秋⽥県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会
会⻑ 鎌⽥ キネ⼦⽒
 ■林省吾消防庁⻑官(挨拶)
■林省吾消防庁⻑官(挨拶)おはようございます。消防庁⻑官の林でございます。改めまして今⽇お集まりの皆さま⽅には、⽇頃からそれぞれの地域で防⽕防災のために献⾝的なご活動をいただいておりますことに感謝を致しまして、この場をお借りして⼼から敬意とお礼を申し上げさせていただきたいと思います。
ご挨拶ということでお伺をいたしましたけれども、折角の機会でございますので、今消防庁⻑官として、私が考えていること、またやりたいと思っていることをお話をさせていただき、皆さま⽅のご理解とご協⼒をいただければと思いますので宜しくお願いいたします。
昨年は、本当に私共としては忘れられない年になってしまいました。
記録的な災害の年と⾔ってもいいと思いますが、ご承知のように7⽉の局地的な集中豪⾬、新潟、福井の⽅は⼤変でございました。
それから23号に⾄るまでの10個に上る台風の上陸、これも記録的な被害に遭遇いたしました。
更に10⽉23⽇には新潟県の中越地震で、⼤変⼤きな地震が発⽣するという経験を致しました。
その間振り返ってみますと消防関係者の⽅々には、最⼤限の活動をしてくださったものと感謝を致しているわけであります。
今⽇お集まりの婦⼈防⽕クラブの皆さん⽅のように、それぞれの⽴場でご協⼒いただきました。
しかしながら年末のインド洋で起こりました津波被害は、史上最⼤の犠牲者30万⼈を超えるような被災者が出る津波でありましたけれども、そのような津波被害も合わせて考えますと、私共としては、昨年何とか乗り切ったと⾔うことで満⾜してはいけないわけでありまして、これを教訓とし、またこれを糧として、これからの防災防⽕対策に⼼して取り組まなければならないと、こういう決意を新たにして新しい年を迎えているということを、先ず皆さんにお伝えをさせていただきたいと思います。
学ぶことが⼤変多うございました。
皆さん⽅もそれぞれの地域で災害対応なさいます時に感じたもの、反省したもの、いろいろおありだったろうと思います。
是非それを活かして今後の対策を実のあるものにしていただきたいと思うものでございます。
そこで、今私が考え消防庁職員に対してもお話をし、お願いをしているようなことをいくつか基本的な事でございますが、申し上げてご報告をさせていただきたいと思います。 ⼀つはやはり昨年の経験を踏まえて、もう⼀度認識を新たにしなければならないのは、災害は必ずやってくると⾔うことであります。
過去にやってきたけれども暫く無いのではないかと⾔うような気持ちで災害を⾒ている⽅も居られるかもしれません。
やはり昨年の災害を考えますと私共の周りにはやはり⼤規模な地震も含めて災害が多発するような時代を迎えているんだという認識をはっきり持った⽅が良いという気持ちを私は深めております。
特に⼤規模地震につきましては、何度も皆さんお聞きになっておられると思いますけれども、東海地震は何時起きてもおかしくない、とこう⾔われております。
南海地震、東南海地震につきましては今世紀前半に発⽣する確率がだんだん上がってまいりまして、最初は4割ぐらいから始まっていましたが、最近では5〜6割と⾔うような確率で、学者がその到来の懸念を表明をされております。
南関東の直下型地震につきましては、これは予測も何も出来ませんで、何時起きるか分からないと、こういう⾔葉で⾔われております。
また三陸沖につきましても、過去何度も地震津波の被害に直⾯されておりますけれども、これはまた何時同じ様な地震津波に⾒舞われるか分からない。
こういうような状況が今⽇の我が国を取り巻く状況になって居りますことは、皆さまご承知の通りでございます。
加えて昨今の新しい状況といたしまして、これもお聞き及びになっておられると思いますが、国⺠保護法と⾔う法律が昨年の通常国会で成⽴を致しました。
これは戦後の冷戦構造の中では、あんまり我が国では議論されていなかった問題でありますけれども、今⽇我が国においても、有事であるとかテロであるとか、そのようなことを考えざるを得ないような時代になってきておりまして、その際国⺠の皆さん⽅、地域の住⺠の皆さん⽅の安全をどのようにして確保するか、これも法律に基づいてしっかり平時から体制を作っておく必要がある。
こういう考え⽅の下で成⽴いたしましたのが国⺠保護法でありす。
その国⺠保護法の下では、例えば有事といいますと、そういうことは有ってはならないことでありますけれども、ミサイルが⾶んでくる時代である。
あるいは緊急対処事態と申しまして、テロ⾏為が⾏われるとか、テロ⾏為も国家的な組織によるテロもあれば⼀部政治的な意図の下にやられるテロもあれば、あるいは愉快犯的なテロ⾏為もあるかもしれませんが、そのような場合であっても、国⺠を保護するためには、どうしたらいいのか。というようなことを想定して国⺠保護法というものを作ったわけであります。災害は何時起きてもおかしくないと思うこと。そのようなテロ⾏為等が何時⾝辺で起きてもおかしくないと、こういう時 代に⼊っているんだということを認識をしなければならないというのが、先ず第⼀点であります。
その上に⽴ってでありますけれども、災害については備えをすることによって、被害を最⼩限に⾷い⽌めることが出来るということも確信を致しました。
昨年奥尻におじゃまをさせていただきましたが、あの地震、津波記念館で⼩学⽣の⼦どもさん達の作⽂を並べられておりました。
⾒ている中の⼀つに、「⾃然にはかなわない」というような⾔葉を書かれた作⽂が目にとまりました。
確かに⾃然の恐ろしさを知り、⾃然に対して畏敬の念を持つということは⼤切でありますけれども、しかし、⽣きている我々と致しましては、そういう⾃然の猛威あるいは災害に対して如何にして備えをしていくか、これも我々の努めであります。確かに災害は避けられません。
しかし、備えをすることによって被害を最⼩限に⽌めることが出来るんだと⾔うことも、改めて私共再確認をしなければならないと思っております。
⼀例でありますが、正確な数字は覚えておりませんが、10年前の阪神・淡路⼤震災の時には、沢⼭の死者の⽅を数えたわけでありますけれども、あの際⽕災の件数が、確か230件程度起きたと聞いております。
そして地震によってではなくて、⽕災によって亡くなられた⽅の数が560名程度だったというふうに聞いておりますが、今回新潟県中越地震の際は、⼤変不幸な被害でありましたし、亡くなられた⽅が40⼈に達しておりますが、幸いなことに⽕災は9件しか起こっておりません。
そして⽕災で亡くなられた⽅は0であります。
10年の間に、やはりそれぞれの地域におかれまして防⽕対策に努⼒をしていただきました成果がそのような形で現れているのではないかと思います。
また、阪神・淡路⼤震災の際の反省教訓を本にいたしまして政府におきましても、地⽅団体におきましても、それぞれの地域社会におきましても災害対応、目を⾒張るような進歩充実が図られていると思いますけれども、そのようにやはり備えを充分にすることによって被害を最⼩限に⾷い⽌めることが出来るのは間違いないと、こういう⾃信を是非持っていただきたいと思います。
そういう観点に⽴って、私共いろいろと防災対策を進めて⾏かなければならないわけでありますが、消防庁と致しましても⼼新たに取り組むことと致しておりまして、私は、象徴的に職員に対して平時のモードを緊急時モードに切り替えようと、こういうふうに話し、みんなでそのような体制づくりを急いでおります。
やはり災害の教訓から学ぶべきものは、我々は災害に対してどうに対応するか、その時何が必要か、いろいろと設備⾯でもハード⾯でもソフト⾯でも訓練もやっているわけでありますが、如何にせん、どの訓練も平時の訓練に⽌まっております。
昨年の新潟の地震の際、ある市町村では全ての設備は整い訓練も充分にやっておられましたが、実際の時には役に⽴ちませんでした。
役に⽴たなかった⼀番の事例を申し上げますと、緊急時は必ず停電になります。停電になるから非常⽤電源を備えておられました。
しかし、訓練は平時にやっておられますから停電をする状況での訓練はやっておられません。
いざ停電だという時に、非常⽤電源の使い⽅を知らないまま⼀夜が明けたというようなこともありました。
それから瀬⼾内海の⽅では昨年⾼潮で随分やられましたけれども、災害時に⽔門を閉めるとか、あるいは電源の消灯を防護するために電源を切るとか、そういうことも考えて、平時に訓練をされていたようでありますが、⽔につかるような所に電源施設をおいて置かれたために、やはり災害時は電気が⽌まる。
地震で毀れる、⽔につかると、そのようなことになるわけでありますので、そういうような事態を想定して如何にその時に救助救出を効果的にやるか、⽣き延びるかというような訓練をしていただく必要があるわけであります。
私共もそういうことで、平時ではなくて緊急時にどう対応できるか、こういう体制を整えようというキャッチフレーズのもとに、消防庁はいろいろとやっております。
「緊急消防援助隊」、昨年⼤変活躍をしてくださいました。阪神・淡路⼤震災の時には、それなりの各県からの応援が出たわけでありますけれども、応援に⾏った⼈達の指揮が統率が取れていなかったという反省もありまして、緊急消防援助隊という制度が、その後発⾜を致しておりました。
昨年制度的に、法制度上のものとして位置づけまして、もし何かありましたら各県から応援が出るという体制を整えるとか、現場に⾏った場合、消防庁の職員が先ず市町村⻑の側に先遣隊として⾏って、全国から来た応援隊の指揮を執るとかいうようなことも考えております。
それなりの装備も調えていかなければならないと思っております。参考までに申し上げますと、緊急消防援助隊、全国で今消防15万⼈おりますが、その内の約3万5000⼈、所謂指揮隊から後⽅⽀援部隊も含めまして3万5000⼈、隊にして2821隊を現在緊急消防援助隊として、私共の所に登録をしていただいております。
何かありましたら市町村消防だけでは対応出来ない。
あるいは県隊だけでは対応できない場合は、他県からの応援をする制度が整っておりますので、その体制を整備していくのが私共の使命だと思っております。
しかしながら、その様に私共消防庁あるいは全国15万⼈の消防職員の体制を今後とも充実してまいりますが、しかし3つめに皆さんに是非知っておいていただきたいことは、国⺠の教訓でありますけれども、⾏政の⼒にはやはり限界があるということであります。
いくら消防庁が、あるいは消防職員が資材機材あるいは訓練を重ねて体制を整備しましても、残念なことに地域の皆さん⽅の被害をもっともっと⾷い⽌めることが出来るものを、⾏政だけではやるのには限界があることも昨年悟りました。
昨年、局地的な豪⾬と台風でお亡くなりになられた⽅が230⼈いらっしゃいます。地震で亡くなられた⽅が40⼈いらっしゃいます。
それを分析をいたしてみますと、65歳以上の⽅が60数%、約 2/3に上って居ります。
特に局地的な集中豪⾬台風の際に亡くなられた70歳以上の⽅々の、お亡くなりになったときの状況を具体的に調べてみますと、非常に不幸な状況で悲惨な形で終わっている事例が⾒受けられるわけであります。
つまり申し上げたいことは、県なり市町村の消防が如何に頑張ってもその⼈達を救えなかったであろうという事例が多いわけであります。
助かった⽅々を逆に⾒てみますと、地域社会の⽅々が助けてあげている。急に⽔が出てきた、あるいは台風で屋根が⾶んだ、と⾔うようなときに隣近所の⼈が助けることが出来たかどうか。
あるいは⼀緒に住んでいる⽅が、ご⽼⼈を背負って避難できたかどうか、これによって助かった⼈と助からなかった⼈の、特に⾼齢者の⼈についてでありますけれども、差が出ているような分析がされております。
私が申し上げたいことは、⾏政の⼒には限界があると⾔うことを悟って地域社会の防災⼒をどうしても強めていかなければ、被害を最⼩限に⾷い⽌めることが出来ないと⾔うことを痛感いたしたということであります。
地域の防災⼒といいますのに⼆つありまして、⼀つは市町村はどのような体制を取っていただくかということ。もう⼀つは、市町村とは別に、今⽇お集まりの全国223万⼈を擁しておられます婦⼈防⽕クラブの皆さん⽅の組織、あるいは93万⼈を擁する消防団員、その他⾃主防災組織、少年消防クラブ等々、いろんな組織があるわけでありますけれども、このような⽅々が地域社会でどのような役割を担っていただけるかと⾔う点と2つあろうかと思います。
昨年の災害を振り返ってみますと、市町村にもまだまだ体制の不充分な点があるということを私共確信を致しまして、昨年来全国の市町村⻑さんに対し警鐘を発し、お⼿紙を差し上げ、具体的には市町村⻑さん⾃らが停電時を想定して、非常⽤電源を使って消防庁に電話をしてみてください、と⾔うような訓練も年末年始にかけて、全国の市町村でやらしていただきました。
そういうふうにそれぞれの市町村では、防災⾏政無線をどのように整備しておくか、何かあったときに住⺠の⽅々に直ぐその情報が伝わるようなシステムを、どうしても⽤意しておいていただく必要があります。それが整備されていないところもあります。全国で68%の整備率であります。
あるいはそれが整備されましても、どのような時点で避難勧告を出したらいいのか、避難指⽰をしたらいいのか、また何処に避難をしていただいたらいいのか等々についても、充分な体制訓練が出来てない市町村もありました。
それから地震の際でいいますと、地震が起こったときに災害拠点となります公共施設が潰れてしまって使えなかったというようなことも、現実にあったわけでありますけれども、やはり個々の住宅の耐震化も勿論でありますけれども、防災拠点であるとか、あるいは公⽴⽂教施設であるとか、その様なところの耐震化が出来てない。
何時起きてもおかしくないと思われている地域ですら、まだその様な安全策が講じられてないというような市町村もあります。
特に私が急いでいただきたいなと思っておりますのは、防災マップの作成であります。
当地域は、地震台風あるいは津波についてどのような懸念があるのか、それを想定した上で、もしそういうことが起こった場合は、それぞれの地域はどのような被害が出てくるのか、例えば東南海地震が起こった場合は、此処の集落は何分後にどのくらいの⾼さの津波が来るのか、ということを想定をしたような災害マップを作っていただいているところが多いわけでありますけれども、やはりそれを最新のものにして、住⺠の⽅々にそういうような時にはこのようになるんだということを周知していただき、そのような場合、それぞれの⼈がどのような体制を取ったらいいのかを考えられるような場を与えていただきたいと思うわけでありますけれども、これもまだ充分に出来ていないところがある。
このようなことがあります。
それから、これは特に今⽇申し上げたいことでありますけれども、市町村につきましては、縦割りを廃していただくような体制をお願いしたいと⾔うことを申し上げております。 昨年の災害で⾒ましたら、それぞれのセクションは最⼤限の活動をしてくださいましたけれども、結果として効果的効率的に充分な成果が挙げられなかったという地域が多く⾒られました。
消防は消防でしっかりやりました。
防災は防災でしっかりやりました。それから警察は警察でしっかりやりました。
⺠⽣は⺠⽣でしっかりやられました。
しかしながら、⺠⽣の⽅々が毎⽇⼀⼈暮らしの⽼⼈を⾒回り声を掛けておられるのに、災害時にその様なお年寄りの⽅々を助ける体制は⺠⽣だけでは出来ないわけでありますけれども、消防あるいは⾃主防災組織あるいは地域の婦⼈防⽕クラブ等々との連絡が充分でなかったがために、⾔葉は悪いのですが⾒捨てられた形で亡くなられるという例がありました。 基本的には、これは市町村が今まで縦割りできましたものを、横串をさして消防と防災と⺠⽣と、場合によったら商⼯、⼟⽊とも⼀体となって地域の救出救助のために働くような体制を作っていただきたいと思っているわけでありますけれども、なかなか難しい所があるようであります。
そこでお願いをしたいのは、それぞれの地域において⾏政の線も来ていると思いますけれども、皆さん⽅のような婦⼈防⽕クラブあるいは消防団あるいは⾃主防災組織あるいは⺠⽣の組織もあるかもしれませんが、そういう組織が横に⼀つの串で刺された形で、地域で総合的な防災体制として地域の⼈達を⼀⼈でも助けるような体制を作っていただけないかと⾔うのが私の問題意識でありお願いをしたいところであります。
その核となる消防団の充実強化は、最⼤の課題だと私思っておりますが、私の意図するところは、別に消防団でなくても良いんです。
今⽇お集まりの皆さん⽅のように、しっかりとしたリーダーシップを持っておられる⽅が居られる地域は、皆さんがそのリーダーになったいただきたいと思うわけでありますが、誰かがリーダーになってそれぞれの防⽕防災のために働いている⽅々を、総合的な⼒として地域の安全対策に振り向けられるような、体制づくりをお願いしたいと思っているわけであります。
私はあるところで、地域の⼈全員が消防団になるというようなことを話そうとしましたら、内の職員が、「それは⾔い過ぎですから⽌めてください」と、こういったんでありますが、気持ちを申し上げているわけであります。防⽕クラブは防⽕クラブのままで良いと思います。
消防団は消防団のままでいいと思いますけれども、全員が地域の防⽕防災に当たる消防団員として意識を持って当たれるような、働きを考えたら事故があったら困るなーという気持ちが有るものですから、私はその消防団としての肩書きをお持ちになって、なんかあったときには災害補償の対象になるような形で、皆さんが全員消防団に⼊っていただければ有り難いなと、こういうふうな気持ちは率直に⾔ってあります。名前に拘っているわけではありません。
お願いをしたいのは地域でみんなが善意で、地域の⼈を助けよう、被害を最⼩限に⾷い⽌めようと思っている⼈達の気持ちが結果として出るためには、そのようなことをこれから考えていかなければならない。
それぞれの組織がバラバラにやって居るんでは⼒が出せないという点に重⼤な問題があるのでは無かろうかと思っております。
そういうこともありまして、昨年「安⼼安全ステーション」という構想を発表させていただきまして、今年度モデル事業もやらせていただいておりますし、明年度は全国100ヶ所でモデル事業をやらしていただこうと思っております。
モデル事業の対象にならなかったからやらないんだということではなくて、モデル事業は私共が⼀緒に知恵を出せていただきまして、こういう形で出来るんではないかと姿を作ってみたいということでありまして、全国でもしご賛同いただけましたら、このような動きを深めていただきたいと思うわけであります。
これは⼩学校区単位を考えております。ご存じのように⼩学校区というのは全国で2万4000位あるようでありますが、消防団の分団の数も⼤体2万4000位と聞き及んでおります。郵便局の数も特定郵便局も含めまして2万4000位であります。そのことから考えまして、⼤体地域のコミュニティというのは、⼩学校区単位というのが⼀つのユニットになっているのかなと思います。
特に⼩学校区単位というのは⼦供さんの教育を通じて、特に今⽇お集まりのご婦⼈の⽅々の連携は非常に私的にも公的にも強いものがあると思いますし、いろいろと家庭の事情もご存じで、お付き合いもされているユニットであると思うわけでありますが、その様な地域を単位として消防団も婦⼈防⽕クラブも少年消防クラブも防犯も⽔防もみんなが集まって、あるいは各⼩学校の空き教室があればそこを拠点とし、消防団の詰め所でも公⺠館でも婦⼈防⽕クラブの会議室でも良いと思いますが、何処か拠点を決めていただきまして、そこで地域内の⽅々の安否情報をプライバシーに反しない限り範囲で確認をしながら、普段の防⽕対策あるいは警報機の設置の指導あるいは場合によっては、警察からの話があれば、防犯も⼀緒にやっても良いと思いますが、兎に角地域の⽅々を守るための拠点を、⼩学校区単位ぐらいで作り、地域の⼈の被害を最⼩限に⾷い⽌めるような対策を普段からやっていただけないかと思いまして、「安⼼安全ステーション」というのを提⾔させていただいております。是非どのような構想なのか、課⻑がお話しすると思いますが、気に留めていただきご賛同いただければご協⼒をいただきたいと思っております。
その様なことが広がりまして、それぞれの地域が本当に安⼼して住めるような地域になっていただきたいというのが、私共の願いであります。
勿論⾏政として、消防職員として最⼤限のご⽀援努⼒をするつもりでありますけれども、究極は地域の被害を最⼩限に⾷い⽌めるためには、そのような地域の防災⼒、特に地域の皆さん⽅の⾃助、共助無くしては駄目なんではないだろうかというふうに思ったものですから、その様なお話をさせていただきたいと思ったわけであります。
先⽇全国の消防団の会⻑さんの集まりが此処でございまして、ご挨拶をさせていただきましたが、その時、⼀つこれをお願いを致しました。
そういう観点から総点検をお願いしたいと、総点検の観点は、「今何が出来るかではなくて、これから来る地震津波あるいは台風に対して、来たときには何をしなければならないのかということを、もう⼀回⽩紙で考えていただきたい」と、そして「何をしなければいけないかを考えたときに、初めて今で充分な部分と⾜りない部分が分かってくると思います。⾜りない部分をどのようにして補っていくかという観点から体制の整備をしていただきたい」ということをお願いを致しました。
地域の防災マップを是非ご確認をいただき防災マップに照らして、今の地域の安全対策は充分なのかどうか総点検をしていただきまして、必要な対策をしていただきたいと思います。私共、社会のお役に⽴つために⼀⽣懸命にやらなければならないと思っておりますが、よく申し上げるわけでありますが、究極は皆さんにお願いしたいことは、⼈を助けるのも良いんですけれども、先ず⾃分のご家族を助ける、⾃分の⼦供を助ける、⾃分の亭主を助ける、親戚を助ける、友⼈を助ける、そこから地域の防災対策の根っこは、しっかりと根付いたものになるのではないだろうかと思っております。
消防団の皆さんにも家庭を犠牲にして消防団に⼊るんだというふうに思わないでいただきたいと、先ず⾃分の家族を守るために⼈を助ける、そうすれば⾃分の家族も守っていただける。
それが地域の理想的な防災体制のあり⽅ではないだろうかということを申し上げて、地域防災⼒の充実強化をお願いを致しているところであります。
意のあるところをお酌み取りいただきまして、ご苦労でございますけれども地域でのご活躍をいただければと思っております。
皆さんの今後のご活躍ご健康を⼼からお願いを申し上げまして私のご挨拶とさせていただきます。どうも有り難うございました。