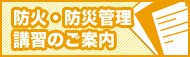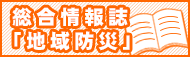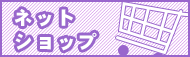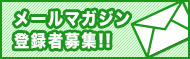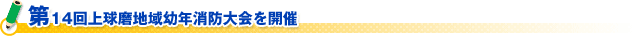

平成16年11⽉2⽇(⽕)、幼年消防クラブ員が待ちに待った、上球磨地域幼年消防⼤会を実施しました。
今年で第14回目を数える本⼤会は、管内で結成されている幼年消防クラブ18クラブのうち17クラブ441名が⼀堂に集い、2年に1度のイベントとあってクラブ員は皆⼼待ちにしていましたことと思います。
第1部の式典のあと、第2部ではクラブ代表者18名によるくすだま割りのオープニングから始まりアトラクションでは、早苗保育園幼年消防クラブによるきびきびとした通常点検の披露に観客は皆目を細めて喝采の拍⼿を送っていました。
そのあと、消防署救助隊による展⽰訓練等の披露があり、続いて約2時間わんぱく広場で消防⾞の⾒学、ミニ消防⾞試乗、ミニSL試乗、煙体験、フワフワエレファントなどのコーナーを回って、短い時間ではありましたが楽しいひと時を過ごすことができたと思います。
閉会式では全員で「⼿のひらを太陽に」を合唱し、⼼を新たにして『防⽕の誓い』を再確認し全⽇程を終了しました。


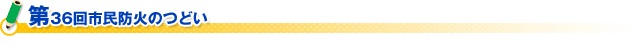
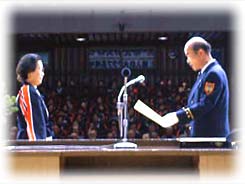
防⽕意識の⾼揚を目指す「第36回市⺠防⽕のつどい」が11⽉17⽇(⽊)⿂の町・⻑崎市公会堂において⾏われれました⻑崎市婦⼈防⽕クラブ連絡協議会(松本スミ⼦会⻑)や市消防局などが、各地域の防⽕団体の連携を強めようと毎年開催しているものです。市内の340の婦⼈防⽕クラブ、40の少年消防クラブなどから約2,000名が参加しました。
つどいでは⻑崎市消防局⻑より、婦⼈防⽕クラブ会⻑職を20年間務めた⻄本妙⼦さん、尾上千代⼦さんら6名をはじめ、防⽕活動に功績のあった計23名に表彰状を贈呈し、また、参加者全員で「相互連帯を密にし、さらに⼤きく防⽕防災の輪を広げます」と防⽕宣⾔を読み上げました。
防⽕意識の普及啓発と、会員相互の親睦を図ることによって、各クラブ員の⾃主性と連帯意識が醸成され、ひいてはこれが積極的な防⽕防災活動につながり、「⾃分たちの地域は⾃分達で守る」という目標達成が図れました。


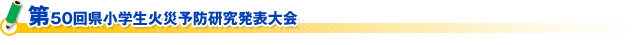

第50回県⼩学⽣⽕災予防研究発表⼤会が、11⽉13⽇(⼟)富⼭市消防本部で⾏われました。県内18⼩学校の計98名が参加し、氷⾒市加納⼩学校6年(⼤森遼君、⾦⾕太智君、萩⼭承⼦さん、酒元暁啓君、坂絵⾥菜さん、⼤⽯⼤佑君)が特選と北⽇本新聞社表彰に、⾼岡市万葉⼩5年が⾦賞に選ばれました。
加納⼩は「ヒューマンネットワークを⼤切にした防⽕プロジェクトの輪」をテーマに、世代ごとの防⽕対策について発表し、万葉⼩は動画などを駆使し、⽕災から同校区を守る活動を紹介しました。参加者はこのほか、地元消防団の活躍や⽕事の原因などを調べて⽕災予防の⼤切さを訴えました。
北⽇本新聞社の⽵沢事業部⻑が講評、県消防防災課の藤井課⻑が受賞者に賞状などを⼿渡しました。表彰は次の通りです。
特選・氷⾒市加納⼩6年、⾦賞・⾼岡市万葉⼩5年、銀賞・南砺市井⼝⼩6年、⼩⽮部市⼤⾕⼩5年、銅賞・南砺市福野⼩5年、細⼊村⼤沢野町学校組合神通碧⼩6年


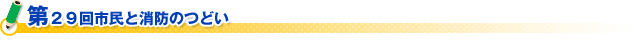

平成16年11⽉14⽇(⽇)午前10時00分から午後2時00分まで、第29回「市⺠と消防のつどい」を別府公園で開催いたしました。
この催しは、秋の全国⽕災予防運動⾏事の⼀環として【⽕災のない,明るい街づくり】をめざして、市⺠の皆様に防災意識の⾼揚や、⽕災予防思想の普及を図るため、体験や⾒学を通じ理解を深めていただくため開催したものです。
催し物については、餅まき・明星幼稚園幼年消防クラブの⿎笛演奏・はしご⾞試乗体験・救急隊員と⼥性消防団員による応急シミュレイーション等その他チビッ⼦レインジャー・煙の怖さ体験・⽔消⽕器による消⽕チャレンジャーなど、多くの体験コーナーを⽤意しましたところ、⼤変好評でした。
また、当⽇は17地区社協及び福祉団体による模擬店などを含め多彩な⾏事が繰り広げられました。
なお、天気予報によれば90%と⾬予想が発表されたが、予想とは⼤きく違い晴天に⾒ぐまれ多数の市⺠(約30,000⼈)が参加して頂きました。


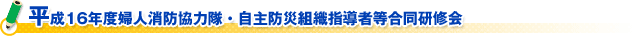

両盤地区幼少年婦⼈防⽕委員会では、11⽉20⽇(⼟)管内の川崎村⽣涯学習センターにおいて、婦⼈消防協⼒隊と⾃主防災組織指導者等の合同研修会を実施しました。
研修会は、幼少年消防クラブの指導者、婦⼈消防協⼒隊員、⾃主防災組織の指導者ら180名が参加しました。
川崎村婦⼈消防隊⻑ ⼩野寺さち⼦さんの体験発表では、平成13年の隊⻑就任時からの取り組みを振り返るとともに、今後の活動への展望を⽰しました。特に、就任2年目には「実際に即した活動を」との考えから『総会時の普通救命講習』『班⻑を対象にした初期消⽕訓練』『郡下連合演習で軽可搬ポンプ操法を実施』など、多彩な活動を導⼊したことを紹介しました。これからに向けては「非常時の⾏動や対処など、1回の参加で多くのことを学べる取り組みを⼼掛けたい。また、⾃主防災組織と協⼒して、災害に強い地域づくりを実践したい」と意気込みを述べました。
体験発表後、IBC岩⼿放送の河辺邦博⽒の講演が⾏われました。講演では、昨年5⽉宮城県沖を震源とする地震において放送局の施設が被害を受け、報道をする者としてたいへん悔しい思いをしたことから、⽇頃の災害に対する備えが非常に⼤切であること、地震災害によるPTSD(⼼的外傷後ストレス障害)の実態などの話がありました。
参加した⾃主防災組織の指導者は、「非常に親しみやすい雰囲気の中で講演の内容が具体的で、時を忘れて話を聞くことができた。災害に対する備えの⼤切さを再認識した。」と気持ちを新たにしていました。
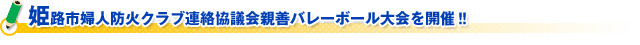

姫路市婦⼈防⽕クラブ連絡協議会(溝脇静⼦会⻑)では、春季⽕災予防運動に先⽴ち、2⽉26⽇(⼟)に「第19回姫路市婦⼈防⽕クラブ連絡協議会親善バレーボール⼤会」を開催しました。
この⼤会は、平成7年の阪神淡路⼤震災の年を除き、昭和61年から毎年開催しており、今年で19回目。バレーボールを通じて、婦⼈防⽕クラブ員相互の親睦と連帯及び有事の協⼒体制を強化しました。
出場チームは、昨年秋の各地区婦⼈防⽕クラブ連合会親善バレーボール⼤会の予選(37チーム参加)を勝ち抜いた精鋭12チーム(120⼈)。
また、防⽕・防災意識の⾼揚を図るため防⽕研修を毎回実施。今回は、新たな住宅防⽕対策の必要性をクラブ員に理解してもらうため、「住宅⽤⽕災警報器」の取り扱いと⼀般住宅への設置義務化等について研修しました。
1.⽇時
平成17年2⽉26⽇(⼟)
9時30分から15時30分まで
2.場所
姫路市⻄延末90 姫路市⽴中央体育館
3.試合結果
| ○優 勝︓ | 別所校区婦⼈防⽕クラブ (姫路東婦⼈防⽕クラブ連合会) |
| ○準優勝︓ | ⼋幡婦⼈防⽕クラブ(飾磨婦⼈防⽕クラブ連合会) |
| ○第3位︓ | 御国野校区婦⼈防⽕クラブ(姫路東婦⼈防⽕クラブ連合会) 安室婦⼈防⽕クラブ (姫路⻄婦⼈防⽕クラブ連合会 |




●上天草市誕⽣後初の消防出初式
今年も、新春を告げる消防出初式が1⽉2⽇から9⽇まで天草各地で⾏われ、各市町の防⽕クラブ員多数が参加して華を添えました。
1⽉4⽇、上天草市誕⽣後初の消防出初式に⼤⽮野町あそか保育園幼年消防クラブが参加しました。同クラブは昨年7⽉に結成されたばかりですが、5⽉の連休明けから練習してきたマーチング演奏を⽴派に披露することができました。少々緊張気味でしたが、元気いっぱいのその姿は寒さにも負けない凛々しい姿でした。
本渡市の宮⼝区婦⼈防⽕クラブは、1⽉6⽇の本渡市出初式に参加しました。クラブ員は各家庭の主婦であり、訓練のある⽇は、⼣⾷の後始末も早々に済ませ、海からの潮風を受ける佐伊津漁港前広場で訓練を重ねました。出初式では星光園婦⼈防⽕クラブとともに規律ある⼊場⾏進、通常点検でした。
また、新和町消防出初式では、新和⼩学校と⼤多尾⼩学校の少年消防クラブ員が碗⽤ポンプを使った珍しい⽟落とし競技を⾏いました。ポンプ突き⼿が「ワッショイワッショイ」の元気な掛け声でポンプを突き⾒事に⽟を落としていました。
その他にも各市町で幼少年消防クラブが出初式に参加し、将来を担うチビッコの勇姿に観客から喝采が寄せられていました。
 ●牟⽥地区のお年寄りを訪問
●牟⽥地区のお年寄りを訪問
上天草市⽴牟⽥⼩学校少年消防クラブでは、12⽉20⽇牟⽥地区のお年寄りを訪問し、⼼を込めて育てた花鉢を贈り、健康⻑寿を祈った作⽂を読みあげて防⽕を呼びかけました。
これは、⼀⼈暮らしのお年寄りを訪問し、防⽕を呼びかけることをとおして、お年寄りを慕う⼼情と少年消防クラブ員としての意識の向上を図る目的で、毎年実施しています。
当⽇は、クラブ員26⼈が4班に分かれ、校⻑先⽣以下教職員5⼈、上天草市消防団⼤川副団⻑、地区分団⻑、東天草分署職員と⼀緒に13⼈のお年寄りを訪問しました。
「スイートピー」と「キンギョソウ」2個の花鉢を受け取ったお年寄りは、クラブ員の温かい⼼遣いに感謝し、笑顔で防⽕を約束されていました。
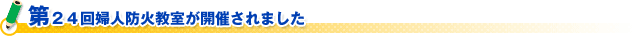

平成17年1⽉22⽇(⼟)、浜⽥地区消防本部において「第24回婦⼈防⽕教室」が開催され、管内婦⼈防⽕クラブ員が消⽕訓練、避難訓練、応急⼿当訓練等を体験しました。
⽇頃⽕を取り扱う機会の多い⼥性の皆さんに、家庭における防⽕意識の⾼揚と地域に防⽕の輪を拡げていただくため管内18防⽕クラブの代表者22名が参加して開催されました。
午前中は浜⽥地区消防本部予防課⻑の挨拶に始まり、防⽕の話や地震の話、防⽕映画の上映を⾏い防⽕の知識を学びました。特に⼀般家庭に義務設置とされる住宅⽤⽕災警報器の説明は、皆さんが真剣に聞いておられました。
午後からは煙の体験に始まり、消⽕訓練、応急⼿当訓練を⾏い、消⽕訓練時は実際に燃え上がっている炎を消⽕する際の⾊々な消⽕⽅法や注意事項を真剣に聞き、実際に消⽕器で消⽕する際はスムーズに消⽕できました。
今回の開催で24回目となりましたが、参加していただく⽅は過去の参加者以外の⽅としており、防⽕思想の拡⼤に今後とも努めて⾏きたいと思っております。