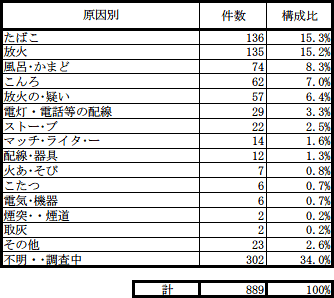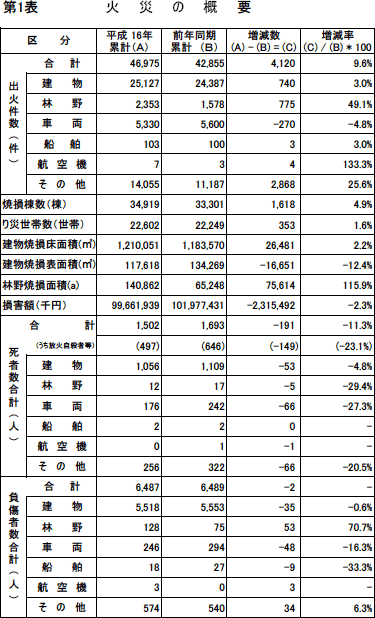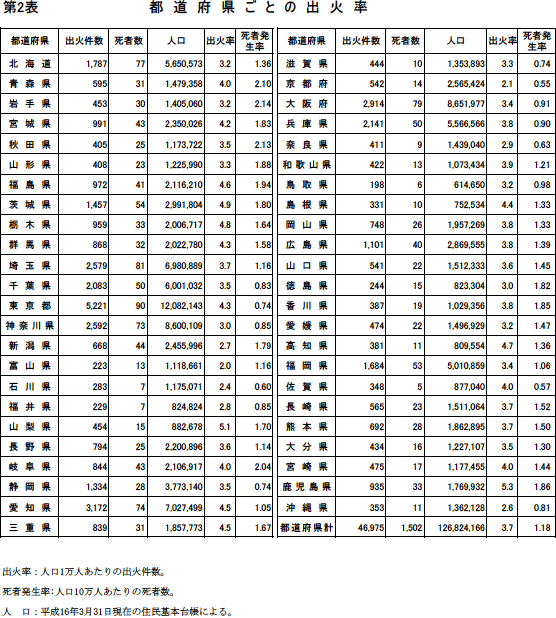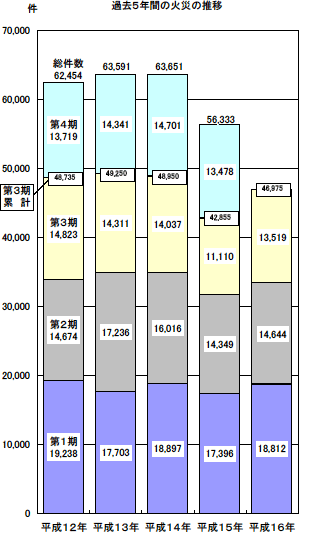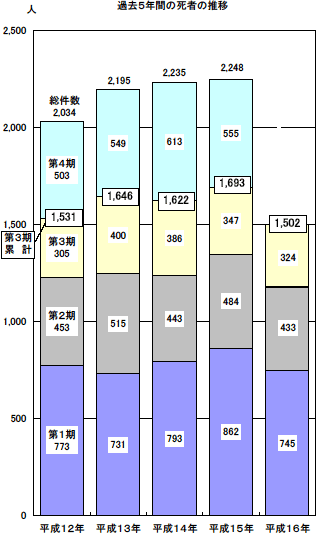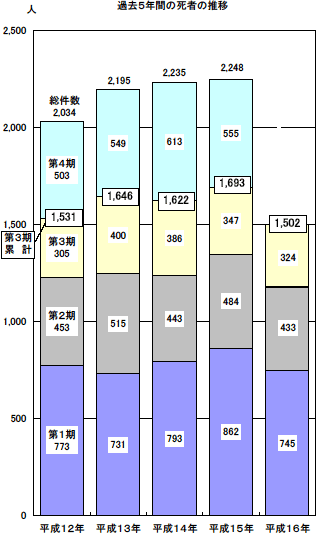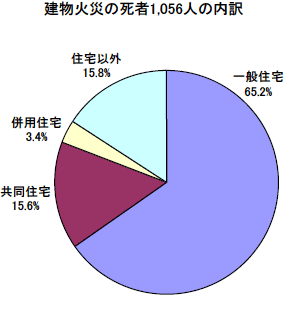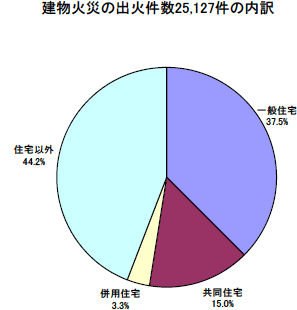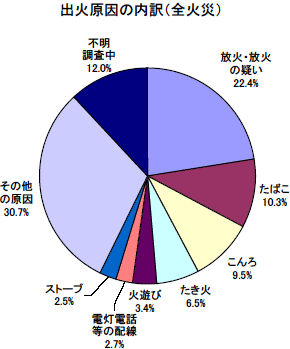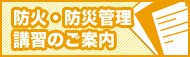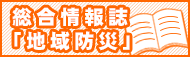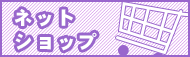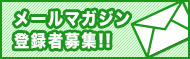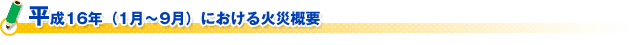
| (1)総出⽕件数は、46,975 件、昨年同期⽐4,120 件(9.6%)増加 (2)⽕災による死者は191 ⼈、負傷者は2 ⼈減少 (3)住宅⽕災死者(放⽕⾃殺者等除く)は26 ⼈減少、57.0%が⾼齢者 (4)「放⽕」、「放⽕の疑い」は、0.3%減少したが、⼤都市部に多い傾向 |
(1)総出⽕件数は46,975 件で、昨年同期より4,120 件(+9.6%)増加しました。
(2)⽕災種別ごとに⾒ると、特に林野⽕災が2,353 件で775 件(+49.1%)増加し、その他⽕災も2,868 件(+25.6%)増加しました。⼀⽅、⾞両⽕災は5,330 件で270 件(-4.8%)減少しました。
(3)⽕災による死者の総数は1,502 ⼈で、昨年同期より191 ⼈(-11.3%)減少しました。負傷者は6,487 ⼈で昨年同期より2 ⼈減少しました。
住宅⽕災による死者は728 ⼈(放⽕⾃殺者等は除く)で、年間1,000 ⼈を超えた昨年と⽐べると26⼈の減少ですが、依然予断を許さない状況です。このうち415 ⼈は65 歳以上の⾼齢者となっており、死者の57.0%を占めています。
(4)出⽕原因の22.4%は「放⽕」及び「放⽕の疑い」、昨年同期より27 件(-0.3%)減少しましたが、これを地域別にみると、⼤都市部を抱える5都府県で全体の52.1%を占めています。
平成16 年12 ⽉17 ⽇ 総務省消防庁
平成16 年(1 ⽉〜9 ⽉)における⽕災の概要(概数)
1 総出⽕件数は対前年⽐4,120 件の増加
平成16 年(1 ⽉〜9 ⽉)における総出⽕件数は46,975 件であり、前年同期と⽐べると、4,120 件の増加(9.6%)となっております。
これは、おおよそ1 ⽇あたり172 件、8 分に1 件の⽕災が発⽣したことになります。
⽕災種別ごと前年同期⽐較をみると、建物⽕災25,127 件(740件の増・+3.0%)、⾞両⽕災5,330 件(270 件の減・-4.8%)、林野⽕災2,353 件(775 件の増・+49.1%)、船舶⽕災103 件(3 件の増・+3.0%)、航空機⽕災7 件(4 件の増・+133.3%)、その他⽕災14,055件(2,868 件の増・+25.6%)となっています。林野⽕災は、前年同期と⽐べると⼤幅に増加しています。
2 ⽕災による死者は191 ⼈、負傷者は2 ⼈の減少
⽕災による死者は1,502 ⼈で、前年同期と⽐べると191 ⼈の減少(-11.3%)となっています。
⽕災種別ごと前年同期⽐較をみると、建物⽕災1,056 ⼈(53 ⼈の減・-4.8%)、⾞両⽕災176 ⼈(66 ⼈の減・-27.3%)、林野⽕災12 ⼈(5 ⼈の減・-29.4%)、船舶⽕災2 ⼈(増減無し)、航空機⽕災0 ⼈(1⼈の減・-100%)、その他⽕災256 ⼈(66 ⼈の減・-20.5%)の死者が発⽣しており、全体的に死者が減少しています。
⽕災による負傷者は6,487 ⼈であり、前年同期と⽐べると2 ⼈の減少(-0.0%)となっています。
⽕災種別ごとにみると、建物⽕災5,518 ⼈、⾞両⽕災246 ⼈、林野⽕災128 ⼈、船舶⽕災18 ⼈、航空機⽕災3 ⼈、その他⽕災574 ⼈の負傷者が発⽣しています。
また、放⽕⾃殺者等は、前年同期より149 ⼈少ない497 ⼈となっています。
3 住宅⽕災による死者(放⽕⾃殺者等を除く)は728 ⼈で、26⼈の減少
建物⽕災における死者は、1,056 ⼈ですが、このうち住宅(⼀般住宅、共同住宅及び併⽤住宅)⽕災における死者は、889 ⼈であり、放⽕⾃殺者等を除くと728 ⼈となっています。これを前年同期と⽐べると26 ⼈の減少(-3.5%)となっていますが、年間1,000 ⼈を超えた昨年と⽐べても、依然予断を許さない状況です。
また、建物⽕災の死者に占める住宅⽕災の死者の割合は、84.2%で、出⽕件数の割合55.8%と⽐較して非常に⾼いものとなっています。
4 住宅⽕災による死者(放⽕⾃殺者等を除く)の約6割が⾼齢者
住宅⽕災による死者728 ⼈のうち、415 ⼈(57.0%)が65 歳以上の⾼齢者です。
また、住宅⽕災における死者の発⽣した経過別死者数の前年同期⽐較は、逃げ遅れ446 ⼈(70 ⼈の減・-13.6%)、着⾐着⽕38 ⼈(2 ⼈の減・-5.0%)、出⽕後再進⼊21 ⼈(2 ⼈の増・+10.5%)、その他223 ⼈(46 ⼈の増・+26.0%)となっています。
5 出⽕原因の第1位は「放⽕」、続いて「たばこ」
全⽕災46,975 件を出⽕原因別にみると、「放⽕」6,096 件(13.0%)、「たばこ」4,835 件(10.3%)、「こんろ」4,442 件(9.5%)、「放⽕の疑い」4,421 件(9.4%)、「たき⽕」3,074 件(6.5%)の順となっています。また「放⽕」及び「放⽕の疑い」を合わせると、10,517件(22.4%)となっています。
なお、前年同期は、「放⽕」6,249 件(14.6%)、「こんろ」4,339件(10.1%) 、「放⽕の疑い」4,295 件(10.0%)、「たばこ」4,052件(9.5%)、「たき⽕」2,254 件(5.3%)の順となっています。
「放⽕」及び「放⽕の疑い」を合わせた件数(10,517 件)を都道府県別にみますと、東京都(1,902 件)、⼤阪府(940 件)、神奈川県(930 件)、愛知県(910 件)、埼⽟県(801 件)の順となっており、上位5 都府県で全体の52.1%を占めています。
⽕災種別ごとにみると建物⽕災25,127 件にあっては、「こんろ」4,376 件(17.4%) 、「放⽕」2,825 件(11.2%)、「たばこ」2,574 件(10.2%) 、「放⽕の疑い」1,752 件(7.0%)、「ストーブ」1,160 件(4.6%)の順となっています。
林野⽕災2,353 件では、「たき⽕」592 件(25.2%)、「たばこ」312 件(13.3%)、「⽕⼊れ」266件(11.3%)、「放⽕の疑い」229 件(9.7%)、「放⽕」122 件(5.2%)の順となっています。
⾞両⽕災5,330 件では、「放⽕」698 件(13.1%) 、「排気管」533件(10.0%)、「放⽕の疑い」518 件(9.7%)、「衝突の⽕花」217 件(4.1%)、「たばこ」206 件(3.9%)の順となっています。
船舶⽕災103 件では、「放⽕の疑い」11 件(10.7%) 、「排気管」10 件(9.7%)、「電灯・電話線の配線」9 件(8.7%) 、「配線器具」7 件(6.8%) 「溶接機・切断機」6 件(5.8%)、の順となっています。
航空機⽕災7 件では、「排気管」、「電気機器」、「内燃機関」、「配線器具」、「衝突の⽕花」、「放⽕」、「その他」が、1件ずつとなっています。
その他⽕災14,055 件では、「放⽕」2,449 件(17.4%) 、「たき⽕」1,943 件(13.8%)、「放⽕の疑い」1,911 件(13.6%) 、「たばこ」1,742件(12.4%)、「⽕あそび」880 件(6.3%)の順となっています。
6 消防庁の対策について
(1) 住宅防⽕対策への取り組み
平成15年中の住宅⽕災における放⽕⾃殺者等を除く死者数は、1,041 ⼈(49 ⼈増)と昭和61 年以来の1,000 ⼈超となりました。このうち65 歳以上の⾼齢者は589 ⼈(61 ⼈増)であり58.2%を占めています。
消防庁では、⾼齢社会の進展に伴う⾼齢者の被害を軽減するため、平成3年から住宅防⽕対策推進協議会を中⼼として住宅⽤⽕災警報器等の普及など住宅防⽕対策を積極的に推進してきましたが、近年の住宅⽕災における死者の急増から、キャンペーン中⼼の対策には限界があることが指摘されていました。
このことを踏まえ第159 回国会に於いて、住宅に住宅⽤防災機器の設置を義務づけること等を内容とする「消防法及び⽯油コンビナート等災害防⽌法の⼀部を改正する法律」が、衆・参両院とも全会⼀致で可決成⽴し、平成16年6⽉2⽇に公布されました。
この中で、住宅⽤防災機器の設置及び維持については、消防法第9条の2において、政令で定める基準に従い、市町村条例で定めるとされたことから、「消防法及び⽯油コンビナート等災害防⽌法の⼀部を改正する法律の⼀部の施⾏に伴う関係政令の整備に関する政令」(平成16年10⽉27⽇政令第325号)により消防法施⾏令を⼀部改正するとともに、さらに、「住宅⽤防災機器の設置及び維持に関する条例の制定の基準を定める省令」(平成16年11⽉26⽇総務省令第138号)を新たに制定しました。
今後、各市町村において条例が定められ、平成18年6⽉1⽇から施⾏されることとなります。
(2) 放⽕対策への取り組み
放⽕及び放⽕の疑いによる⽕災は、10,517 件で、全⽕災の22.4%を占めています。
消防庁では、平成12 年に「放⽕⽕災予防対策マニュアル」を作成し全国の消防機関に配布するとともに、平成14 年度から学識経験者、消防機関、関係⾏政機関等からなる検討会を開催し、放⽕・連続 放⽕に対する具体的な対策とその進め⽅などについて、検討を進めています。
放⽕⽕災を防ぐためには、⼀⼈ひとりが放⽕対策を⼼がけるだけでなく、地域全体として放⽕されない環境を作ることが重要です。
特に連続放⽕の発⽣地域においては、可燃物を放置しない、夜間にゴミを出さない、門灯を終夜点灯するなどの基本的な対策及び関係⾏政機関と地域住⺠が協⼒して、街灯の増設、炎センサー、対⼈センサーと連動した照明や放⽕監視機器の設置などの対策を推進するなど、地域全体による、より⼀層の警戒体制を構築することが必要です。
現在、地域が⾏う取り組みについて地域の現状分析と評価及びその対応策を総合的に⾏うことができるような仕組みについて検討を進めています。
また、先に⾏われた秋の全国⽕災予防運動(11⽉9⽇〜15⽇)においても、重点目標として関係機関と連携しつつ、被害軽減に向け積極的に放⽕⽕災防⽌の推進を図っています。
(3) 林野⽕災への取り組み
林野⽕災の件数は、前年同期と⽐較すると775 件の増加(+49.1%)となっており、特に2⽉においては348 件(+195.5%)も増加しています。また、延べ焼損⾯積は約1,409ha となっており、前年の756ha から⼤幅に増加しています。
なかでも平成16 年に⼊り、1 ⽉と2 ⽉に瀬⼾内地域、また4 ⽉には宮城県でいずれも焼損⾯積が100ha を超える⼤規模な林野⽕災が発⽣するなど、平成15 年に較べて林野⽕災の多発及び規模の⼤型化が憂慮されています。
平成16 年6 ⽉以降、⽕災気象通報の効果的な運⽤を⾏うため、気象庁と連携して、モデル県を4県(岩⼿、栃⽊、⼭⼝、熊本)選定のうえ、消防本部での観測データを地⽅気象台等に提供し、その提供データをもとに地⽅気象台から、より細分化された図形式の⽕災気象通報を⾃治体に提供してもらう取組み(試⾏)を推進しています。11 ⽉には、モデル県から試⾏の中間報告が提出されたところであり、今後は課題等を整理しながら全国への普及を検討していく予定です。
また、本年における林野⽕災の多発状況を踏まえつつ、主な原因である⼈的失⽕の抑制による林野⽕災の低減を図るため、平成16年10 ⽉には「林野⽕災の有効な低減⽅策検討会」を開催し、⽕災警報の効果的な運⽤、林野⽕災発⽣危険度予測システムの活⽤、失⽕抑制による林野⽕災低減のあり⽅などの検討を始めたところであり、年度内にその結果を取りまとめる予定です。
(4) 産業施設の防災対策の推進に係る取り組み
○ ⽯油コンビナート等特別防災区域における防災対策の充実強化
平成15年⼗勝沖地震で発⽣した出光興産㈱北海道製油所タンク⽕災事故を受け、「消防法及び⽯油コンビナート等災害防⽌法の⼀部を改正する法律」では、⽯油コンビナート等特別防災区域における防災体制を拡充することとされました。
これに基づき、「⽯油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の⼀部を改正する省令」(平成16年11⽉30⽇総務省令第140号)において、特定事業者による防災業務実施状況の定期報告制度について、報告の期間及び内容を定めました(12⽉1⽇施⾏)。なお、新たに配備を義務付けることとしている⼤容量泡放射システムの整備に関しては、公布後1年6⽉以内の施⾏に向け、当該システムの性能・機能及び配備⽅法等について検討を⾏っているところです。
また、屋外貯蔵タンクの耐震改修を促進するため、「危険物の規制に関する政令の⼀部を改正する政令」(平成16年7⽉2⽇政令第218号)において、旧基準により設置された屋外貯蔵タンクの耐震改修期限をタンクの規模別に2年⼜は3年繰り上げることとしました。
○ 指定可燃物及び指定可燃物に類する物品に係る⽕災予防対策の充実強化
平成15年8⽉に発⽣した三重ごみ固形燃料(RDF)発電所事故、9⽉に発⽣した㈱ブリヂストン栃⽊⼯場⽕災などの事故を受け、「消防法及び⽯油コンビナート等災害防⽌法の⼀部を改正する法律」では、指定可燃物等の貯蔵・取扱を⾏う場所の位置・構造等(ハード⾯)に関して、消防法に市町村条例への委任規定を追加しました。各市町村においては、この委任規定を根拠に、ハード⾯の安全対策について、必要な事項を市町村条例で定めることとなります。
また、「危険物の規制に関する政令の⼀部を改正する政令」(平成16年7⽉9⽇政令第225号)により、廃棄物固形化燃料等を「再⽣資源燃料」として指定可燃物に追加し、防⽕安全対策の充実を図ることとしました。
さらに、各市町村の⽕災予防条例において指定可燃物等の⽕災予防対策の充実強化に必要な事項を定めるため、「⽕災予防条例(例)」の⼀部改正を⾏い、各都道府県知事及び各指定都市市⻑あてに通知しました。

(※前年⽐較値については、全て確定値です)
1 全国の概況
(1) ⽕災件数
平成16年(1⽉〜9⽉)における出⽕件数は46,975件で、これは、おおよそ1⽇あたり172件、8分に1件の⽕災が発⽣したことになります。これを⽕災種別ごとにみますと、次表のとおりです。
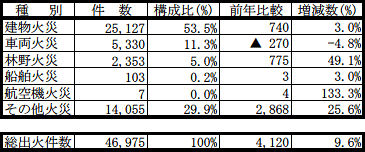
(2) 死傷者数
平成16年(1⽉〜9⽉)における死傷者数は、次表のとおりです。
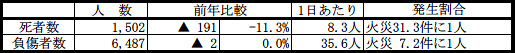
(3) ⽕災による損害
平成16年(1⽉〜9⽉)における⽕災損害は、996億6,194万円でその損害状況等は、次表のとおりです。
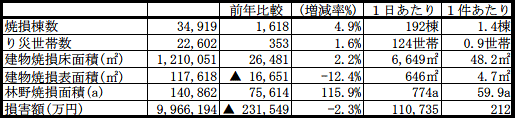
2 建物⽤途ごとの⽕災発⽣状況
建物⽕災25,127件を建物⽤途別にみますと、次表のとおりです。
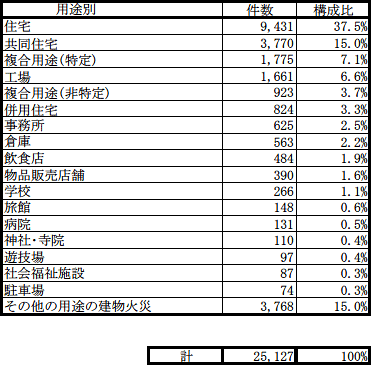
3 出⽕原因ごとの⽕災発⽣状況
| (1) 全⽕災 全⽕災46,975件を出⽕原因別にみますと、 次表のとおりです。 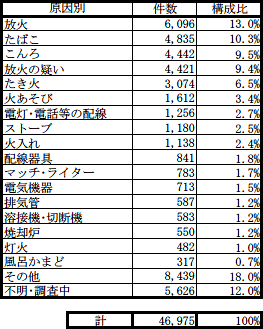 |
(2) 建物⽕災 建物⽕災25,127件を出⽕原因別にみますと、次表のとおりです。 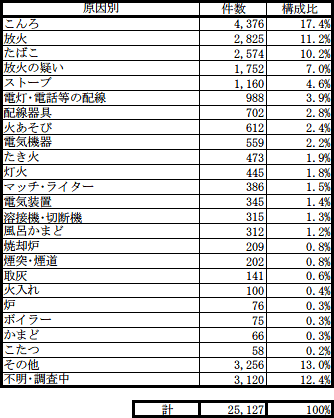 |
| (3) 林野⽕災 林野⽕災2,353件を出⽕原因別にみますと、 次表のとおりです。 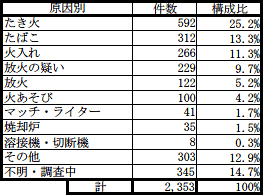 |
(5) 船舶⽕災 船舶⽕災103件を出⽕原因別にみますと、次表のとおりです。 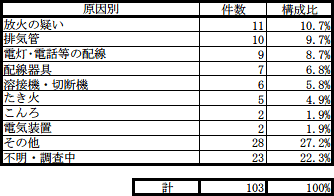 |
| (4) ⾞両⽕災 ⾞両⽕災5,330件を出⽕原因別にみますと、 次表のとおりです。 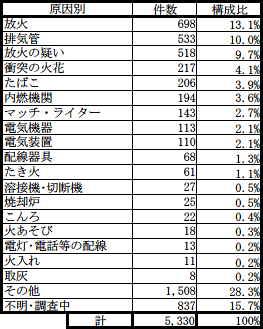
|
(6) 航空機⽕災 航空機⽕災7件を出⽕原因別にみますと、次表のとおりです。 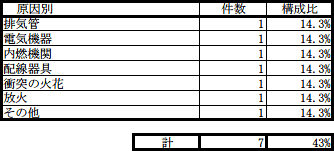 |
| (7) その他⽕災 その他⽕災14,055件を出⽕原因別にみますと、次表のとおりです。 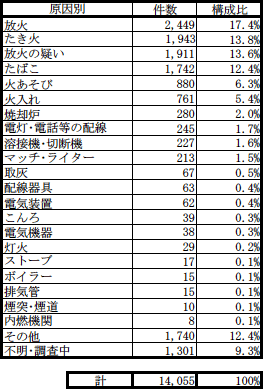 |
4 負傷者の発⽣状況
| (1) ⽕災種別ごとの負傷者発⽣状況 全負傷者6,487⼈について⽕災種別ごとにみますと、次表のとおりです。 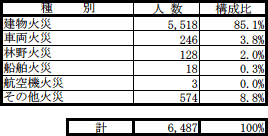 |
(2) 建物⽤途ごとの負傷者発⽣状況 建物⽕災における負傷者5,518⼈を建物⽤途別にみますと、以下のとおりです。 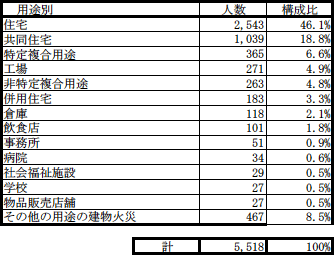
|
5 死者の発⽣状況
| (1) ⽕災種別ごとの死者発⽣状況 死者1,502⼈について⽕災種別ごとにみますと,次表のとおりです。 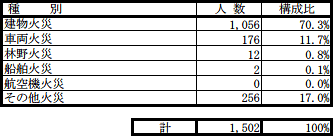 |
(2) 建物⽤途ごとの死者発⽣状況 建物⽕災における死者1,056⼈について⽕災種別ごとにみますと、以下次表のとおりです。 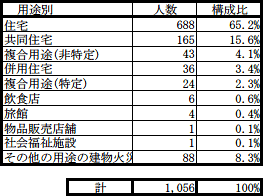 |
| (3) 死者の発⽣した経過ごとの死者発⽣状況 死者1502⼈について、死者の発⽣した経過別にみますと、次表のとおりです。 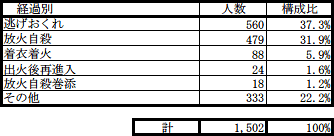 |
(4) 年齢層ごとの死者発⽣状況 死者1,502⼈について、年齢別にみますと、次表のとおりです。 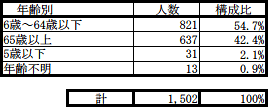 |
(5) 住宅⽕災における死者の発⽣状況
ア 住宅⽕災における経過別死者の発⽣状況
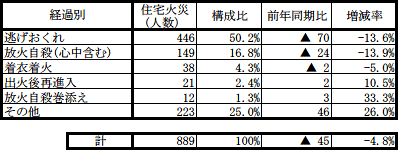
イ 住宅⽕災における年齢別死者の発⽣状況(放⽕⾃殺等を除く)
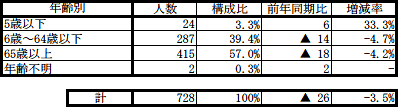
ウ 住宅⽕災における出⽕原因別死者の発⽣状況