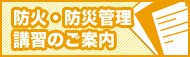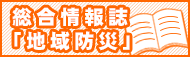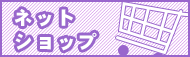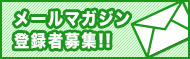早稲⽥⼤学<地域社会と危機管理>研究所所⻑
浦野正樹
⽇本は現在、30年に及ぶ地学的平穏の時代が終焉し、⼤災害が頻発し⾃然の猛威にさらされる地学的不穏の時代に突⼊したといわれる。確かに1990年代に⼊ってから、雲仙普賢岳噴⽕災害(1991年)、北海道南⻄沖地震による奥尻の津波災害(1993年)、阪神・淡路⼤震災(1995年)、有珠⼭噴⽕・三宅島噴⽕(2000年)、東海豪⾬(2000年)など、第⼆次世界⼤戦前後に集中して発⽣した⾃然災害以降、久しくなかった規模の⾃然災害が頻発しており、「歪みの蓄積が既に臨界点に達している」といわれる東海・東南海・南海地震なども間近に迫っている。さらに、地学的には稀有な平穏の時代に進⾏した未曾有の経済的繁栄のツケが、都市の建造空間の変容やヒートアイランド現象などの形となって現れ、異常豪⾬の発⽣など不穏の時代の危機に拍⾞をかけている。
2004年は、国内では、台風禍等による度重なる豪⾬災害、そして新潟中越地震、そして海外ではとてつもない規模で被害が拡⼤しつつあるインド洋津波災害など、衝撃的な⾃然の破壊⼒に⾒舞われ、過疎地や発展途上地域の存亡を鋭く問う災害が相次いだ年として⻑く語り継がれることになろう。そして迎える2005年は阪神・淡路⼤震災から10年の節目の年である。
⾃主防災の原点は、「災害を知り、地域を知り、知識を⽣かす」ことである。
「災害を知る」とは、過去の災害経験を学び教訓を蓄積させていくこと、災害が襲ってくるメカニズムと危険の現出する様相を<よりリアル>に把握することである。「地域を知る」とは、過去の災害履歴や⼟地利⽤の特徴を掘り起こしたり、現状での地域社会の特徴や現在進⾏中の地域の変化が及ぼす影響を多⾯的に検討したり、地域の未来像を充分話し合い意思疎通を図ったりすることを通じて、地域の(災害)脆弱性やポテンシャルをよく⾒極めるとともに、地域で活⽤しうる⼈材や資源を発掘し確認しあっていくことである。そして、「知識を⽣かす」とは、地域の⽂脈にそくして災害時の体験や知識を解読し、地域の探索・再発⾒を進めつつ、それを実践的なかたちで⽣かせるようなしくみをつくり、地域の内外の⼈材や資源をネットワーク化する試みということになる。
災害を限りなく実体験に近い形でリアルに想像しうる⼒、・・・・その想像の世界に⾝を投じることによって⾒えてくるさまざまな危険性や可能性の発⾒と可視化、・・・・その危険性や可能性を予測しそれに対抗できるコミュニティの⼒を強化すること、これが⾃主防災の実践なのである。
近年、インターネットの普及に対応して各機関・団体ではホームページやデータベース機能などの充実をめざして情報提供のしかたを開発してきており、とくにここ数年、防災関連情報の提供⼿法、情報の検索・整理・利⽤のためのツールは格段に進歩しつつある。これらの中には、災害を限りなく実体験に近い形で描き、災害への対処⽅法をコンパクトに提供しようとする試みもみられる。これらの情報(及び情報ツール)をいかに市⺠レベルで使える道具にしていくか︖このメールマガジンも、そうした試みのひとつで、アップ・ツー・デートな情報提供と地域同⼠の活発な交流を促進することが主なねらいである。また、これを機にインターネットやこうしたメールマガジン等を通して得た災害・防災情報、福祉や安全・安⼼のまちづくりに関する情報を、幅広く地域で共有し、充実した地域活動を展開していただくよう願っている。