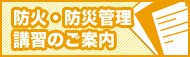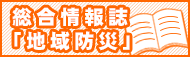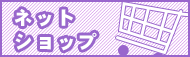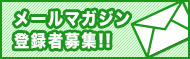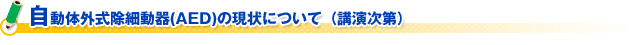
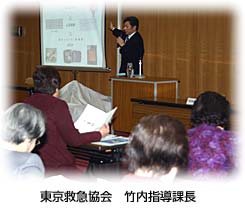 ⾼円宮さまが47歳でお亡くなりになられた時、救急隊到着
時は⼼肺停⽌状態だったそうです。2回の電気ショックとCPR
を実施しましたが、残念ながら10時52分に死亡が確認されま
した。死因は室細動でした。この時、そばにAEDがあれば、も
しかしたら助かったかもしれません。
⾼円宮さまが47歳でお亡くなりになられた時、救急隊到着
時は⼼肺停⽌状態だったそうです。2回の電気ショックとCPR
を実施しましたが、残念ながら10時52分に死亡が確認されま
した。死因は室細動でした。この時、そばにAEDがあれば、も
しかしたら助かったかもしれません。
AEDについてご説明しますと、⾼円宮さまのような⼼臓突然
死の多くの原因は⼼室細動と云われています。この⼼室細動な
んですが、まず正常⼼電図というのは⼀定に波うつような波動
となりますが、⼼室細動の場合、無秩序状態です。⼼臓がぶる
ぶる震えている様な状態でポンプとしての機能を果たしており
ません。⾎液も充分全⾝に送り出せないような状態です。こう
いった状態を⼼室細動といいます。
この⼼室細動の唯⼀の特効薬ともいえるのが、AEDなのです。AEDとは、⼼臓に電気ショックを与
えて正常な状態に戻す装置を除細動器といいます。なぜ除細動かといいますと、⼼室細動の細動を取
り除くから除細動ということです。電気ショック=除細動と受けとめてくださって結構です。
この除細動器を⼩型で操作を簡単にした機器をAutomated External Defibrillator(⾃動体外式除細
動器)の頭⽂字を取ってAEDといいます。AEDですが、⽇本で薬事法上、承認されているものが三種
あります。非常に⼩型で操作が簡単なのが特徴です。中にはコンピュータを内臓しておりまして、⼼
電図を⾃動的に解析していきます。先程お話しした⼼室細動の波形を読んで、この⽅は電気ショック
が必要だとメッセージで知らせます。つまり、除細動(電気ショック)の必要の有無は機械が判断す
るということです。
以前は、この除細動器は医師、看護師、救急救命⼠のみしか使⽤が許されておりませんでしたが、
平成16年7⽉1⽇より⼀般の⽅でも使⽤できるようになりました。
その背景についてお話ししますと、非医療従事者によるAEDの使⽤についてということになりま
す。この非医療従事者とは⼀般の⽅にあたります。まず、非医療従事者によるAEDの使⽤のあり⽅検
討会を厚⽣省で設置し、7⽉1⽇厚⽣省医政局⻑より「非医療従事者によるAEDの使⽤について」⽰さ
れました。
その内容についてですが、医師法17条において、医師でない者が医療⾏為を⾏ってはならないとい
う条⽂があります。つまり、医師でない者が反復継続する意思を持って⾏えば医師法17条違反となる
というものですが、⼀定頻度で⼼停⽌者に応急の対応をすることが期待・想定されている者、これは
ようするに反復継続性のある⼈、何回もAEDを使うような⼈、⼀定頻度者と呼んでいますが、この⼀
定頻度者以外は反復継続性が認められないので医師法17条の違反ではないと書かれています。
では、⼀定頻度者は使えないのかということですが、⼀定頻度者は4条件を満たせば医師法17条違
反にはならないとも書かれています。その4条件については次に出てきますが、⼀定頻度者というのを
細かく説明させてもらいますと、例えば、警備業務や警察官など職種で明確には出されていません。
非常に抽象的な解釈なのです。
では、どういうのが⼀定頻度者かというと、例えば警備業務、警備員さんの事業主がうちは⼀定頻
度者だといえば⼀定頻度者なのですね。ようするに⾃⼰申告制のようなところがあるのです。非常に
分かりにくくはありますが、⼀定頻度者とは反復継続性があるような⼈と理解していただいて結構で
す。
⼀定頻度者は4条件を満たせば医師法17条違反にならない、その4条件とは何かということですが、
1は医師等(医療従事者)を探す努⼒をしても⾒つからない等、医師等による速やかな対応を得るこ
とが困難な場合、2は使⽤者が、対象者の意識、呼吸がないことを確認していること、3は使⽤者
が、AED使⽤に必要な講習を受けていること、4は使⽤されるAEDが医療⽤具として薬事法上の承認
を受けていること、この4つの条件を満たせばAEDを使っても医師法17条違反にはならないというこ
とです。
この資格をもらって何になると思われた⽅もいらっしゃると思いますが、これからはAEDを使う
にあたって、4条件のひとつに講習を受ける事が含まれているため、ある意味、⼀般的に禁⽌されてい
ることをそれを受けることによって許可されるのですから免許証のようなものですね。そういったこ
とで法的な条件をクリアするために必要な講習ですので、今後は重きのあるものになるかと思われま
す。
⼀定頻度者以外でも安全を確保するため受講が推奨されています。また、実際に講習を指導するの
はどんな⽅かといえば、有資格者(医師、看護師、救命⼠)という⽅々になっています。
⼀定頻度者に対する講習に関してですが、8⽉16⽇厚⽣省医政局指導課⻑より「AEDの講習内容の
取りまとめについて」というのが出されました。これは、⼀定頻度者に対する講習は220分で⾏う旨
が書かれています。細かな内容についてですが、イントロダクション、これはAEDの必要性・重要性
について15分、CPR(⼼肺蘇⽣法)の実技が50分、AED使⽤⽅法の実技が80分、知識確認(筆記)
と実技評価(実技)に60分となっています。この試験ですが、8割以上の点をとることが基準とされ
ています。つまり、80点とらなければならないということです。講師養成のためのAED講習は360分
で⾏っています。やはり、教える⼈なのでもう少し詳しい内容となっています。
続いて、総務省の動きはどうなっているかというと、平成16年12⽉24⽇「応急⼿当普及啓発推進
検討会」報告書が出ております。その報告書に基づいて、「応急⼿当の普及啓発活動の推進に関する
実施要項」というのがあるのですが、普通救命講習、上級救命講習などの根本なるものは実施要項な
んですね。これがAEDが⼊ったため、改正となったということです。
では、どのようなことが改正となったかというと、普通救命講習、上級救命講習プログラムの検
討、応急⼿当指導員、応急⼿当普及員講習プログラムの検討、応急⼿当指導者標準テキスト(追補
版)の作成、この内容をうけて、東京消防庁、東京救急協会では平成17年1⽉21⽇から救命講習に
AEDの内容を追加したものを⾏っています。
その内容についてですが、普通救命講習Ⅰの今までの3時間の講習では、応急⼿当の重要性、応急⼿
当の対象者と必要性、救命に必要な応急⼿当の項目をおこなってきました。新しい講習ではAEDの使
⽤法、効果判定が加わりました。続いて普通救命講習Ⅱですが、先程お話しした⼀定頻度者の講習で
す。⼀定頻度者は先程の普通救命講習Ⅰに加えて筆記試験と実技試験が⼊ります。これで8割以上の点
を取ることになっています。これらを240分、約4時間で⾏います。ですから反復継続性のあるような
⼈、⼀定頻度者と思えるような⼈はこちらの講習を受けなければならないということです。
上級救命講習はどうなっていくかというと、今までのプログラムに⼀定頻度者講習が⼊ってくる形
になります。⼤枠の8時間は変わりません。ですから、上級救命講習も受けた⽅は⼀定頻度者ともいえ
るわけです。
では、普通・上級救命講習を既に持っている⽅はどうするかというと、AEDの使⽤⽅法80分とAED
に関する知識、実技の確認(筆記・実技試験)60分の140分を受けて8割以上の点をとれれば良いと
いうことになっています。そういう講習を⾏っているかですが、東京救急協会では再講習として140
分受けていただいています。ただ、⼀定頻度者講習(240分)を受けた⽅が望ましいといわれていま
す。ですから、都内で再講習を受けた⽅は皆、⼀定頻度者になるわけです。
講師となる場合、普及員講習Ⅰ(24時間)を受けられた⽅は5時間の講習を受ける形になります。
AEDの知識、シナリオに対応したAED使⽤法、AED指導法、知識確認・実技評価の4点の講習を実施
する、もしくは普及員再講習(3時間)を利⽤し上記4点を併せ5時間の講習を実施することになりま
す。
そして、救急⾞到着までの平均時間が全国平均約6分ですが、⼼肺停⽌者を蘇⽣するチャンスは1分
毎に7〜10%づつ減少します。通常、119番通報が指令センターにかかり、消防署に出場指令が出
て、現場に到着する、そして除細動まで10分以上かかることになってしまいます。このことからも早
期除細動が重要となってきます。
救命の連鎖(チェーン・オブ・サバイバル)が⼤切ということです。早期アクセス、早期CPR、早
期除細動、早期ACLSが救命の連鎖です。これが早くつながってこそ、救命につながっていくことにな
るのです。
そして、AEDの設置場所についてですが、イベントホール、スポーツ施設、空港、駅、デパート、
ホテル等の多くの⼈が集まる場所の設置が望まれます。
AED使⽤による救命例ですが、オーストラリアのカンタス空港では65ヶ⽉で46⼈の⼼肺停⽌患者に
対してAEDを使⽤しました。機内で27⼈中6⼈、空港内で19⼈中17⼈が⼼室細動により除細動を実施
し、除細動を実施した23⼈中6⼈(26%)が救命されました。救命率3〜4%程になると思います。そ
う考えると、非常に⾼い率で救命されているということです。どれだけ除細動が効果があったのかと
いうことが理解できると思います。
続いて、シカゴのオヘア空港ではAEDが53台設置してあり、空港内では1分〜1分半で取りにいける
距離にあるそうです。1999年〜2001年の21⼈の⼼肺停⽌患者が発⽣し、そのうち18⼈が⼼室細動で
除細動を実施したのですが、11⼈(61%)の⼈が助かりました。61%の⼈が助かっているというの
は驚異的な数字だと思います。11⼈のうち9⼈は5分以内、2⼈は7分以内に除細動を実施しているそ
うです。8⼈は病院に着く前に意識がもどっているという状況です。
これにより、非常に除細動の効果があるということが理解できるかと思います。⽇本でもAEDを普
及して⾄る所に消⽕器のように置いてあれば、それを使って救命するということで救命率がどんどん
⾼くなるかと思われます。これから、皆さんにも普及していっていただければと思います。
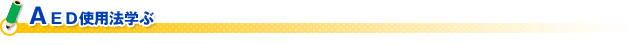
 飯舘村婦⼈消防隊役員総会が4⽉14⽇(⽊)、 飯舘村公⺠館に
おいて開かれ、応急⼿当普及講習会の開催など、今年度の事業
計画を決定しました。約30名が出席し、⾼橋美佐⼦隊⻑、⼤
越憲⼀原町消防署飯舘分署⻑があいさつし、来賓の管野典雄村
⻑、松原茂消防団⻑が祝辞を述べました。
飯舘村婦⼈消防隊役員総会が4⽉14⽇(⽊)、 飯舘村公⺠館に
おいて開かれ、応急⼿当普及講習会の開催など、今年度の事業
計画を決定しました。約30名が出席し、⾼橋美佐⼦隊⻑、⼤
越憲⼀原町消防署飯舘分署⻑があいさつし、来賓の管野典雄村
⻑、松原茂消防団⻑が祝辞を述べました。
総会と同時に、昨年から⼀般にも認められた体外式⾃動除細
動器(AED)の使⽤法を学ぶ講習会が⾏われました。(財)⽇
本防⽕協会がこのほど村婦⼈消防隊に寄贈したAEDトレー
ナーを使い、飯舘分署員が実演指導し、参加者はAEDの安全
な使い⽅などを学びました。
今後は婦⼈消防隊の普通救命講習会のみならず、多くの村⺠への講習会に活⽤させていただき、A
EDが各種施設に設置され、「いざ」という時に使⽤できるようになりたいと考えています。