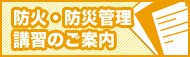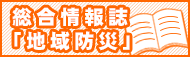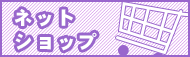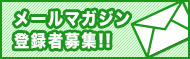1 地震火災の原因
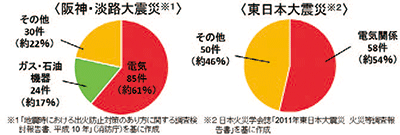
阪神淡路大震災や東日本大震災では、電気が原因で発生した火災が過半を占めています。
近年の大規模地震においては、電気に起因する火災が多く見られるところです。
2 地震火災を防ぐための対策
地震火災を防ぐための主な出火防止対策について、地震前後の流れに沿って紹介します。
① 事前の対策(日頃の備え)
- 感震ブレーカーを設置すること
- 住まいの耐震性を確保すること
- 家具等の転倒防止対策(固定)を行うこと
- ストーブ等の暖房機器の周辺は整理整頓し、可燃物を近くに置かないこと
- 安全装置の付いた製品等を使用すること
② 停電時・避難時の対策(地震直後の対応)
- 停電中は家電製品のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと
- 停電中に自宅から離れる(避難する)際は、ブレーカーを落とすこと
③ 停電からの復旧(再通電)時の対策
- 家電製品、配線やコードに破損・損傷はないか、燃えやすいものが近くにないかなどの安全を確認してから家電製品を使用すること
- 壁内配線の損傷や家電製品の故障等により、再通電後、しばらく経ってから火災になることがあるため、再通電後は余震に注意しつつ、家の中に留まり、煙の発生や異臭などの異常を発見した際は、直ちにブレーカーを落とし、消防機関に連絡すること
また、その他の対策(火災の早期覚知、初期消火)として以下のものがあります。
- 住宅用火災警報器を設置すること
- 住宅向けの消火器・消火用具(エアゾール式簡易消火具)を設置すること
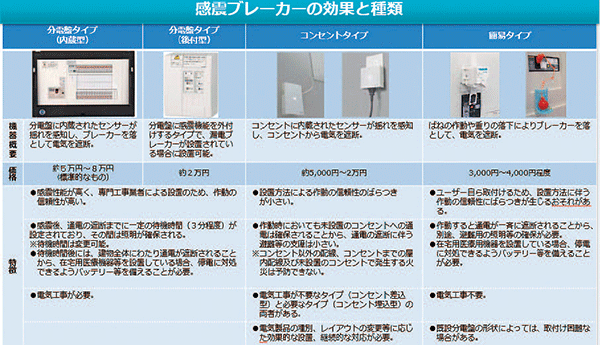
3 感震ブレーカーの普及推進
令和6年能登半島地震においては、石川県輪島市で大規模な火災が発生しました。(地震の影響により特定には至りませんでしたが、電気に起因した火災である可能性があります。)本火災を受け、「輪島市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書」がまとめられ、大規模地震時の電気火災対策として感震ブレーカーの普及推進が必要であるとの提言がなされました。
また、災害対策基本法に基づく防災基本計画(令和6年6月28日修正)においては、 第3編の地震災害対策編の中で感震ブレーカーの普及が位置づけられました。
これらを踏まえ、消防庁では、「住宅用火災警報器・感震ブレーカー設置・維持管理対策会議」等を開催し、都道府県及び市区町村において感震ブレーカーの普及に向けた具体的な計画の策定を行う際の留意事項及び計画(例)をとりまとめ、各都道府県及び市区町村に通知しています。
① 感震ブレーカーとは
感震ブレーカーは、地震の揺れを感知して自動的に電気を止める装置です。
倒れた家具が電気コードを傷つけてショートした場合も、ブレーカーが遮断されれば火災を防ぐことが出来ます。
感震ブレーカーには、分電盤タイプやコンセントタイプ、簡易タイプがありますので、ご自身の環境にあった物を設置しましょう。
② 感震ブレーカー普及に向けた消防庁の取組
消防庁では、感震ブレーカーの普及に向け、広報用のパンフレットや、動画を作成しています。
また、地方公共団体が行う感震ブレーカーの普及啓発に要する経費については、特別交付税措置の対象であることを通知しています。
さらに、国土強靭化実施中期計画において、著しく危険な密集市街地を有する、全国15市区における感震ブレーカーの設置推進に係る事項が盛り込まれたことを踏まえ、消防庁では、これらの自治体の取組みを支援するため、令和8年度予算において概算要求を行っています。

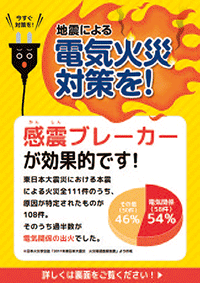
4 まとめ
阪神・淡路大震災における初期消火の実施率は全体の約半数、そのうち初期消火に成功したのは約4割となっています。初期消火の方法別に見ると、消火器による初期消火が最も成功率が高く、成功率は5割となっています。もし仮に、消火器により初期消火が100%実施された場合、単純計算で出火件数は半減し、被害を大幅に減少させることができます。
内閣府の試算によると、南海トラフ巨大地震による火災死者数は、現時点で21,000人と想定されますが、感震ブレーカーの設置を促進することで、約52%減の約10,000人に大きく減少するものと推計されています。
地震時の火災を防ぐためには、こうした対策について日頃から備えておくことが重要です。
(総務省消防庁「消防の動き」2025年10月号より