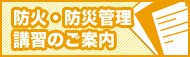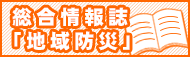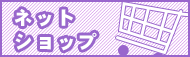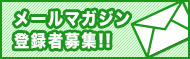1 調査の概要
消防庁では、消防法により設置が義務付けられている住宅用火災警報器(以下「住警器」という。)の設置率等について、令和7年6月1日時点の調査結果をとりまとめました。
設置率 84.5%
(令和6年6月1日時点 84.5%)
条例適合率 65.8%
(令和6年6月1日時点 66.2%)
- ※ 「設置率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一箇所以上設置されている世帯(自動火災報知設備等の設置により住警器の設置が免除される世帯を含む。)の全世帯に占める割合です。
- ※ 「条例適合率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分全てに住警器が設置されている世帯(同上)の全世帯に占める割合です。
2 都道府県別に見る住警器の設置率等
都道府県別に見ると、福井県の設置率(94.0%)と条例適合率(83.8%)が最も高く、一方で、沖縄県の設置率(65.4%)と高知県の条例適合率(41.0%)が最も低くなっています(表参照)。
3 傾向と今後の取組み
我が国における住宅火災件数及び住宅火災による死者数は、新築住宅に対する住警器の設置義務化がスタートした平成18年以降、おおむね減少傾向にあり、住警器の普及促進を始めとした住宅防火対策に一定の効果が現れていると考えられます(グラフ参照)。
住警器の設置状況については、全国平均値で約8割、条例適合率が7割弱となっている一方、設置率や条例適合率が非常に低い地域も見られます。住宅火災による被害が拡大しやすい高齢者世帯をはじめとした未設置世帯等に住警器が設置されるよう、消防庁においても、消防機関に限らず、関係行政機関、関係団体、関係業界等、あらゆる団体と連携した取組みを進めているところです。
また、住警器の維持管理にあたっては、平成23年6月にすべての住宅に住警器の設置が義務化され、令和3年6月に設置から10年を経過したことから、今後、電池切れや電子部品の劣化等による故障が増えるものと予測されます。本調査とあわせて実施した住警器の維持管理状況調査では、作動確認を行ったうちの3.5%の世帯で住警器の電池切れや故障が確認されました。火災時に住警器が適切に作動するよう、定期的に点検を行うとともに、異常がみられた際には本体の交換等を行っていただく必要があります。
このような状況を踏まえ、令和2年度に改正された「住宅用火災警報器設置・維持管理対策基本方針」においては、従来からの設置に対する取組みに加え、住警器の維持管理(点検・交換)に関する広報の推進及び消防機関における住警器の維持管理に関する支援対策の構築が盛り込まれています。
なお、本体交換の際には、各世帯の住宅の構造や世帯構成に応じて、火災にいち早く気づくことができる連動型住警器、ガス漏れや一酸化炭素の発生など火災以外の異常を感知して警報する機能を併せ持つ住警器、音や光を発する補助警報装置を併設した住警器など、付加的な機能も併せ持つ機器などへの交換を推奨しています。
【表】都道府県別設置率及び条例適合率(令和7年6月1日時点)
(標本調査のため、各数値は一定の誤差を含んでいます。)
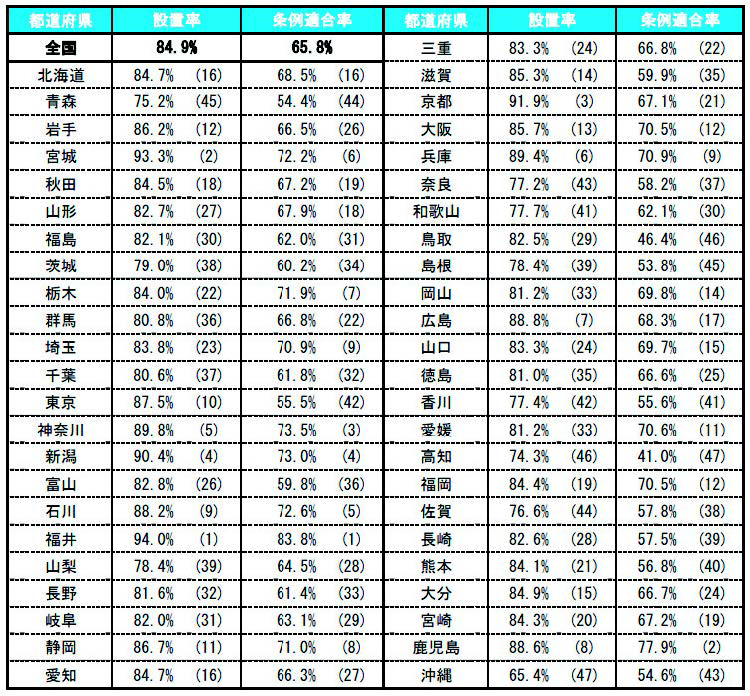
【グラフ】住宅用火災警報器の普及と住宅火災の状況

(総務省消防庁「消防の動き」2025年10月号より