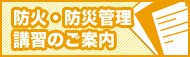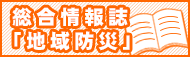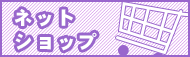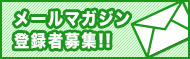和歌⼭県吉備町の救急講習会
「救急の⽇」(9⽉9⽇)及び「救急医療週間」(9⽉8⽇〜9⽉14⽇)は、救急医療及び救急業務に対する国⺠の正しい理解と認識を深め、かつ、救急医療関係者の意識の⾼揚を図るため、昭和57年から例年実施されているもので、本年も全国の消防機関及び医療機関を中⼼に実施されました。
私たちは、いつどこで、突然の怪我や病気に襲われるか予測がつきません。このような時、病院に⾏くまでに、家庭や職場で出来る⼿当を「応急⼿当」といいます。また、脳卒中のように意識がなくなって、呼吸が出来なくなり、ついには⼼臓が⽌まってしまうものや、プールで溺れたり、喉にお餅を詰まらせたりして、呼吸が出来なくなって⼼臓が⽌まってしまうもの、⼼筋梗塞や不整脈で⼼臓が、突然⽌まってしまうものなど、救急⾞が来るまでに何らかの処置をしないと命は助かりません。
カーラーの救命曲線によると、⼼臓停⽌後約3分で50%死亡、呼吸停⽌後約10分で50%死亡、多量出⾎後約30分で50%死亡となっています。いかに救急⾞が来てくれるまでに「応急⼿当」が⼤切であるか分かると思います。
当協会では、財団法⼈救急振興財団からの受託事業により、全国の婦⼈防⽕クラブ員を対象として、「婦⼈防⽕クラブ員救急講習会」を全国20地区(平成14度)のモデル地域で実施しており、来年度においても同事業を⾏っていくこととしています。