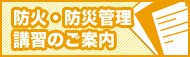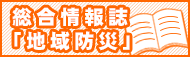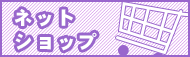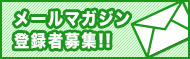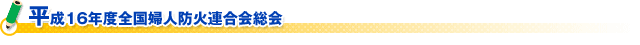
2⽉23⽇の第5回応急⼿当普及啓発推進会議において、⽇本放送協会解説委員⼭﨑登⽒により、講演
「最近の災害取材の現場から」が⾏われました。スライドでの説明と共に、新潟・福井の豪⾬災害や
新潟県中越地震から学んだ⾼齢者対策や、各地の取り組みなどが紹介されました。
24⽇に⾏われた全国婦⼈防⽕連合会総会では、下河内司総務省消防庁防災課⻑による「最近の消防
情勢について」の講演も⾏われ、ご参加の皆様に⼤変好評をいただきました。
この2つの講演で使われた資料とともに「最近の災害取材の現場から」の講演次第を掲載します。
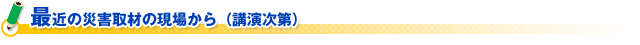
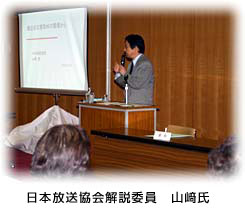 どうもこんにちは、NHKで解説委員をしております⼭﨑と申します。各地⽅の名⼠の皆さんの目の前で私の話を聞いていただけるということで、今⽇は⼤変有り難いと思ってやって参
りました。
どうもこんにちは、NHKで解説委員をしております⼭﨑と申します。各地⽅の名⼠の皆さんの目の前で私の話を聞いていただけるということで、今⽇は⼤変有り難いと思ってやって参
りました。
⾃⼰紹介をかねて、普段私が何をやっているかというあたりからお話をさせていただきます。私はNHKで解説委員という仕事をしております。解説委員という仕事にはいくつかの担当がありまして、私の担当は⾃然災害と防災です。どういうことをするかというと、例えば地震が起きたり、⽕⼭が噴⽕した、あるいは去年は⼤変多く台風がきましたが⼤⾬が降った、⽔害が起きた、⼟砂崩れが起きた、それから⼤きな⽕事も災害になりますのでそのような事があるとすぐに現場に出かけていき、どうしてこんなに⼤きな被害が起きて
しまったんだろう、過去の災害と⽐べて今回の災害で何か特徴はあるんだろうか、過去の教訓はちゃ
んといきたのだろうか、もし伝えるべき今回の災害の教訓があるとしたらそれは⼀体何だろうか、と
いうような事を消防の⽅や、河川の場合ですと河川の管理をしている⽅、⾃治体の⽅、地元の研究を
している⼤学の先⽣、地元の消防団の皆さん、そのご近所の皆さんなど、いろんな⽅にお話を伺っ
て、取材をして喋るに⾜る何事かをテレビで伝えるという仕事をしております。
よくこういう仕事をしていますと、「⼭﨑さん、昔から地震や⽕⼭、⽔害など勉強して得意だった
のですか︖」と聞かれますがそんな事はないです。私がNHKに⼊ったのは昭和51年で、社会部の所
属になりました。皆さんもご存じかと思いますが、新聞社も放送局もニュースを取材するところはい
くつかの部局に分かれています。部局には、政治部・経済部・国際部・スポーツ部・科学⽂化部、そ
れから、社会部があります。政治・経済・国際・スポーツ・科学⽂化の範疇に⼊らない森羅万象がす
べて社会部の範疇になります。社会部は、俗に事件記者と呼ばれました。事件は、⼤事な社会部の取
材ターゲットです。例えば、教育問題・司法の問題・ごみ問題・環境問題もすべて社会部のターゲッ
トです。
私が社会部に所属した時、デスクに「⼭﨑君、君は社会部に所属したが、これから何を取材したい
のか」と聞かれ、全国のどこでもできるテーマである気象と災害に決めました。まず⼿始めに、気象
庁の取材で気象庁へ⾏きました。私は⽂系の⼈間でしたので、最初は⼤変つらかったです。天気の
ニュースを書いたり、台風や⾬量の取材をするには天気図くらいは読めなければ話にならないので
す。⽕⼭や地震の取材をするには、地学のプレートテクトニクスが多少分かってないと気象庁や地震
学者の⽅と話が通じないんです。そのうちに実際に災害が起こりますが、実際に災害が起こった時に
動くのは役所はどこかというと、消防庁なんですね。
気象庁は理科の範疇ですが、消防庁はどちらかというと社会の範疇です。災害というのは、理科と
社会がくっついた時に災害になるんです。今⽇は風が強かったです、だけでは災害にはならない。そ
の風でどこかの看板が落ち、⼈が怪我をした時に災害になるのです。その時は気象庁だけでなく消防
庁も必要になる。私は取材していて、なるほどと思いました。理科ばかり勉強しなくても、社会が分
かる程度に理科をやればいいんじゃないかと思うようになって、これは⾃分でもできるかもしれない
と思ってから20年近くが経ちました。
去年は7⽉に新潟と福井で豪⾬⽔害がありました。10⽉になって台風が上陸しました。兵庫の豊岡
では、⽔害の後遺症の対策が続いている中で新潟県の中越地震が起きました。中越地震は阪神⼤震災
以降、もっとも⼤きな地震災害になりました。これで終わりかと思いきや、年末にスマトラ島沖の巨
⼤地震が起こりました。これは万という単位の⽅がお亡くなりになりました。
今年になって、阪神淡路⼤震災から10年ということで、被災地の神⼾で国連の防災会議が開かれ、
その時も世界の巨⼤地震・津波による被害をどのように減らしていくかが⼤きなテーマになりまし
た。
去年、取材したそれぞれの災害の中から、今後のために考えておかなければならないいくつかの事
を断⽚的になりますがお話させていただこうと思います。
新潟・福井の豪⾬は亡くなった⽅の⼤半が65歳以上の⾼齢者でした。新潟・福井・福島でも21⼈の
⽅が亡くなりました。このうち、17⼈の⽅が65歳以上の⾼齢者でした。中にはおじいさんとおばあさ
んの2⼈暮らしで、寝たきりのおじいさんを何とか2階に持ち上げようとしているうちに⽔が浸⽔して
おじいさんが亡くなってしまうとか、悲惨な犠牲者も含まれていました。
最近、こういう豪⾬災害が多いですね。1時間に50mmとか80mmの⾬が降るんです。50mmを超
えたら⾞のワイパーを強くしても向こうが⾒えにくい。100mmになると、傘をさしていてもびしょ
ぬれで隣の⼈の話も聞けません。その位の⾬です。そんな⾬が頻繁に降るんです。新潟・福井の時も
そのような⾬が続き、堤防が決壊して被害になりました。
⾼齢者の問題は、これからよほど考えなくてはならないと思っていた⽮先、新潟県の中越地震が起
きました。新潟県中越地震のひとつの側⾯をお話しすると、⾼齢化が進んだ地域をおそった地震でし
た。
今、全国の⾼齢化率は平均19.5%です。ほぼ平均値だったのは⻑岡市だけです。⼗⽇町市は26%、
⼩千⾕市は25%、川⼝町は27%、2,000⼈のすべての住⺠が⻑岡市などに避難した⼭古志村に⾄って
は40%になります。倍です、10⼈の⼈がいると4⼈は65歳以上の⾼齢者ということになります。
この2つの災害から、私達は何を読み取らなくてはならないかというと、それは⽇本がこれから⾼齢
化社会に向かっていくと、こういう災害が増えてくるんじゃないかと考えなくてはいけないというこ
とです。そうすると、その⾼齢者の対策を⼀体どうするのかというのは災害にとって、それから⽇本
の国にとって⼤変⼤きな課題だということになります。
阪神淡路⼤震災の時に、⾼齢化対策が⼤変⼤きな問題になりました。例えば、被害を受けた被害者
はまず避難所に⼊ります。そこに⼊った後は仮設住宅で暮らします。そこに暮らしている間に⾃⼒で
家を建て直せる⼈はいいんですが、そうでない⼈は公営住宅、これは復興住宅ともいわれる団地みた
いなものですが、そこに住むんですね。
阪神淡路⼤震災の時にどういう事が起こったかといいますと、例えば、被災した⼈がいたとして、
その⽅は近くの体育館に避難します。神⼾市は市の真ん中はなるべく早く復興したいということで、
仮設住宅を郊外の空き地に作りました。そうすると体育館から仮設住宅に移動する時に、その地区に
住んでいた⼈が遠くの郊外の仮設住宅に⼊らなくてはならない事になります。しかも、⾼齢者から順
番に⼊居させましたから、あちらこちらの⾼齢者ばかりになる。⼀⼈暮らしの⾼齢者や⾼齢者世帯と
いうのは、その地区に30年40年50年暮らしてきた⼈ばかりです。地域の⼈達とのつながりや、世間
話をしたりするのが楽しみのひとつです。そういう⼈達がばらばらに仮設住宅に⼊りました。⾃⼒で
家を建てられるのは若い⽅が多いですから、⾼齢者の⽅は今度はまた、公営住宅に⼊らなくてはなら
ない。そして、その埋め⽴て地に建てた団地にまた⾼齢者をこっちからこっちという感じで移動させ
たんですね。せっかく仮設住宅で仲良くなってコミュニティができていたのに、それを全部断ち切っ
て⼊居者を連れてきたのです。⾼齢の皆さんが何⼗年も住んでいた地区のコミュニティや⼈のつなが
りを断ち切られて、仮設住宅でようやくできたつながりをまた断ち切られて、新しい団地へ来て、し
かも今度は⻑屋ではなく、コンクリート造りの5階建て・7階建てで⽩い壁・⽩い天井・鉄の扉です。
⾼齢者の⽅で⾜腰が弱って階段などで⾏き来ができないため、もう1度近くの⼈とつながりを作り、団
地の中で引きこもってしまう⽅が多くできました。この象徴的な出来事が孤独死といわれたもので
す。阪神淡路⼤震災で、その問題が未だにクリアされていない地域は非常に多いです。
⾼齢者の問題は、阪神淡路⼤震災の時も⼤きな教訓でした。今回新潟県中越地震の後、⼭古志村は
どんな取り組みをしたのか︖⼭古志村は仮設住宅や避難所に⼊る時、⼭古志村の14の地区の⼈達が必
ずまとまって同じ地区の仮設住宅に⼊れるように取り組みました。
それから、阪神淡路⼤震災や三宅島の避難の時には家のサイズを優先しました。例えば三宅島にも
⼆世帯・三世帯で暮らしていた⼈達がいます。団地は2DKくらいですから3世帯で⼀緒に暮らすこ
とは無理です。ですから、⽴川の団地におじいさんとおばあさん、多摩の団地に息⼦夫婦というよう
な避難になった。これはいけないということで、⼭古志村では今まで作ったことのないような⼤きな
仮設住宅を作って家族の単位を壊さないようにしました。しかも、集会所や村の診療所を仮設住宅の
中に作りました。村の床屋をやっていた⼈は⾃分の仮設住宅の⼀間を使って床屋を始めたり、まるで
仮設住宅を元の村のような所にしたんです。これは、阪神淡路⼤震災の教訓が活きたのです。
⼭古志村の⾼齢化率は40%といいましたが、これは昔からの数字です。その⼭古志村の⼈達は、⾼
齢者を地区の⼈がまとまって暮らし、家族が⾒守り、村全体で⾒守ることによって対応してきたんで
す。つまり、⾼齢者の問題というのは災害があった時に動き出したのではだめだという事です。普
段、どういう風に地域が⾼齢者の問題を考えているかがいざという時に活きるということなんです。
そういう取り組みをやっているところがあるのかを調べてみました。岩⼿県川崎村、ここも⾼齢化
が非常に⾼いところで何度も⽔害にあってきました。この川崎村は、⼀⼈の⾼齢者を家族や近所だけ
に任せるのではなく、みんなで⾒守ろうとなっています。例えば郵便配達の⼈がその家の近くに⾏っ
て声をかけてみる。おかしいなと思ったら、⺠⽣委員に連絡する。⺠⽣委員が⾏って、これはケアが
必要と感じると隣近所の⼈にお願いする。⾏政にも連絡して、⼀⼈の⾼齢者をみんなで⾒守る仕組み
を作っているんですね。これはすばらしい取り組みと伝えたところ、それは⽥舎だからできるんだろ
うと⾔った⽅がいらっしゃいました。では、都会はどうなんだと調べてみました。
東京都江⼾川区に渚団地という所があります。これは典型的な団地でここは⾼齢者の問題、地域の
問題は地域で考えなくてはいけないと、団地の役員会が中⼼に団地に暮らしている⼈全員の防災名簿
を作りました。どの⼈が⼀⼈では逃げられない、どういう⽣活をしている、どういう病気でいつどこ
病院に通っているということが分かるようにしました。本⼈の了解を得て、いざというときに⼀⼈で
は避難できないという⼈の⽞関には要救助者シールを貼り付けました。この家の⼈は救助が必要な⽅
です、と誰でも分かるようにする為、作ったものです。それで年に⼀回防災訓練を⾏う時には、その
救助されなくてはいけない⼈をどうやって誰が救助するかという担当者まで決めて訓練を⾏っていま
す。これは防災と福祉、防災と防犯の連携だと私は思っています。⾼齢者の問題は普段からあって、
災害の時にそれが⼤きく⾒えるのですね。顕在化します。災害の時だけ対応しようとしても無理なん
です。普段からやってるかどうかが⼤事なのです。
阪神淡路⼤震災以降、皆さんの町でもそうですけれども、それぞれの⾃治体や県は地域防災をつく
ることが決まっています。防災や災害が起こった時、各⾃治体や県で⾃分達の地域はこういう取り組
みをします、という計画をたてることが法律で決まっています。そこには必ず災害弱者対策が必ず書
いてあります。書いていない⾃治体はない。しかし、例えば⼀⼈暮らしの⾼齢者だけのお年寄りがど
こに住んでいて、どんな悩みを抱えているかを知らない⾏政にはいざという時の⾼齢者対策はできな
いんです。
地域の問題はなかなか深刻です。去年は消防団にも多く取材させていただきましたが、昭和30年代
くらいは全国に200万⼈位はいた団員が今、全国に93万⼈程です。半分以下です。だから地域の防災
⼒が落ちているとすぐに結びつけては⾔えません。それを補って余りある婦⼈防⽕クラブや地域の⾃
主防災組織の活動等もありますので。
ただやはり、私達が考えなくてはならないと思うのは去年の防災⽩書を⾒ると、全国⽕災原因の
トップは放⽕と放⽕の疑いなのです。これは7年か9年連続でそうなっています。昔、⼤阪市の消防局
が放⽕して捕まった犯⼈にどういう所が放⽕しやすいのかという調査をしたことがあります。⼀ヶ⽉
前の地域の催しのチラシがまだ貼ってある、ゴミを出す⽇が決まっているのに指定されていない⽇に
もゴミが出されている、暗がりが多くて⼈通りが少ない、そんな地域は放⽕しやすいそうです。つま
り、近所付き合いや取り組みがきちんとしていない所は放⽕しやすいという事ですね。最近、路上犯
罪も増えてきています。ひったくりなどの路上犯罪も、昔から⽕の⽤⼼などをまわっている地域では
少ないです。そんな取り組みが⾏われていないところはやはり多かったりします。地域の問題を地域
でどう取り組むかということは、こと防災だけに限らず⼤変⼤きな問題だといえるのではなかろうか
と思っています。
地域の取り組みはどのくらい災害の時に効果があるのかというと、これは阪神淡路⼤震災の時に⽡
礫の中から救出された⼈がだいたい3万5,000⼈ほどいました。その⼈達は誰によって救出されたかと
いうと警察・消防・⾃衛隊で8,000⼈、家族と近所の⼈が救出した2万7,000⼈、これを⾒ると明らか
です。⼤きな災害が起こると警察・消防・⾃衛隊では⼿に負えないんですね。例えば⼈⼝10万⼈ほど
の町で同時多発で7〜8件ほどの⽕災でしたら、地元の消防がなんとかしてくれると思います。ただ、
阪神淡路⼤震災の時は同時多発で数⼗件の⽕災が発⽣しました。消防ではどうにもならないです。⽕
災を10件しか消せない町で30件の⽕災が発⽣しても消防⾞は⾏くことができません。阪神淡路⼤震災
の例を取材すると、近所で消そうとバケツを持ってきて近所のお風呂屋さんから⽔を持ってきて消し
て延焼を⾷い⽌めた、みんなが近くの避難所に集まった時にあそこのおばあさんがいない、もしかし
て埋まっているんじゃないか︖助けにいこう、となった地域はやはり救助された⼈が多かった。それ
がこの結果です。
つまり、阪神淡路⼤震災が教えた最⼤の教訓は、災害は⼤きくなればなるほど防災機関の⼿には負
えなくなるんです。何かあったら消防に助けてもらえばいいというのは、⼩さい災害にしか通⽤しま
せん。阪神淡路⼤震災のような災害が起こったら消防は⾏けないです。
新潟県中越地震の時、90時間以上経ってから男の⼦が救出されたというのがありました。これはあ
れが1ヶ所だったからできたわけです。阪神淡路⼤震災のように120ヶ所もあれば⾏けません。そうい
うことなんですね。それは、やはり私達が⼀⽣懸命考えなくてはいけないことのひとつではないかと
思います。
最近の災害を取材していて思うのは、災害には地域性があるということです。平成12年の3⽉に有
珠⼭が噴⽕し、6⽉に三宅島が噴⽕し、9⽉に名古屋が⽔浸しになり、10⽉に⿃取県中部地震がおこり
ました。
有珠⼭の噴⽕は⼤変驚かされました。有珠⼭噴⽕の前までは、だいたい噴⽕後に警報が出ていまし
た。ところが有珠⼭の場合、初めて噴⽕の前に数⽇中に有珠⼭は噴⽕すると⾒られるという発表をし
たんです。有珠⼭の周りの1万⼈近い⼈達は、噴⽕の前に全員避難しました。噴⽕は、例えば国道で
もおきましたし、⾷べ物の⼯場のすぐ脇でもおきました。ですから、全員が避難していなかったら⼈
的な被害が出たかもしれません。幸い、有珠⼭の噴⽕は、直接の被害として⼈が⼀⼈も亡くなりませ
んでした。これは世界の⽕⼭防災のお⼿本といわれました。どうして、そういう事ができたのかとい
う話ですが理由は⼆つです。⼀つは有珠⼭という⼭は明治以降、だいたい30年〜50年の間隔で噴⽕を
繰り返しておりまして、近代の科学の目でとらえた噴⽕の記録が積み重ねられていた。つまり、科学
的なデータがあったんです。噴⽕の前にはこういう現象が起こる、こうなってくるとこういうステー
ジになる、有珠⼭というのはこういう形で噴⽕する⼭だ、と分かっています。しかも、有珠⼭の麓に
北海道⼤学の⽕⼭研究所があって、有珠⼭のホームドクターのような先⽣がずっと有珠⼭を研究して
た。有珠⼭のことは俺に任せてくれというような⼈がいたんです。つまり、近代的な観測によって有
珠⼭の事がよく分かっていたというのが⼀つ、もう⼀つは何かというと観測技術の勝利なんですね。
GPSというものがありまして、皆さんの分かりやすい⾔葉で⾔えばカーナビです。カーナビついて
る⾞があると思いますがカーナビゲーションというのは地球の周りにいくつも⾶んでいる⼈⼯衛星か
ら出ている電波を地上でとらえて⾃分の位置を決めるんですね。GPSで測りますと、地上のここか
らここまでの距離をミリ単位で測れるんです。だから、こことここが何ミリあって、こっちとこっち
が何センチあるということがGPSでは測れる。⽕⼭というのは地震と違って、例えば噴⽕に⾄まで
にはどういう事がおこるかというと、だいたいマグマがあがってくるんです。何もないところから、
下からマグマがどんどんあがってきます。何もないところへどんどんあがっていきますからどういう
事がおこるかといいますと地⾯を割るんですね。下からマグマがあがってきて地⾯を割る、これが⽕
⼭の周りでおこる地震です。最近の観測技術はとても進歩して、今、⼈体に感じないような地震の震
源も測定することができるようになった。今は、絶対⼈が分からないような地震の震源がどこにある
かが分かるようになってきた。もっとマグマがあがってくると、この前ニュースで出てましたが、浅
間⼭で東側が少し膨らむ分だけ⻄側が少し縮んだりするんです。⼭が要するにセンチ単位で膨らむん
ですね。それをGPSがとらえるんです。⼆点間の距離をミリ単位でとらえます。その⾝体に感じな
い地震の震源も測定していくと、どうも震源が浅くなってきているということが分かる。過去のデー
タをつきあわせてみると、そういうことが起こると⼆⽇くらいで噴⽕してると分り、数⽇以内に噴⽕
するおそれがあると出たんです。では、他の⼭でもやればいいじゃないかと思いますよね。出来ない
んです、どうして出来ないか、富⼠⼭はもう300年噴⽕していないんです。富⼠⼭が噴⽕する前にど
ういう事がおこったかを分かる⼈はもう誰もいないんです。古⽂書を読むしかない。古⽂書にそんな
細かいことは書いていない。だから、富⼠⼭で⻑周期の地震がおきたとか、湯気がでたとかニュース
になりますが、それが噴⽕とどういう関係があるのかと分かる⼈は⽇本中、いや世界中でも誰もいな
い。だから有珠⼭で速報が出来たけれども富⼠⼭では出来るのか、まず出来ないでしょう。だから、
これは有珠⼭だけの出来事なんです。
6⽉に三宅島が活動を始めました。三宅島は2000年9⽉2⽇か4⽇にかけて、3800⼈の住⺠が東京
などに避難しました。今年の2⽉から4年半振りに帰島が始まってます。三宅島の噴⽕にもいくつもの
特徴があるんですけど、ここではひとつだけ避難の特徴をお話しします。三宅島の避難の特徴は何か
というと、普通はさっきお話ししたように被災者がでると、まず最初に避難は体育館みたいな所で⾏
われるんですね。私も体育館へ取材に⾏きました。有珠⼭でも⾏ったし、⿃取県⻄部も新潟県でも⾏
きました。⼀⽇⼆⽇はいいんですよ、みんな仲良くして暮らしてますから。新潟県中越地震なんか、
体育館のスペースはひとりほぼ⼀畳ですよね。そこに⼀週間、⼆週間、⼀ヶ⽉と暮らすわけですね。
若い⼥の⼦はその環境の中で着替えもしなくちゃならない。隣からは2・3⽇は我慢してるけれども3
⽇目くらいになるとお酒を飲む⼈もいて、酔っぱらいもでる、いびきもかく。やっぱりプライバシー
の問題は⼤きいんです。しばらくしていくと、ダンボールで衝⽴をたてて、家族単位で囲ったりして
います。三宅島の噴⽕の際に東京都は⽕⼭の噴⽕は⻑引くと、まあ4年にもなるとは思わなかったで
しょうけれども、地震や⽔害に⽐べて⻑引くという事で最初から体育館には寝かさないようにしよう
という事で都営住宅に避難させたんです。
それはプライバシーの⾯から良かったんですね。ところが、先程阪神淡路⼤震災の所でもお話しま
したように、三宅島の⼈達はひとつの島の中で非常に強い⼈間関係を形成しながら⽣活していまし
た。運命共同体ですよね、同じ島にみんな住んでるんですから。そういうつながりの中で⽣きてきた
⼈達がばらばらの団地に避難することになったんですね。
若い⼈達はいいですが、お年寄りの中には団地の中で孤⽴してしまう⼈が出ました。三宅島の対策
を考えるためには地続きの所で暮らしている⼈達に⽐べて、地域のつながりが強くて運命共同体のよ
うにして地域のコミュニティを作りあげてきた。そういう所でずっと暮らしてきた⼈達なんだという
ことを配慮しなければ⾎の通った防災対策にはならないのです。つまり、三宅島にも三宅島固有の問
題があるんですね。
⿃取県⻄部地震はどういう地震だったかというと、過疎化が進んだ⾼齢化が進んだ地域がやられた
んです。死者は⼀⼈もいませんでした。地盤が強かったのと、昼間だったのと、それから東京のよう
に家が密集していなかった、というようなことが幸いしたと⾒られています。ただ、壊れた家はたく
さんありました。
⽇本の災害対策は道路や橋や病院、公共の建物が壊れたときはものすごく⼿厚いんです。優先で直
されます。ところが、個⼈の財産形成に関わるものには税⾦はつぎ込まれません。ですから、家が壊
れても⾃分の責任でなんとかしなくてはならないんです。
⾼齢者には建て替える余裕がありませんから、⼟地などを⼿放してしまう⼈が多くでたんですね。
つまり、公共の施設が直っても住む⼈がいなくなってしまうんです。
そこで、⿃取県では全国で初めて個⼈の住宅の再建に300万円を出すという決断をします。それに
それぞれの市町村が100万円上乗せします、ということになりました。それによって、⾼齢者がその
⼟地に残りやすいようにしたんですね。残った⽅に話を伺うと、ここで先祖の位牌を守りながら死ん
でいきたいとおっしゃっている⽅がたくさんいらっしゃいました。
これは何を意味するかというと、災害は地域の課題がたくさんあって地域の課題にきめ細かく対応
していくことが重要なのだということなんですね。全国⼀律の法律を作ることももちろん⼤切ですが
国や県や市に任せるだけでなく、地域や個⼈でも取り組んでいく必要があります。そのことについ
て、これからお話します。
新潟県中越地震の時に、消防が搬送した負傷者は216⼈いました。その怪我をした⼈達は何故怪我
をしたかというと、家具の転倒や落下で怪我をしたのが41%、⼈の転倒が25%、⽕傷などが11%、
ガラスなどが8%、家屋の倒壊7%、そのほかが8%という数字になりました。私がかつて取材した釧
路沖地震の時にも、明け⽅の地震で慌てて布団から⾶びだした時に裸⾜で駆け回ったため、ガラスで
⾜の裏を怪我した⼈が沢⼭いました。その時に、家族全員がガラスで怪我をしているなか、⼀⼈だけ
怪我をしていないおばあさんがいました。これは、昔から枕元に懐中電灯を⽤意していたので、地震
の時もガラスが⾶び散っているのが⾒えたのでスリッパを履いて移動できた為だそうです。それで怪
我をしない。家族に⽐べればそのおばあさんがしたことは防災対策ですよね。そんな難しいことでは
ないんだなというのがよく分かりました。
阪神淡路⼤震災で取材して、とても⼤変だったのはトイレです。家が崩壊している⼈は体育館に避
難しますが、それは1畳に1⼈程のスペースです。体育館はトイレは2つか3つしかないのにです。し
かも、断⽔していますから、⼥性やお年寄りはトイレに⾏きたくなるのが嫌だからあまり飲み⾷いし
ないようにしている⼈が沢⼭いました。
被害があまりでていない家に取材に⾏ったとき、断⽔なのにそこはトイレの⽔がバケツにあるんで
すね。どうしたのかと聞くと、おばあさんが風呂の残り湯を必ずとっておいていたという事です。風
呂の⽔があれば家族4⼈の⽣活⽤⽔は3⽇分くらいはもちます。
この話やさっきのおばあさんの懐中電灯の話からも分かるように、そんなに難しいことではないの
です。つまり、防災対策とは新しい事を考えることはなくて、これやった⽅がいいんじゃないかなと
思うことを何でもいいからひとつでもやっておくと、それはその分で助けになるということです。
正しい知識をもって、災害に備えるということはとても⼤切なことです。稲むらの⽕という話があ
ります。
戦時中の⼩学校の教科書に載っていた話です。昔、⼤きな地震がありました。地震があると津波が
くる。そこで、地元の名⼠のおじいさんが村⼈に知らせて逃がすために、稲むらに⽕をつけた。当時
の稲むらは命の次に⼤切なものです。それに⽕がついているということでみんなあわてて消しに⼭を
登っていった。それに津波がきて、みんな助かったという⾔い伝えです。今年の1⽉の国連防災世界会
議でもこの話が注目されました。
それはスマトラ沖地震で何故こんな⼤きな被害が出たかというと、ここはもともと地震が少ない地
域である為、地震と津波が結びつかないわけですね。⽇本は海で⼤きな地震があると津波が起こるか
もしれないと警戒します。⽣きていくためには正しい知識を⾝につけなければならないということで
すね。
例えば、先程災害には地域性があるとお話ししましたが、崖の下に住んでいる⼈は⼤⾬が降ったら
崖くずれが起こるかもしれないと考えなければならない、川沿いに住んでいる⼈は洪⽔になるかもし
れないと思わなければならない。それは、⼦供の時からみんなに教えておかなければならないという
ことです。海辺の⼈には⼤きな地震があれば津波になるかもしれないという事をおしえておかなけれ
ばいけないのです。
今回のスマトラ沖の地震で津波の映像を⾒た⽅はたくさんいらっしゃったと思います。津波と⾼潮や
⾼波は全く違うものです。⾼潮や⾼波はせいぜい海の⽔の表⾯30cm〜1mくらいの⽔が浮いたり沈ん
だりしているんです。津波は海底が動くことによって起こります。海の底から海の上までの海の⽔全
部が動くんですね。津波はきたときは40分くらいきっぱなしです。海底から海⾯まで全部動きますか
ら。ですから、ちょっと頑張って引くのを待って逃げればいいという訳にはいかないんです。そうい
うことを私達は⼦供達にも伝えていかなければいかないというのを教えたのが、今回のスマトラ沖の
⼤津波とそれによって世界が関⼼を⽰した稲むらの⽕ですね。
もうひとつ付け加えると、スマトラ沖地震の津波で何故被害が多くでたかといえばインド洋の沿岸
には津波警報を出している国は少ないんですね。⽇本は地震が起こってから3分以内に気象庁は情報を
出してテレビが⼀⻫に伝えます。地震が起こると、テレビにそれぞれの⾃治体の名前が出ます。その
他に地域の防災⾏政無線で避難勧告がでたり、⾃主防災会や婦⼈防⽕クラブのルートを使ったり、広
報⾞や消防団をまわしたりして⽇本は防災情報を流します。こんなきめ細かい防災情報をだしている
国は世界にないです。
だから、⽇本の取り組みは世界に誇っていいと思います。⽇本がこれだけ災害の多い国でありなが
ら、その災害に⽴ち向かって、これだけの経済成⻑を遂げているということをもっと世界に伝えて
いっていいんだと思います。
最後に去年の災害が何を教えたかというと、⽇本には100年から150年おきくらいに⼤きな地震が
起こってきました。内陸を⾒ると、活断層が分かっているだけで国内に2千はあります。⿃取県⻄部地
震はこれまで知られていない断層で起こりました。
つまり、⽇本に住んでいる以上は地震はどこで起こるか分からないということです。しかも予知が
できない。地震の予知にはいつ・どこで・どのくらいの⼤きさの地震が起こると分からなければ予知
にならないのです。
⼀番難しいのはいつ起こるかということです。どこで起こるというのは最近の研究では分かるよう
になってきました。東海地震は地震計などをおいて、研究を進めています。しかし、他の地震はすべ
ていきなり起こります。それが去年改めて分かったことですね。
2つめの台風をなめてはいけないですが、台風のニュースでものすごい風と⾬の中で町を歩けなく
なって柱にしがみついている⼈の映像を⾒たことあるかと思います。あれはどういう事かと思いま
す。台風なので数時間すれば通り過ぎます。それをあえて、そこまでして出かけなければならない⽤
事とはなんなのでしょう。台風の中を出歩くのは、看板等がぶつかる可能性もあって⼤変危険です。
波が⾼い・川の⽔位が⾼いといって、⾒にいくことも⼤変危険なのでやめていただきたいと思いま
す。
普段やれていないことはいざという時はなかなかできません。これは分かっているようで分かって
いない。つまり、普段の取り組みがいざという時に⽣きるというのが3つめです。
4つめの⾃然災害はなくせてないが、被害は減らせるですが、⽇本に住んでいる以上、世界の地震エ
ネルギーの10%は⽇本と⽇本の周辺で起こります。そして、世界の活⽕⼭の10%は⽇本にあります。
梅⾬があります、台風がきます。こんな国は少ないですね。
でも、例えばイランでマグニチュード6.4の地震が起こると480⼈の⼈があっという間に亡くなりま
す。⽇本でマグニチュード6.4の地震が起こっても、住宅を耐震構造にして家具を固定すればそこまで
の地震被害にはなりません。⽇本の住宅は昭和56年以降、基準が厳しくなっていますから、阪神⼤震
災でも昭和56年以降に作られた住宅はつぶれなかったんです。56年以前に作られた住宅の構造をしっ
かりさせて、家具を固定すれはそうとう被害は防げます。
台風もそうです。サイクロンというのがインド洋にあります。太平洋では台風ですね。サイクロン
がインドからバングラディシュを襲うと5万⼈くらいが死ぬことがあるんですよ。⽇本も昭和20年代
の伊勢湾台風で5万⼈くらいも死んでいます。台風の規模が⼩さくなったわけではありません。何故被
害が減ったのかというと、伊勢湾台風の時は防波堤もなかなかなかった、⾬が降った時に避難する仕
組みもなかった、放送局も台風情報を24時間放送しなかった。そういう取り組みをすることによっ
て、被害は減らすことができるんですね。
さっきでいえば、スリッパを履いて動くことでけが⼈を減らすことができる。しかも、けが⼈を減
らすだけではなく、助ける側にもまわることができるのです。ただ、減るのではなく、プラスマイナ
スで考えるととても⼤きいのです。先程、近所の⼈が助けたのが7割という話をしました。怪我をして
しまうと7割に⼊れないですが、怪我をしない⼈が多ければそっちにまわれるんです。そういう風に考
えながら、防災対策は進めていく必要があるのではなかろうかと思っています。
せっかく今⽇はこれだけのたくさんの⼈にきていただいているのでお話ししますが、NHKにとっ
て災害報道というのは⼈の命に関わる報道ですから、後ろ向きではすまされないと報道関係の者は皆
そう思っています。
もし、何かあった時にはNHKがきちんと放送しているかを確認する意味でもNHKをつけていた
だきたいと思っています。そのお願いをして、私のお話にかえさせていただきます。今⽇はどうもあ
りがとうございました。
⼭﨑 登
□ 史上最多の10個の台風上陸(10⽉まで)
□ 新潟県中越地震(10⽉)
□ スマトラ島沖の巨⼤地震と⼤津波(12⽉)
21⼈の犠牲者のうち17⼈が65歳以上
□ 新潟県中越地震の被災地の⾼齢化率
⻑岡市 20%
⼗⽇町市 26%
⼩千⾕市 25%
川⼝町 27%
⼭古志村 40%
全国平均19・5%
(2) 家族単位を崩さない
(3) 仮設住宅を元の村のようにする
↑
阪神淡路⼤震災の教訓
⾼齢者対策は普段の取り組みが⼤事
⼀⼈の⾼齢者を複数で⾒守る
↑
郵便配達・⺠⽣委員・隣近所・⾏政
□ 東京江⼾川区渚団地
団地の防災名簿・要救助者シール
↑
救助担当者を決めた訓練
防災と福祉・防犯の連携
消防・警察・⾃衛隊 8000⼈
家族・近所が救出 2万7000⼈
(京都⼤学 河⽥恵昭教授)
↑
災害は⼤きくなると防災機関の⼿に負えない
家具転倒・落下 41%
⼈の転倒 25%
⽕傷など 11%
ガラスなど 8%
家屋の倒壊 7%
そのほか 8%
(東京消防庁)
救助される⼈を救助の側に
⼤津波がくることを稲むらに⽕をつけて村⼈に知らせた
↓
「国連防災世界会議」で世界が注目
正しい知識は的確な防災⾏動につながる
□ 台風をなめてはいけない
□ 普段の取り組みがいざという時に⽣きる
□ ⾃然災害はなくせないが、被害は減らせる
最近の消防情勢についての詳細はこちら(PDF1.8MB)