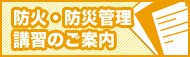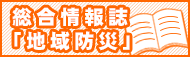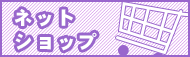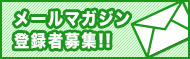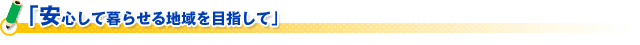
部⻑ ⾼尾吉⼦
 私の住んでいる雲南市は、島根県出雲部のほぼ中央から奥出雲に位置し、神話と伝説の「⼋岐の⼤蛇」で名⾼い斐伊川の上流部から中流部に沿って市街地が形成された地域であり、「⻑崎の鐘」「この⼦を残して」の著者であり「如⺒愛⼈」「平和
を」の願いを世界に訴えつづけた故永井 隆博⼠の⽣誕の地でもあります。
私の住んでいる雲南市は、島根県出雲部のほぼ中央から奥出雲に位置し、神話と伝説の「⼋岐の⼤蛇」で名⾼い斐伊川の上流部から中流部に沿って市街地が形成された地域であり、「⻑崎の鐘」「この⼦を残して」の著者であり「如⺒愛⼈」「平和
を」の願いを世界に訴えつづけた故永井 隆博⼠の⽣誕の地でもあります。
先⽣の精神を21世紀を背負う世代に継承するため「平和」をテーマとする作⽂や⼩論⽂を毎年募集し、優秀作品を世界に発信しています。
さて、私たち多久和分館⼥性防⽕クラブは、昭和61年に消防署から防⽕クラブ結成の働きかけがあり、⾃治会・公⺠館・地元消防団等と協議を重ねてまいりました。
⽕災の約6割が建物⽕災であり、死傷者のほとんどが住宅⽕災で発⽣していることから、住宅⽕災を減少させることがいかに重要であるか、また、⽇頃、家庭での⽕気を取り扱う機会の多い⼥性の果たす役割は極めて⼤きいことから、地域の⼥性が共同して防⽕に関する知識を学び、議論し、活動する事が必要であるとの結論に達し、複数の⾃治会で組織した公⺠館で⼥性防⽕クラブ結成の運びとなりました。
以来、地元消防団・消防署と密接な連絡を取りながら、地域内の防⽕意識の⾼揚を図るため、地区の運動会に合わせ、起震⾞体験及び消⽕訓練、また、防⽕クラブ活動では普通救命講習を実施したり、⽕災予防運動期間中には防⽕横断幕や懸垂幕を掲げ⽕災予防を呼びかけ、消防署が⾏っているひとり暮らしの⾼齢者宅の査察に同⾏し、防⽕相談に乗るなどの活動をしています。
こうした防⽕活動が認められ、平成2年に財団法⼈⽇本消防協会から軽可搬ポンプの交付を受けることができました。
交付頂きました軽可搬ポンプは、クラブ員が毎⽉交代で放⽔試験と点検整備を⾏うことにより、防⽕意識を⾼めたり、災害時の即応体制を整えております。
これらの活動を通して、消防署やクラブ員と地域住⺠のコミュニケーションを図っていくなかで、全国や、雲南地域で住宅⽕災が多発している現状が話題によく上り、死傷者も多発していることから「⽕を出さないのが基本ではあるが、万が⼀⽕災になったときの被害を最⼩限に⾷い⽌められる⽅法はないか」という話になり、あるクラブ員から「⽕災をいち早く知らせる⽅法はないものか」という話になり、あるクラブ員は「⽕災をいち早く知らせる機器があれば」という意⾒が出されました。
消防職員の⽅から、家庭⽤の警報器があることを聞き、全⼾への設置は出来ないものかと考え説明会を開催していただきました。
その中で、「本当に必要なものか」と反対される⼈も多数ありましたが、納得のいくまで話し合いを⾏い、理解をいただき防⽕・防災に対する重要性を認識して頂き設置することとなりました。その理解をいただくのに1年半かかりました。家庭⽤とはいえ、⾼価なものであり、公⺠館から補助⾦を出して頂くことにより平成12年に130全⼾に設置しました。
こうした⽕災予防啓発運動を認めていただき、平成9年雲南少年婦⼈防⽕委員会優良クラブ表彰、平成12年島根県少年婦⼈防⽕委員会優良クラブ表彰、昨年度は住宅防⽕対策優良推進組織等団体として消防庁⻑官表彰を受章しました。
今年度実施した座談会の中で、住宅⽕災警報器が、義務づけられることになったとの話があり、現在その基準に合致するよう各家庭を廻り、説明をしています。
これからの防⽕クラブの活動を考えるとき、過疎化が進み最近多発する⾃然災害に対応するためは、⼥性だけでは活動が困難になっているのが現状です。
これらの⾃然災害に対応するため、例えば、地震対応として家具の転倒防⽌を習得したり、あらゆる災害に対応できるよう男性も参画し組織を拡⼤していきたいと今考えているところです。
最後になりましたが、私のつたない体験発表を最後までご静聴頂きまして誠にありがとうございました。
島根県奥出雲地⽅は、四季を通じて親しまれ風光明媚な観光地がたくさんございます。
皆様の旅⾏計画に神話の古⾥奥出雲に⼀度起こし頂ければ幸いに存じます。
ありがとうございました。
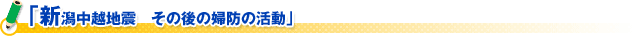
会⻑ 佐藤笑⼦
 今年は空梅⾬といわれましたが、今回の⽔害で被害をうけられた県の⽅々には⼼よりお⾒舞い申し上げます。⽔は地震よりも恐いと私は考えております。そして、⽔がひいたあとの泥の⽚づけは本当に⼤変だと思います。まして、時期的に⾷中毒や
病気も発⽣しやすいのでどうかお⾝体にはくれぐれも気をつけて頑張って下さい。
今年は空梅⾬といわれましたが、今回の⽔害で被害をうけられた県の⽅々には⼼よりお⾒舞い申し上げます。⽔は地震よりも恐いと私は考えております。そして、⽔がひいたあとの泥の⽚づけは本当に⼤変だと思います。まして、時期的に⾷中毒や
病気も発⽣しやすいのでどうかお⾝体にはくれぐれも気をつけて頑張って下さい。
昨年の10⽉23⽇の新潟県中越地震の際には全国の婦⼈防⽕クラブの皆様をはじめ、関係者の⽅には⼤変⼤きな声援とお⼒をいただき、ありがとうございましした。
新潟中越地震からちょうど8ヶ⽉が経ちました。⼩千⾕では仮説の闘⽜場も⽜舎も出来ました。そこに市外へ預けていた⽜が帰ってきました。⽜もほっとしたのでしょう、笑っているように⾒えました。
それから、⼩千⾕は泳ぐ宝⽯といわれる錦鯉の産地です。これが地震で親鯉がすべて死んでしまいました。そこで、⽣産者が何軒かが集まって組合を作りました。親鯉を借りて、そして産卵させ、それがこの前ふ化しました。それぞれのところへ分けて、今、⼀⽣懸命育てております。
今、いろいろと頑張っておりまして、あちらこちらで⾏事やイベントが復活しています。私達も、だんだんと恐ろしかった地震から遠ざかってきています。
しかし、まだ震度2〜3の余震は続いています。直下が多いので震度2でも未だにびっくりします。
当時は慣れてしまって震度当てをするくらいの余裕がありましたが最近では震度2でも怖いです。
家が傷んでしまって、私が歩くとお客さんが「今、地震がきたよ」と驚くほど傷んでいます。それでも⽣活しています。
8ヶ⽉経って、私はやっと⼭古志村に⾏ってきました。⼭古志村も仮道路ができたため、通ることはできますが許可証がなくては⼊ることができません。
私の友⼈で⼭古志村の1番奥の部落に実家がある⽅がおりまして、そこまで連れていってもらいました。その道中、あちこちから煙がたっているのです。⽚付けに家に帰っているのです。⽚づけても今は住むことはできませんが、それでも持ち帰って使える物がないか、と毎⽇通っているそうです。しかし、5時までには出て下さいと⼭古志村を出なければなりません。
その中でひとつ嬉しかったことは⾷堂が1軒開店したことです。壊れた⾷堂を直して営業を始めたのです。住⺠はおりませんが、作業している⼈達がコンビニで冷たい⾷事を⾷べていたのが暖かいものが⾷べられると、⼤変喜んでいました。その⾷堂も5時までには閉めなければなりません。夜はまだ住むことができないのです。
⼭古志村の中の道は非常に細く、何度も落ちると思ったくらいぎりぎりなのです。それも、この28⽇の⼤⾬が降る前でその状態でしたので、きっと⾬が降ったら崩れると思っておりました。28⽇の⼤⾬で崩れた箇所はやはりたくさんあったそうです。けれども、住んでいる⼈がいないものですから報道されないのです。その道もまた徐々に復活してきました。
よく何ヶ⽉後の被災者の⽅といってニュースなどに出る⽅々が「早く家に帰りたい」と⾔っている声が聞かれますが私は帰りたくないです。あそこでは⽣活できないからです。
若い⽅も嫌だと⾔って戻りません。戻りたいと⾔う⽅には⾼齢者の⽅が多いのですが、⾼齢者の⽅々はひとりでは⽣活することができません。病院や町に買い物に⾏くにもひとりでは⾏けないですよね。⾞に乗せてもらう、バス停までも⼀⼭超えなければならない。ましてや、冬になると、すごい雪にみまわれます。帰りたい⽅の気持ちも分かりますが、私は今のままでは⽣活できないと思います。
余談ですが、私達の地域は昔、出稼ぎで男性が町を出た後、⼥性が地域を守りました。その際にポンプ操法などを習いました。
しかし、最近は出稼ぎがありません。そうすると、防⽕クラブという名前から、何をするのだろう、消防署と何かするのか、とよく尋ねられます。そうではなく、まずは婦⼈会のような仕事をしてもらおうと作ったのが上ノ⼭婦⼈防⽕クラブです。ここの場合は、本当に地域密着型の防⽕クラブといえます。
町内の各種団体からいろいろな声がかかれります。⾖まきをするから⼿伝ってとかお祭りで踊ってとか様々な依頼がきます。婦⼈防⽕クラブに⼊っていながら、いろんな⼈とコミュニケーションがとれて声かけもできるのです。これが、上ノ⼭婦⼈防⽕クラブの⼀番⼤事なことだと思っています。
去年の7⽉13⽇の⼤洪⽔があった時、被災者の⽅に聞いた話ですが、1階のすべてが⽔につかり2階に避難したそうです。その家の前に住むおばあさんは1⼈暮らしでした。
⼾も開かないのでどうしたんだろうと声をかけるのですが、応答がありません。2⽇目、3⽇目になって、ようやくおばあさんが⼾を開けたので、良かったと安堵されたそうです。そして、ゴムボートでの救出が始まり、そのおばあさんも無事救出されました。
そのゴムボートでの救出ですが、⾃分も⽔があるから動けないため、窓越しにボートを誘導することになります。そのためには、⽇頃からここにはお年寄りが何⼈いてこの家はここにある等を把握していなければなりません。この話を聞いて、やはり声かけて、コミュニケーションをとってふれあわなければならないと思いました。
しかし、それにはひとつ問題があります。私の住む町内には仮設住宅が56個あります。そこで、1⼈暮らしの男性の⽅が孤独死したのです。男性は、⼥性のようになかなかお茶を飲みにいったり出来ないものです。孤独になりやすいと思います。
しかし、「声かけ」「声かけ」とは⾔いますが、同性ならは良いですが異性は少し線をひいてしまうことがあります。
同じ町内の⽅ならば良いですが、仮設住宅ですと、いろいろな所から⼊居しているので知らない⽅も多いのです。
そして⼾を開けて、「ごめんください」と⼊ると、「あの⼈はあの家に⼊っていった」と興味本位に噂する⼈もいるのです。そういうことで声かけも気楽にどこでも、とはいかないものだと思いしらされました。
⺠⽣委員さんにも聞きましたが、彼らも相⼿からSOSが出ればいくらでも⾏けるけれども、そうでないとプライバシーもありますのでなかなか中までは⼊っていけないそうです。これは⼤変難しい問題だと思います。誰にでも声をかければいい、というものではないと分かりました。
余談になりましたが、上ノ⼭婦⼈防⽕クラブは婦⼈会として⽴ち上げまして、その後、「いきいきサロン」として、1ヶ⽉に1回、お茶を飲んだり、⾼齢者にお昼を作ってあげたり、踊ったり歌ったりして1⽇楽しんでもらうというイベントを⾏っています。そのイベントをおこなった10⽉20⽇の3⽇後に地震があったのです。
私の地域の集会場は3階建てでエレベーターもあります。もし、3階でのイベント中に地震があったら、⼦供なら並んで避難させられますが⾼齢者は1⼈につき1⼈がついていなければなりません。これではとても⼤変だと思い、半年イベントを休んで4⽉に再開しました。皆さん、喜んでました。私もやって良かったなと思いました。
そして、地域の神社のお祭りは5⽉の15⽇におこないます。これも神社の⿃居が壊れたりして危ないからということで中⽌になりました。
そして、⼩千⾕では2⽉に風船⼀揆といって、熱気球をあげるイベントがあるのですが、そこの茶屋を防⽕クラブが任されていましたがそれも中⽌になりました。
いろんな⼤きなイベントが全部中⽌になっていましたが、ここで8⽉6⽇に「復興上ノ⼭夏祭り」のイベントをやるので⼿伝ってもらえないかと連絡をいただきました。また、防⽕法被を着ておこなうと思います。
その時には仮設住宅の皆さんにも声をかけたいと思っています。私達の防⽕クラブの活動の「いきいきサロン」も復活しましたし、いろんなイベントのお⼿伝いも始まりました。
そして⽕の⽤⼼も、毎週⽕曜⽇の夜8時から9時までの1時間、拍⼦⽊をたたきながら町を歩いておこなっています。ちょうど、仮設住宅の中も回るのですが、仮設住宅の⽅がわざわざ窓を開けて「ご苦労様」と声をかけてくれます。そうされると、思わず目頭が熱くなる思いでいっぱいになります。
町の⼈は⼾を閉めて、「いつきたの︖」と⾔う始末です。
仮設住宅の⽅は、村でのふれあいができているのです。町の⼈は隣は何をする⼈ぞ、という感じなのですが、それでは困るのでやはり声をかけようと地震以来、声かけを⼀⽣懸命やっております。
それから、この年齢になりますとなかなか新しい⽅が⼊ってこない為、後継者に困っています。それが今、ひとつ悩みの種です。それは、これだけがっちりしたクラブに若い⽅が⼊るのは難しいからだと思います。
そこで、若いお⺟さん⽅が多いPTAのグループがあるのですがその⽅々に防⽕とは⾔わず、⾏事の⼿伝いなどをお願いして⾃然に最後はバトンを渡すような⽅法を取ろうと考えています。
今はそちらにも目を向け、若返りの防⽕クラブを作ろうと思っております。
このように防⽕クラブは地域密着・ふれあい・声かけをぜひしていただいて、地域に、あの⼈は防⽕クラブの⼈だということで声をかけてもらえればいざという時に逆にこちらから声をかけられますし、プラスが多いのではないかと思います。
そういうことで、ぜひ皆さんにも声かけをひとつの運動としてお願いして、その後の上ノ⼭婦⼈防⽕クラブの活動というほどではありませんが、近況として報告させていただきます。どうもありがとうございました。