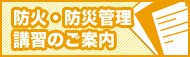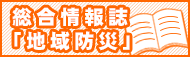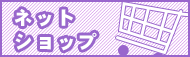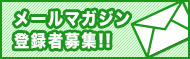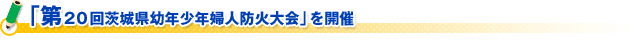
 7⽉27⽇(⽔)、茨城県⽔⼾市の⽔⼾市⺠会館において、第20回となる「茨城県幼年少年婦⼈防⽕⼤会」が開催されました。
7⽉27⽇(⽔)、茨城県⽔⼾市の⽔⼾市⺠会館において、第20回となる「茨城県幼年少年婦⼈防⽕⼤会」が開催されました。
県内の幼年・少年・婦⼈の各防⽕クラブ員などおよそ1.000名が参加し、相互の交流と、地域における⽕災予防思想の⼀層の普及を図ることを確認し合いました。
⼤会では、⽕災予防活動に功績のあった50の団体及び個⼈に対し表彰状が授与され、そのうちの地元⽔⼾市の「⼤⼯町地区婦⼈防⽕クラブ」の袴塚禮⼦会⻑が受賞者を代表して謝辞を述べられました。
また、アトラクションの時間には、同じく地元⽔⼾市の「のぎく保育園」の園児によるマーチングバンドの演奏とそれに引き続いての「防⽕への誓いのことば」などが披露され会場を盛り上げていました。


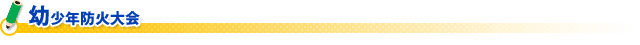
 幼年消防クラブが発⾜し25周年を向えた今年は、幼少年時期からの防⽕の理解を求めることにより将来の健全な⻘少年の育成を目指すことを目的とし、平成17年7⽉31⽇(⽇)に⼥性防⽕クラブ・警察・授産所施設等の協⼒を得て、「防⽕防
犯まつり」を開催しました。
幼年消防クラブが発⾜し25周年を向えた今年は、幼少年時期からの防⽕の理解を求めることにより将来の健全な⻘少年の育成を目指すことを目的とし、平成17年7⽉31⽇(⽇)に⼥性防⽕クラブ・警察・授産所施設等の協⼒を得て、「防⽕防
犯まつり」を開催しました。
郡上市⼥性防⽕クラブによる住宅防⽕に伴うパンフレットの配布・炊き出し訓練や、岐⾩県防災航空隊の訓練披露、市内の保育園による演技披露のほか、消防・警察⾞両の展⽰や地震・煙・AED体験、住宅防⽕対策ゲームや消防⾞との綱引き等をし、⼤⼈から⼦供まで約2,000⼈の来場者があり盛⼤に開催することができました。




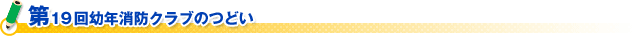
 京都府⻑岡京記念⽂化会館⽂化ホールにおいて、7⽉2⽇(⼟)午前10時30分から第19回幼年消防クラブのつどいを⻑岡京市幼少年婦⼈防⽕委員会と(財)⽇本防⽕協会の共催で開催しました。
京都府⻑岡京記念⽂化会館⽂化ホールにおいて、7⽉2⽇(⼟)午前10時30分から第19回幼年消防クラブのつどいを⻑岡京市幼少年婦⼈防⽕委員会と(財)⽇本防⽕協会の共催で開催しました。
これは、防⽕思想啓発運動の⼀環として、毎年引き続き防⽕のつどいを開催しているもので、楽しみながら防⽕思想の普及・推進に努めるとともに、幼年消防クラブのPRや啓発並びにクラブ員相互の親睦を図り、もって地域ぐるみの防⽕意識の⾼揚を図ることを目的とするもので、今回で19回目になりました。
第1部は式典で、関係各位のあいさつ及び祝辞を頂いた後、クラブ員全員で防⽕宣⾔をしました。
そして、今年のメイン、参加者全員で歌う「みんなで歌おう︕踊ろう︕ひとつの歌で︕」をスローガンに2曲を選定して⼤合唱をしました。
選定された曲は、「ともだちさんか」と「世界中の⼦どもたちが」です。
代表の幼年消防クラブ員は壇上に上がり、毎年、笑顔たっぷりの顔で、会場のクラブ員と共に、踊りながら⼤きな声で合唱してくれました。
また、幼年消防クラブ員のかわいい法被姿に、婦⼈防⽕クラブ員だけでなく、来賓や⼀般の⼊場者もつられて⼀緒に記念歌をくちずさんでいる姿は、実に微笑ましい光景でした。
第2部のアトラクションは、⾳楽劇団てんてこによる「てづくり楽器ワールド」を公演としました。
⾝の回りにある素材で作った楽器を使って、てんてこ風にアレンジされた不思議な⾳のオリジナル曲を会場全員で楽しんで鑑賞して頂けたと思います。
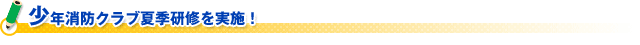
 ⼋⼥消防本部では、管内の少年消防クラブがそれぞれ夏季研修を⾏いました。
⼋⼥消防本部では、管内の少年消防クラブがそれぞれ夏季研修を⾏いました。
有明海に注ぐ⽮部川の清流でのカヌー教室、キャンプ場に出かけての登⼭、カレー作りなどクラブ員同⼠交流を図りました。
⼤⾃然に触れながらふるさとの美しさ偉⼤さそしてその⾃然を守ることの⼤切さを学びました。
また、防⽕教室や救急教室も⾏い、命の⼤切さ、⼼肺停⽌状態になった場合の⼼肺蘇⽣法などを学び、充実した研修となりました。
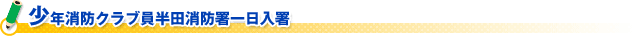
 知多中部広域事務組合消防本部は、愛知県知多半島のほぼ中央に位置する半⽥市、阿久⽐町、武豊町、東浦町の1市3町を管轄する消防本部です。
知多中部広域事務組合消防本部は、愛知県知多半島のほぼ中央に位置する半⽥市、阿久⽐町、武豊町、東浦町の1市3町を管轄する消防本部です。
当消防本部では、平成17年8⽉4⽇(⽊)〔半⽥市のクラブ員対象〕、5⽇(⾦)〔阿久⽐町、武豊町、東浦町のクラブ員対象〕の両⽇に半⽥消防署⼀⽇⼊署を実施しました。
この半⽥消防署⼀⽇⼊署は、少年消防クラブ員に対して、消防についての関⼼を深めさせ、実践活動を通して少年期から⽕災予防の知識と技術を培うとともに、防⽕意識の⾼揚及びクラブ員相互の親睦を図ることを目的とし、昭和54年度から実施、今年度で27回目の⼀⽇⼊署となりました。
1 実施内容
(1) 午前の部
ア ⼊署式
イ 防⽕映画上映(こぎつねの消防隊)
ウ 規律訓練、救急法
エ 通信指令室の説明及び⾒学
オ 望楼⾒学
カ ⾞両説明
(2) 午後の部
ア 救助訓練⾒学
イ 消防○×クイズ
ウ はしご⾞搭乗
エ 放⽔体験
オ 濃煙体験
カ 起震⾞体験
キ 退署式
2 参加者
(1) 平成17年8⽉4⽇(⽊)
半⽥市の少年消防クラブ員78名
少年消防クラブ指導者2名 計80名
(2) 平成17年8⽉5⽇(⾦)
阿久⽐町、武豊町、東浦町の少年消防クラブ員83名
少年消防クラブ指導者3名 計86名
2⽇間合計 166名
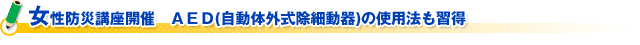
 碧南市⼥性防⽕クラブでは、7⽉1⽇から延べ4⽇間に亘り碧南消防署で⼥性防災講座を開催しました。延べ出席者数は469⼈にも達し、8⽉11⽇に全⽇程を終了しました。
碧南市⼥性防⽕クラブでは、7⽉1⽇から延べ4⽇間に亘り碧南消防署で⼥性防災講座を開催しました。延べ出席者数は469⼈にも達し、8⽉11⽇に全⽇程を終了しました。
第1⽇目は、地震・台風体験、消防⾃動⾞や消防庁舎内の⾒学、消⽕訓練、ハイゼックスによる非常炊出しとカレーの試⾷という盛りだくさんのメニューです。あいにくの⾬模様で救助袋の体験は中⽌。ちょっとスリルを味 わいたかったのに、憎らしい⾬でした。
第2⽇目は家庭における救急法の講習、第3⽇目はAED(⾃動体外式除細動器)の使⽤法を含めた普通救命講習を実施しました。愛知万博会場でAEDにより⼈命が救われたというニュースがタイムリーであったためか、第3⽇目の受講希望者が殺到し、急きょ⽇程を7⽇間に増やしていただき、合計139⼈のクラブ員が普通救命講習修了証の交付を受けました。
第4⽇目は、市内の⼯場の施設⾒学です。さすがステンレス鋼のメーカーです。⼯場内は熱気にあふれ、折からの猛暑と重なりお化粧も汗とともに流れ落ちるほどで、男性の職場がどれほど⼤変かよく分かりました。
4⽇間の講座を通じ、「⾃分の命は⾃分で守る」「愛する⼈の命を救う」「家庭から⽕を出さない」ことを皆再認識し、非常に有意義なものとなりました。



 7⽉25⽇(⽉)晴天の中、元気いっぱいの⼩学⽣が「BFCの集い」に富⼭消防署にやってきました。この集いは毎年、楽しく⽕災予防について学んでもらおうと⾏っているものです。会場にやってきた⼦供たちは展⽰されている各消防⾞両を⾒て、
興味津々な様⼦でした。
7⽉25⽇(⽉)晴天の中、元気いっぱいの⼩学⽣が「BFCの集い」に富⼭消防署にやってきました。この集いは毎年、楽しく⽕災予防について学んでもらおうと⾏っているものです。会場にやってきた⼦供たちは展⽰されている各消防⾞両を⾒て、
興味津々な様⼦でした。
実際に現場で使⽤しているヘルメット・防⽕⾐を着⽤しての放⽔体験では、⽔の圧⼒にも負けず的に描かれている炎を消そうと真剣な様⼦でした。うまく当てたときには「やった〜」と無邪気に笑う姿が⾒られました。
その他にも、梯⼦⾞試乗・ロープ結索・通信指令室⾒学などの消防の仕事にも触れ、また、起震⾞試乗・煙中体験など震災時の体験も⾏い、⼦供たちにとってとても良い体験になったと思います。
⼦供たちは「消防の仕事は⼤変そう」、「⽇ごろから災害に備えたい」など、さまざまな思いをもっていました。
この「BFCの集い」で学んだ知識や体験を周りの友達や家族にも伝え、防災意識を⾼め、今後の防災活動に役⽴ててほしいと思います。
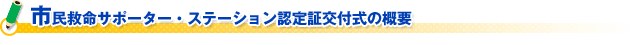
 豊中市消防本部は、7⽉22⽇(⾦)に、市施設をはじめ、給油取扱所、ホテル、スポーツクラブ、福祉施設等96施設に市⺠救命サポーター・ステーション認定証及び認定表⽰マークを交付しました。
豊中市消防本部は、7⽉22⽇(⾦)に、市施設をはじめ、給油取扱所、ホテル、スポーツクラブ、福祉施設等96施設に市⺠救命サポーター・ステーション認定証及び認定表⽰マークを交付しました。
この制度は、不特定多数の市⺠が利⽤する施設で、従業員の半数以上が普通救命講習を受講していること等を要件に、市⺠救命サポーター・ステーションとして認定し、⾃施設内及び施設周辺地域で、救護を必要とする事故が発⽣した場合に、普通
救命講習修了者の市⺠サポーターが、応急⼿当や119番通報、救急隊員への情報提供等、積極的に救護活動を⾏うことを目的に設置されたもので、認定書を交付されたホテル関係者は、「お客様の安全・安⼼を確保するという姿勢を表すものが同サポーター・ステーション。ホテル内はもちろんですが、近隣で発⽣する事故も念頭に置き迅速に対応したい。」と話していました。
豊中市消防本部としましては、今後も様々な施設の賛同を得て、この活動を発展させ、市域全体の防災⼒を⾼めたいと考えています。
 (参考)
(参考)
市⺠救命サポーター・ステーションの認定について豊中市では、平成15年6⽉から消防本部が市内の給油取扱所を対象に実施していた市⺠救命サポーター・ステーション制度を、豊中市が目指す「市⺠の防災⼒を⾼めよう」「安全・安⼼のまちづくり」を更に推進するため、サポーター・ステーション対象施設の範囲を広げるとともに、市の全施設(⼩・中学校を除く)を、率先して市⺠救命サポーター・ステーションとして認定することとした。
この制度は、⾃施設内、及び施設周辺、施設周辺地域において救護を必要とする事故が発⽣した場合に、または市内で発⾒あるいは遭遇した時は、各施設の救急講習修了者である市⺠救命サポーターが、積極的に救護活動協⼒を⾏うことを目的に設置された。
⼤阪府下では初めて実施され、豊中市消防本部では豊能地区の消防本部に活動を共に進めて欲しいと要請したところ、いずれの市町も実施の⽅向で検討するとの回答があったとのことである。
豊中市は、平成16、17年度の2ヶ年で全職員に普通救命講習を受講するよう通知し、この市⺠救命サポーター・ステーションの認定に必要な、施設ごとに職員の半数以上が普通救命講習を受けていること、という条件を満たすこととしている。
この制度は、消防本部が平成15年6⽉から市内の給油取扱所のみという範囲で開始したが、⾼齢化社会の進展、社会的モラルの低下による事件の増加、交通事故、核家族化に伴う不安の増⼤による事故、また⾃然災害、尼崎市で発⽣したJRの事故など、救命に関する応急⼿当を含め、救護を必要とする事故には、側にいる市⺠の早い応急⼿当が必要とされることから、市⺠が利⽤する施設を主に、地域全般にも拡⼤する必要があるということから、この度、消防本部が制度を⾒直し、対象範囲を拡⼤することとした。
消防本部では、市施設以外に市内事業所にも参加呼びかけを⾏い、7⽉22⽇(⾦)の認定交付式には、ホテル、スポーツクラブ、福祉施設など9事業所、市施設54施設、給油取扱所33施設(平成15年当初は委嘱としていた)、合計96施設の認定を⾏った。
消防本部では、本制度の対象となる市内の総てのスポーツクラブ、福祉施設、駅舎など従業員が10⼈以上の事業所で不特定多数の⼈が利⽤する施設に、もしもの時にすぐに対応出来る、特に救命処置が適切にでき、市⺠が安⼼して利⽤できるような施設としての体制作りを⾏うよう、今後も呼びかけを続けていくこととし、企業姿勢に訴えていきたいとしている。
また、⾃主防災の観点からも、⾃助、共助体制作りが防災の基本であるとして、各施設に積極的に参加協⼒して欲しいとしている。
消防本部では、「市⺠救命サポーター・ほーむ」という、地域内における近隣での協⼒体制作りも同時に進めているが、こちらは⼥性防⽕クラブの会員を対象として参加の呼びかけを⾏っている。現在⼀般を含め180名ではあるが、救急講習の都度、参加⼈員は増加しているとのことである。豊中消防本部では、更にこの活動を活発化し、市域全体の防災⼒を⾼め、安全・安⼼のまちづくりに努めたいと考えている。

 平成17年8⽉5⽇(⾦)に豊⽥市消防本部庁舎において、⼀⽇消防署員が⾏われ、市内の少年消防クラブ員200名が参加しました。この催しは、少年消防クラブに消防の仕事を体験させ、消防への正しい理解を深め、防⽕意識を⾼めてもらおうと、昭和60年から、毎年この時期に開かれています。はじめに予防課⻑から代表児童に辞令が交付され、「消防の仕事の基本は、⼈を助けることです。訓練をとおして消防の仕事内容を知ってもらい、⼈を助けるためにはどういう知識と技術が必要なのか学んでほしい。」とあいさつをしました。
平成17年8⽉5⽇(⾦)に豊⽥市消防本部庁舎において、⼀⽇消防署員が⾏われ、市内の少年消防クラブ員200名が参加しました。この催しは、少年消防クラブに消防の仕事を体験させ、消防への正しい理解を深め、防⽕意識を⾼めてもらおうと、昭和60年から、毎年この時期に開かれています。はじめに予防課⻑から代表児童に辞令が交付され、「消防の仕事の基本は、⼈を助けることです。訓練をとおして消防の仕事内容を知ってもらい、⼈を助けるためにはどういう知識と技術が必要なのか学んでほしい。」とあいさつをしました。
今年度は、猛暑の中での実施となり時間が経つごとに屋内訓練場も徐々に熱気に包まれ、最初の規律訓練からクラブ員達は、⼤粒の汗を流しての訓練を体験しました。規律訓練では、消防職員の「敬礼」の掛け声に少し緊張しながら最後には、しっかりと敬礼ができるようになりました。その後、班ごとに分かれて、庁舎内にある防災学習センターで煙の充満する迷路の中から脱出する煙脱出メイズや震度7の揺れが体験できる地震体験ハウス、⼈⼯呼吸や⼼臓マッサージの応急⼿当の学習、消防本部に隣接する中消防署で、実際に消防職員が着⽤する防⽕⾐を着装しての放⽔体験、訓練塔を使⽤してのロープ体験をしました。
ロープ体験では、地上から約10メートルの⾼さに約20メートルの⻑さで張られたロープをチロリアン渡りで渡りました。下には、防護ネットが張られているもののクラブ員たちにとってはかなりの恐怖⼼がある様⼦でしたが、それでも勇気を振り絞って訓練に挑戦していました。中には途中で⼒尽きてしまうクラブ員もいましたが、⾒学していたクラブ員の声援を受け、最後まで渡りきることができました。
参加したクラブ員は、ロープ体験を終え「最初は簡単にできると思ったけど、渡りきるまでにけっこう距離があり⼤変でした。消防署員は毎⽇、ロープ訓練をしている事を知り、⼈を助けるためには、こうした訓練が⼤切ということがよくわかりました。暑い中での訓練はつらかったけれど消防署員の仕事の⼤変さがわかり、⽕災予防に対する気持ちが⼀層強まりました。」と流れる汗をふきながら話していました。また、放⽔体験を終えたクラブ員は、「防⽕⾐を着たらとても暑く、またホースから⽔が出るとき⽔圧でものすごい反動があり、びっくりしました。消防署員の⼈が⼤変な訓練をして僕らの町を守ってくれることがわかりました。」と話していました。
⼀⽇署員は、午後3時30分まで⾏われ、最後に修了証と参加賞が配布されました。そして、⼀⽇署員を終えたクラブ員は、嬉しそうに迎えにきた家族に今⽇⼀⽇の体験を話していました。