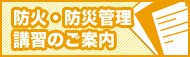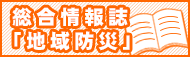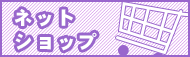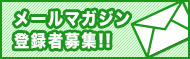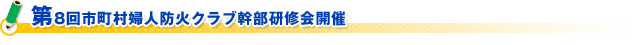
 「第8回市町村婦⼈(⼥性)防⽕クラブ幹部研修会」が、平成17年7⽉7⽇(⽊)・8⽇(⾦)の2⽇間、ホテルルポール麹町において開催されました。
「第8回市町村婦⼈(⼥性)防⽕クラブ幹部研修会」が、平成17年7⽉7⽇(⽊)・8⽇(⾦)の2⽇間、ホテルルポール麹町において開催されました。
この研修会は、団体相互の交流と活動内容等の情報交換などを⾏うことにより有事に際して地域間組織の⼀層の充実・強化・連携を図り連絡応援態勢の構築を目的に⾏われております。
7⽇は先ず、(財)⽇本防⽕協会⼩林弘明常務理事より開会の⾔葉の後、当協会徳⽥正明会⻑による講話が⾏われ、「婦⼈防⽕クラブ員の皆様が市町村幹部研修会に参加して、なおかつ理論ばかりではなく⾏動する事を望みます。異常気象や災害が多い今⽇この頃、皆様⽅が消防と協⼒し、活動する事を期待しております。」と話されました。
次いで、総務省消防庁蝶野光審議官より、「婦⼈防⽕クラブに望む」と題して、ご講演をいただきました。
また、消防庁防⽕安全室⽊原正則室⻑より「⽕災警報器の普及について」の施策説明をいただきました。
 次いで体験発表に移り、新潟県⼩千⾕市婦⼈防⽕クラブ会⻑佐藤笑⼦様が「新潟中越地震 その後の婦防の活動」、島根県雲南市多久和分館婦⼈防⽕クラブ部⻑⾼尾吉⼦様が「安⼼して暮らせる地域を目指して」について、体験発表をそれぞれ⾏いました。(来⽉号にて掲載予定)
次いで体験発表に移り、新潟県⼩千⾕市婦⼈防⽕クラブ会⻑佐藤笑⼦様が「新潟中越地震 その後の婦防の活動」、島根県雲南市多久和分館婦⼈防⽕クラブ部⻑⾼尾吉⼦様が「安⼼して暮らせる地域を目指して」について、体験発表をそれぞれ⾏いました。(来⽉号にて掲載予定)
そして、NHKキャスターで、現在、「語り」の達⼈として著名な平野啓⼦先⽣の講演「語りは⼼の絵画」が⾏われ、語りや朗読を織り込んだお話に参加の皆様より多くの拍⼿をいただきました。
 その後、⾏われました当協会秋本敏⽂理事⻑の講話「ひとりひとりの幸せ結んで」も参加の皆様に⼤変好評をいただきました。
その後、⾏われました当協会秋本敏⽂理事⻑の講話「ひとりひとりの幸せ結んで」も参加の皆様に⼤変好評をいただきました。
夜は参加者による交換会が⾏われました。総務省消防庁東尾次⻑もかけつけ、ご挨拶を頂戴し、平野啓⼦先⽣も同席され、各都道府県間での交流が盛⼤に⾏われました。
2⽇目は、⼭梨県⼥性防⽕クラブ連絡協議会 中澤会⻑による講話「福井豪⾬災害への⽀援活動」で始まり、続いて、各県に分かれワークショップが⾏われました。

(財)⽇本防⽕協会徳⽥会⻑ ワークショップの課題テーマは、共通テーマ、住宅⽕災防⽌対策推進に関する⽅策「住宅⽤⽕災警報器の普及啓発活動について」(住宅⽤⽕災警報器PRハンドブック〜⽕災を防ぐ「あたりまえ」を地域に︕〜)が話し合われました。
グループ別テーマでは、
第1グループ(北海道・⻘森県・福島県・茨城県・東京都・神奈川県・⼭梨県・⻑野県・滋賀県・京都府・⿃取県・島根県・⾹川県・愛媛県・熊本県・⼤分県)により「安全・安⼼の地域社会づくりに果たす婦⼈(⼥性)防⽕クラブの役割について」(消防団、⾃主防災組織等と連携した活動の実態、幼少年消防クラブの育成と婦防、災害時要援護者と婦防)
第2グループ(岩⼿県・宮城県・栃⽊県・群⾺県・新潟県・富⼭県・岐⾩県・静岡県・⼤阪府・兵庫県・岡⼭県・広島県・⾼知県・福岡県・宮崎県・⿅児島県) により、「婦⼈(⼥性)防⽕クラブ活動と資⾦調達の⼯夫について」(財政危機下における資⾦調達の⼯夫の実態、今後における資⾦調達への提⾔)
第3グループ(秋⽥県・⼭形県・埼⽟県・千葉県・⽯川県・福井県・愛知県・三重県・奈良県・和歌⼭県・⼭⼝県・徳島県・佐賀県・⻑崎県・沖縄県)により「⼤災害における婦⼈(⼥性)防⽕クラブの役割について」(平成16年の各種⾃然災害における婦防の取り組み状況、防災訓練の⾒直し・充実⽅策、活動域を超えた広域⽀援のあり⽅)の3つのテーマについて、議論が交わされました。
最後に修了式がとりおこなわれ、盛⼤なうちに第8回市町村婦⼈(⼥性)防⽕クラブ幹部研修会が終了しました。

総務省消防庁防⽕安全室 ⽊原室⻑

新潟県⼩千⾕市上ノ⼭婦⼈防⽕クラブ
佐藤会⻑

島根県雲南市多久和分館⼥性防⽕クラブ
⾼尾部⻑

平野啓⼦⽒

(財)⽇本防⽕協会 秋本理事⻑

第1グループ

第2グループ

第3グループ

会場全体

修了式
「⽕災警報器の普及について」(pdf)
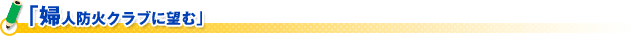
 去年の7⽉くらいから⽔害があったり、地震があったり、台風が非常に多かったりした中で、よく消防防災分野でどういう危険があるのかを分類したものがあります。
去年の7⽉くらいから⽔害があったり、地震があったり、台風が非常に多かったりした中で、よく消防防災分野でどういう危険があるのかを分類したものがあります。
⼤規模災害ということで、通例、地震災害から始まりまして、風⽔害・⽕⼭災害というのがあります。それ以外に⼤きな事故として、航空・海上・鉄道・道路・危険物・⽕災・原⼦⼒事故などがあります。だいたい、今まではこれらが消防の担当でした。
ところが昨年の秋から変わってきておりますのは、武⼒攻撃事態というものに対して消防の職団員が担当しなければならないという話になりました。後で若⼲お話させていただきますが、武⼒攻撃事態とは、たとえばある国から突然⽇本に対してミサイルが打ちこまれるとか、そういった場合にどうするのかということに関して、⽇本ではまったく法令がなかったのですが昨年の秋できあがりました。そういう意味で武⼒攻撃事態に対しては、⾃衛隊がもちろん対応していただけるのですが、そこに住んでらっしゃる住⺠の⽅を置いて誰が救うのでしょうか。誰が安全に違うところにお連れするのですか。そういうことを残念ながら⽇本では全く決められていませんでした。戦前はもちろん隣組をはじめ、それなりの制度はあったのですが、国としてそういう制度がきっちり⾏われていたドイツと⽐べますと、本⼟が爆撃された国⺠の死亡率が⼀桁違います。あれだけ、⼤変な空襲をうけたドイツであっても⽇本よりも遙かに少ない被害でおさえられたのです。それは、やはり戦争の非従事者を守る、国⺠を保護する為の法制があったからというのは事実です。
 そういうものに対して誰がやるのか、と様々な議論がありました。やはり、これは消防団、そして地域の防災を担当してらっしゃる⽅々に⼿伝っていただかないと地⽅公共団体だけではできないということで、昨年の9⽉からそういう部分についても⼤きな仕事になりました。様々の危険があるのですが、サイバーテロや⼤量避難⺠流⼊、外国で邦⼈が被害を受けたということ以外は⼤半を消防でやっていかざるを得ないというのが今の危険に対する考え⽅です。
そういうものに対して誰がやるのか、と様々な議論がありました。やはり、これは消防団、そして地域の防災を担当してらっしゃる⽅々に⼿伝っていただかないと地⽅公共団体だけではできないということで、昨年の9⽉からそういう部分についても⼤きな仕事になりました。様々の危険があるのですが、サイバーテロや⼤量避難⺠流⼊、外国で邦⼈が被害を受けたということ以外は⼤半を消防でやっていかざるを得ないというのが今の危険に対する考え⽅です。
平成16年における我が国の主な風⽔害ですが、6⽉9⽇に台風4号が上陸しています。それ以来、11⽉11⽇の⼤⾬まで昨年の6⽉から11⽉のあたままでだけでも亡くなった⽅が219名、住宅家屋の全壊いたしましたのが1,342という状況です。私どもも、緊急消防援助隊を始めて出させていただきましたのが7⽉13⽇の新潟・福島豪⾬でありました。この対策はある意味では初めてということもあり、様々な間違えもありましたがようやく⼀段落したと思っているところ、次の週に福井で豪⾬がありまして、⼤変な状態だと思っておりました。また次から次にくる台風くる台風が全部⽇本に上陸しました。
だいたい、毎年本⼟に台風が上陸するのは3度と⾔われていました。本⼟というは気象庁の定義によりますと、本州・北海道・九州・四国いずれかの海岸線を台風が超えたとき、これが本⼟だそうです。したがって、それ以外のところは⽇本に上陸したとは⾔わない。沖縄も⽇本ですが定義ではそうなっております。
何故、こういう状況になったかというのは、⼤きな原因として⾔われておりますのはふたつあります。ひとつは⿊潮の流れが変わったこと、もうひとつは太平洋を含めて海⽔温が上がっておりますから、それなりに北の⽅へいっても⼗⼆分にエネルギーを吸い込めるということであります。
次に地震ですが、昨年の我が国の主な地震災害を⾒ていただくと、昨年8⽉から12⽉までの間だけでも震度5以上の地震が13回もありました。おかげさまをもちまして、⼈的被害、亡くなられる⽅がでましたのは中越地震だけでした。さまざまのプラス⾯がありました。⼤きな話としてはふたついえると思っています。ひとつは神⼾で⼤変な被害を被りましたガスによる⽕災がほとんどなかった。⻑岡で1件あっただけと報告を聞いております。年明けで起こりました福岡におきましても、ガスの引⽕は1件もなかったということです。もうひとつは、家が倒壊しますと復興を急ぐばかりに電気の復興を急ぎます。急ぐと家が倒壊しておりますから漏電と同じ現象になって、そこに⽕が点くというのは神⼾では何度もありました。今年の地震ではそういうことは1件もありません。特に、新潟県の中越ではすばらしい対応をしていただいたと思いますが、1件1件電⼒を復旧させる時に消防署や消防団の⽅に⽴ち会っていただいて、そういった熱源になるコンロなどのスイッチを切った上で電気を通す、留守の場合はブレーカーのところで電気を⽌める、こういう細かい作業を全部やっていただきましたので通電⽕災は1件もなかったということです。これは本当に皆さんをはじめ、消防防災の関係者の⽅のすばらしい業績じゃないかと思っております。
先程の⽔害でもそうですが、この中越地震でも7⽉1⽇現在で亡くなった⽅は48名なのですが、そのうち27名の⽅が65歳以上の⽅、60歳以上の⽅を含めますと29名、約30名が⾼齢者の⽅です。⽔害の時はこの割合が更に6割を超える状況になっておりました。こういう⼈達をどういった形で守るのか、更に必要な避難というものが⼀番⼤きな課題といわれておりまして、様々な検討会等を開いて検討しております。各消防本部では、それぞれの管轄の中で介護保険の介護を受けてらっしゃる⽅の情報をいただいて、消防としてどこの家のどういう⽅なのかきっちり把握できるようにしようという形でやらせていただいております。ただ、今は個⼈情報保護の問題等もございますので、皆様⽅のご協⼒をいただければより効率よくできるのではないかと思っている次第です。
今年の3⽉にでました活断層や海溝型地震の⻑期評価では、様々なところで⼤変な確率で地震が起こりますと、すでに発表されております。
北海道の根室沖・⼗勝で地震が起こったので、しばらくは北海道では地震はないのではないかと皆様は思われるでしょう。しかし、去年から何度も何度も地震は起こっております。今年の春で根室沖では30%〜40%と非常に⾼い数字がでておりますし、新潟県では糸⿂川で断層線14%という数字になっております。これははっきりいいまして、非常に⼤きな地震が起こる確率であります。先⽇の中越の地震は、この対象とはなっておりません。あの規模の地震が起こる確率は発表されておりません。いつ起こってもまったく不思議ではないということです。発表されていないから起こらないという事ではなくて、震度5弱程度で地震が起こるのはどこで起こってもまったくおかしくないのです。
では、このような⾃然災害に対してどのような事をおこなってきたかという事ですが、⾃然災害による死者等の推移を⾒ていただくと、かつて昭和23年頃から考えますと福井地震では約5千⼈が亡くなりました。さらに、風⽔害等を⾒ましても伊勢湾台風の年には約6千⼈が亡くなっています。たしかに、阪神淡路⼤震災の6,481名というのは⼤変な数ですがよくよく⾒ていただくと⽔害や豪⾬で千⼈以上の⽅が亡くなるということは⾒事に無くなりました。皆さんを始め、それぞれの体制が出来上がってきたということです。これまで対策をしてきた成果といえるのかもしれません。しかし、伊勢湾台風から40年経ってしまったので対策が少々古くなってしまいました。⾒直しが必要かと思います。ただ、これらをきちんと⾒直すことにより、⾃然災害に関しても最⼩限の被害にくい⽌められるということであります。
そして⽕災による死亡原因ですが、先⽇、消防庁で発表しました資料によりますと、ほとんどが逃げ遅れになっております。したがって、それをひとりでも少なくするために法制化までさせていただいて、⽕災警報器を義務付けさせていただいたわけです。
さらに、⾒ていただきたいのは、この逃げ遅れを含めた、それぞれ年齢別に死亡原因上3つをとった場合、残念ながら79名という形でありますが、65歳以上の⽅で1番多い理由は病気で⾝体が不⾃由であったからと考えられるもの、2番目に多いのは⼀般的に避難⾏動をおこしているけれども逃げきれなかった。どちらかといえば、⾝体がご不⾃由に含まれるのではないかと思います。熟睡していたとか、泥酔していたということだけならば警報器で気づいていただければ逃げられます。ただ、それよりも1歩踏み込んで助けるためには、どこの家に逃げるために周りの⼈の⼿助けが必要な⽅がいるのかを把握していただかないと⾼齢者の逃げ遅れを確実に減らしていくということができないのです。
まず、気がついてもらうための体制を制度として作りました。それを、さらに中⾝のあるものにしていただくためには、ぜひ地元の皆様のような⽅々のご協⼒が必要になるのです。
そして、⼤規模災害に備えた住⺠による防災活動ですが、これは阪神淡路⼤震災で当時とりましたアンケートでは、現実問題、阪神淡路⼤震災の時には誰が救ってくれたのかといえば、⾃分で逃げ出しましたという⽅が約35%、家族に助けてもらったのが32%、友⼈・隣⼈が28%、通⾏⼈が3%で、なんとあれだけの震災にもかかわらずこれで98%になります。
やはり地元のことをしっかり知るというのが重要でありまして、そういう意味で皆様⽅にご活動いただいているように、⾃分の町で起こったことをきっちり検証していただくというのが重要です。
福岡の地震が起こった際に、私も現地に赴きました。そこで、消防の⽅に消防OBで最年⻑の⽅から昔、福岡にこういう地震があったという話を聞かされた覚えがある、とのお話を伺いました。福岡というのは地震がおこらない所との認識があるかもしれませんが、そんなことはないのです。確実にそういうことが繰り返されているはずです。
私の⽣まれ故郷の奈良、育ちました⼤坂の親戚に「東京に引っ越してこないか」と話すと、よく「あんな地震の多いところは嫌だ。関⻄は地震はないんだ」と⾔われていました。
しかし、秀吉の住んでおりましたところが崩壊した原因は地震です。平家が遷都した際には地震や⼭津波を含めた⼤災害がおこっています。必ず災害は過去におこっています。
⽔俣の⽔害があった際に、地元で⼤きな被害がありました。調べてみましたところ、残念ながら地域としての⾃主防災組織がなかったところでのみ、亡くなられた⽅、⾏⽅不明の⽅がでてきています。これも現実です。
昨年の中越地震以来、非常に防災に対する関⼼が⾼まっております。神⼾から10年たちますと、ほとんどの⽅の意識が低くなっております。
その中でどうするかというと、皆様⽅のようなしっかりした形で活動していただいているところもありますが、まだまだ未設置団体もありますのでそのあたりについても、ぜひお願いしたいという事と、消防機関と皆様⽅、婦⼈防⽕クラブと消防団を始め、それぞれ役割分担がありますので、ぜひ協⼒をして⼀致団結して活動していただきたいです。
そして、皆様⽅はまわりにひとりでも多く、そういった意識のある⽅を育てていただく必要があります。そのためのツールとして、消防庁のホームページにe-カレッジというのを始めております。これは様々な防災・消防の基礎的知識などを掲載しておりますので、ぜひご活⽤をいただきたいと思います。
武⼒攻撃事態に関して⻑官から⼀⾔皆様に、とのことですが、武⼒攻撃事態について、⼤変な役割が消防にきたわけですが、本年は全国の47都道府県がそれぞれの国⺠保護計画を作っております。そして来年1年間、全国のすべての市町村は国⺠保護計画を作る形になります。
そこで、地元をよく知る皆様⽅が積極的に発⾔をしていただきたいと考えております。武⼒攻撃事態に直接対応するのは⾃衛隊になるかと思われますが、それに伴う被害を最⼩限にとどめるのは消防防災関係者の⼤きな仕事なんだということをぜひお考えいただきたいと考えております。
国⺠保護において、婦⼈防⽕クラブとして皆様にやっていただかなくてはならないのは、消防団と皆様⽅で住⺠の⽅にいち早く避難していただくことです。まさに、これは地元によってどういうやり⽅がよいのかは千差万別であります。やり⽅については皆様⽅のお知恵を拝借させていただきたいですし、様々な形でのリーダーとしての役割を果たしていただきたいと考えております。皆様⽅の地元でも市町村レベルの打ち合わせが始まりますので、ぜひとも積極的に発⾔していただきたいとお願いいたします。