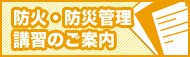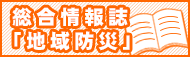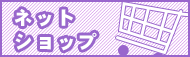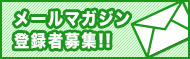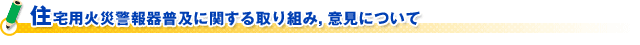
茨城県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会総会が平成17年6⽉17⽇(⾦)茨城県市町村会館において、茨城県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会幹部及びクラブ員231名が参加して盛⼤に開催されました。
総務省消防庁予防課課⻑補佐松野秀⽣⽒を講師に招き、「住宅防⽕対策の必要性について」と題した講演が⾏われました。これは「住宅⽤⽕災警報器PRハンドブック」を⽤いて、住宅⽤⽕災警報器の普及啓発に必要な知識を習得せしめ、クラブ員に周知することを目的としたものです。
<本協議会での住宅⽤⽕災警報器の設置普及啓発に向けた現況>
 役員会時,本県からの説明,資料提供を⾏い地域に根ざした活動をしている婦⼈防⽕クラブ員に今後の各市町村の設置開始に向けた普及啓発を図られるようお願いしました。
役員会時,本県からの説明,資料提供を⾏い地域に根ざした活動をしている婦⼈防⽕クラブ員に今後の各市町村の設置開始に向けた普及啓発を図られるようお願いしました。
⼜,平成17年度総会においては消防庁予防課の講師による「住宅防⽕対策の必要性」についての講演を⾏い,参加者190名に「⽕災警報器PRハンドブック」を配布したところです。
<各クラブ員の反応>
本協議会役員における当該機器の模擬設置等,クラブ員の反応については
- 台所に設置しているので,⿂を焼いた時の煙に鳴動してしまうなど,感知器の反応が多く,スイッチを切ってしまった。
- ⽕気の無い場所への設置例では,設置期間中鳴動が全くない為,設置⾃体を忘れていた。
- 警報器の価格に関する質問が多く,広報⽤の機器パンフレットには値段が記載されていないなどの指摘があった。
- 訪問販売に対する注意を促す必要がある。
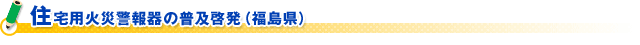
福島県⼥性防⽕クラブ連絡協議会 福島県⼥性防⽕クラブ連絡協議会総会が平成17年8⽉2⽇(⽕)14時40分より、福島県ハイテクプラザにおいて⾏われ、福島県⼥性防⽕クラブ連絡協議会幹部及びクラブ員100名が参加して盛⼤に開催されました。
総務省消防庁防⽕安全室予防・調査係⻑⾼橋典之⽒を講師に招き、「住宅⽤⽕災警報器PRハンドブック」を⽤いて、住宅⽤⽕災警報器の普及啓発に必要な知識を習得せしめ、クラブ員に周知することを目的に講演が⾏われました。参加の会⻑⽅からは、以下の感想をいただきました。
福島県⼥性防⽕クラブ連絡協議会
会⻑ 遠藤 瞳
 おいそがしい中、⼜、遠路おいでいただきありがとうございました。
おいそがしい中、⼜、遠路おいでいただきありがとうございました。
⽕災警報器の効果について、あれだけのデータを拝⾒し、私たち⾼齢者を持つ家庭には絶対に必要だと思いました。
⼀⼈でも多くの⼈に分かっていただけるよう、いろいろな団体を通じ、⼥性防⽕クラブが⼀丸となってPRを重ねたいと思っております。
年々⾼齢者が増加する中で、⽕災警報器の設置促進は私たち⼥性防⽕クラブの役割と認識し、新築の家だけではなく、⼀⼈暮らし⼜⾼齢者を持つ家庭等に対しても、市町村等の⾏政機関と連携しながら、何かの⽅法で取り付けられればと思っております。
最後に、聴覚に障害のある⽅の為に、点滅式のものができればありがたいと思います。 ⽕災による犠牲者が、⼀⼈でも少なくなるよう頑張ります。
福島県⼥性防⽕クラブ連絡協議会
副会⻑ 渡部 光⼦
 今回、消防庁の⾼橋さんから「住宅⽤⽕災警報器の普及について」講演をいただきありがとうございました。消防法が改正されて⼀般家庭でも⽕災警報器を取り付けなくてはならないことは理解していたのですが、具体的にどのような理由でそのよ
うになったのか、どこに取り付けなくてはならないのか、いまひとつ理解できないでおりました。今回の講演でわかりやすく説明していただき、よく理解できました。
今回、消防庁の⾼橋さんから「住宅⽤⽕災警報器の普及について」講演をいただきありがとうございました。消防法が改正されて⼀般家庭でも⽕災警報器を取り付けなくてはならないことは理解していたのですが、具体的にどのような理由でそのよ
うになったのか、どこに取り付けなくてはならないのか、いまひとつ理解できないでおりました。今回の講演でわかりやすく説明していただき、よく理解できました。
今後、私たち⼥性防⽕クラブ員は、消防署・市町村役場等の関係機関といっしょになって、⼀般家庭に対する住宅⽤⽕災警報器の普及に少しでも貢献できるようがんばりたいと思います。
私も取り付け⽅に少々不安がありましたが、割と簡単に取り付けることができました。⽕災警報器を取り付けただけでも、安⼼して過ごすことができます。
私たち⼥性防⽕クラブ員としましては、絶対にわが家から⽕災を出さないよう⼼掛け、⽇々気をつけることが活動の⼀環と思います。また、地域でも、⼀⼈暮らしの家々に声を掛けたり、運動会報にも「⽕の⽤⼼」の枠を設けたりしております。
講演「⽕災警報器の普及について」を受講して
福島県⼥性防⽕クラブ連絡協議会
副会⻑ 園部 キヨ⼦
⼦供の頃、⺟親から⽕災の恐ろしさについては強く⾔われてきました。「泥棒は持てるだけ持って逃げるだけだが、⽕事は全部燃えてしまうのだから。」と。(今では⼤分状況が変わりましたが―)住宅⽕災では、必ずといってよい程死者が出ており、しかも⾼齢者が多いことは、新聞・テレビ等でそれとなく知っておりましたが、確実なデータを提⽰して懇切丁寧に説明してくださったので、⼤変良く理解できました。
⽕災原因のトップを占めているのが放⽕とは、⼈間としてのモラルの低さで、残念でなりません。
すべての⼈が安⼼・安全な⽣活ができるよう、お互いに考えていかなければなりません。住宅⽕災は建物⽕災全体の半数以上を占めており、死者数も約9割が住宅⽕災によるとのこと、更に⾼齢者の割合が6割に近いことや、睡眠時間帯の死者発⽣率が他の時間帯の1.5倍にも及んでいることなどから、⽕災警報器の設置が必要視されるのは当然のことです。
私も恥ずかしながら、警報器に助けられました。
茶の間にテレビがつけてあったので、ちょっと台所を離れて、かわいいペットが迷⼦になった時の番組に夢中になってしまい、鍋のかけてあったのを忘れてしまいました。
突然、「ブー、ブー」あら何だろうと思っているうちに、「⽕事です。⽕事です。」の⾳声にびっくり、あわてて台所に⾏き、ガスを⽌めました。お陰で真っ⿊にまではなりませんでした。
煙を感知して⾳声メッセージで知らせてくれたのです。⼤事に⾄らなかったのは警報器のお陰です。
私は、この講習会で学習したことを機会あるたびに、たくさんの⽅へ普及啓発活動をしていきたいと思っております。市の連絡協議会、そして地区のリーダー研修会の時に伝達して、⼤切な命・財産を⽕災から守っていきたいと思っております。
暑い中、ご講演をくださった⾼橋様に厚く御礼申し上げます。
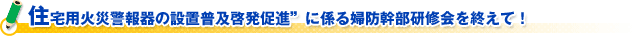
さる6⽉16⽇(⽊)愛知県⾃治センター会議室において、⽇本防⽕協会梅次部⻑様始め関係職員の皆様のご協⼒により「住宅⽤⽕災警報器の設置普及啓発促進に係る研修会」を催したところ総務省消防庁 ⽊原防⽕安全室⻑様を講師として招聘し、県内婦⼈防⽕クラブ幹部役員55名の出席を得て開催することができました。 この研修会開催にあたり、全国の新住宅防⽕対策委員として就任していただいております当協議会の永坂会⻑は「⼥性だからできる安⼼なまちづくりを︕」…防⽕防災には地域のコミュニケーションの中で“声かけ”が必要です︕と信念に持って積極的に取り組んでいただいております。 ⽊原室⻑様とは新住宅防⽕対策の推進に関する調査研究会で委員としての⾯識もあり、⽕災警報器の必要性、また、効果・課題について詳細に説明いただき婦⼈防⽕クラブ員に求められる家庭を守る⼀員として我が家から⽕を出さないことを初期の目的としておりますが今⽇、複雑多様化している個⼈住宅に必要な「⽕災警報器設置」のPRがクラブ員の⽅々の協⼒なしではありえないことを痛感いたしました。 今回の研修会では県婦防幹部の⽅々が熱⼼に聴講されましたが、幹部クラブ員のみならずクラブ員の末端までこの内容を浸透していくために各市町村単位で⾏われるクラブ員会議で説明会を⾏い、併せて設置に関しての問題点等を解決することにより普及啓発を図ることができると思慮します。