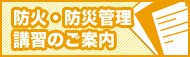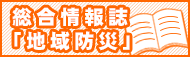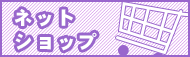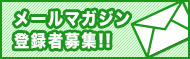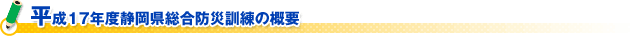
1 訓練の想定と目的
 東海地震の切迫性が指摘されている中、東海地震を想定し、
東海地震観測情報の発表から地震発⽣直後の災害応急対策まで
の地震防災訓練を実施して、県及び市町村の防災計画等の実効
性を検証するとともに、国、県、⽅⾯本部、市町村及び防災関
係機関の連携強化、地域の防災体制の確⽴及び県⺠の防災意識
の⾼揚を図る。
東海地震の切迫性が指摘されている中、東海地震を想定し、
東海地震観測情報の発表から地震発⽣直後の災害応急対策まで
の地震防災訓練を実施して、県及び市町村の防災計画等の実効
性を検証するとともに、国、県、⽅⾯本部、市町村及び防災関
係機関の連携強化、地域の防災体制の確⽴及び県⺠の防災意識
の⾼揚を図る。
会場型訓練(23回目)は、県と焼津市の共催により、焼津
市内全域を会場に設定し、⾃主防災組織等の訓練及び⾃衛隊や
海上保安部等を中⼼とした広域応援受援訓練に重点をおいて実
施する。
2 実施⽇
平成17年9⽉1⽇(⽊)「防災の⽇」
3 訓練の概要
| 区分 | 本部運営訓練 | 会場型訓練 |
| 訓練 時間 |
午前6時50分から11時05分 (⼀部の訓練は8⽉31⽇も実施) | 午前8時30分から14時00分 |
| 場所 | 県庁、⽅⾯本部、市町村役場等 | 焼津市内各訓練会場 |
| 参加 機関 | 国、県、市町村、防災関係機関 | 国、県、市町村、防災関係機関、 ⾃主防災組織、事業所、学校、病院等 |
| 訓練 内容 |
国の本部運営訓練に連携し、観測情報発表
から地震発⽣初期段階までを実施する。 1東海地震観測情報等の受・伝達 2地震災害警戒本部・災害対策本部の 設置・運営 3県本部、⽅⾯本部及び市町村の各段階における応急対策の⽴案・調整 4国、警察、消防、海上保安部及び⾃衛隊等との広域応援に関する調整 |
「平成17年度静岡県・焼津市総合防災訓
練」として、警戒宣⾔発令時から地震発⽣
後72時間経過頃までの避難誘導、救出・
救助及び復旧活動等について訓練する。 1⾃主防災組織による訓練 2現地調整会議運営 3中⾼層建築物や⼭崖崩れ現場等からの救出・救助 4応援部隊(医療班、救助部隊等)の 受⼊れ 5緊急輸送ルート等確保(啓開、復 旧、放置⾞両撤去等) 6緊急物資搬送、広域物資拠点等設 置・運営訓練 7医療救護、重症患者広域搬送 8ライフライン復旧 9⽔門・陸閘閉鎖 10ボランティアの受⼊れ調整 11農業⽤⽔を活⽤した訓練 |
4 訓練の特徴
(1)本部運営訓練
ア県本部・⽅⾯本部における防災関係機関調整会議の開催
イ静岡県総合防災情報⽀援システム(アシストII)による情報の受・伝達の実施
ウ防災ヘリコプターテレビ及び市庁舎等⾼所カメラによる初期情報の収集
(2)会場型訓練
新潟県中越地震及びスマトラ島沖⼤地震の実例を踏まえ、焼津市の地域特性に応じた多会場分散型訓練の実施
ア海岸部…津波避難ビルへの避難・誘導及び救出・救助、船舶の沖出し、⽔門・陸閘閉鎖訓練など
イ⼭間部…孤⽴地域住⺠の救出・救助訓練
ウ市街地…倒壊家屋・多重衝突⾞両等からの救出・救助、医療救護訓練など




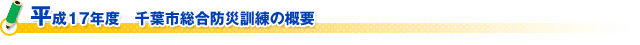
 今年度の千葉市会場の位置づけ
今年度の千葉市会場の位置づけ
第26回となる本年度は、9⽉1⽇の「防災の⽇」に、千葉市が⼋都県市の中央会場となり、援助
物資の輸送訓練やはしご⾞などによる⾼層建物からの救出訓練など、広範囲な実践訓練を⾏いまし
た。
訓練概要
| ⽇時 | 平成17年9⽉1⽇(⽊) 11︓30 〜 13︓30 |
| 会場 | 千葉市蘇我スポーツ公園予定地 |
| 規模 | 参加機関(団体)118機関、参加⼈員7,000名 |
| 想定地震 | 南関東地域における地震、東京湾北部を震源とする。 |
| マグニチュード7.3 震度6強 | |
| 訓練項目 |
1 災害対策本部設置 2 初期対応活動 3 情報収集及び広報 4 避難勧告 5 避難・避難誘導 6 避難所開設 7 応急救護所開設 8 防災ボランティア活動 9 応急給⾷・応急給⽔ 10 医療救護 11 帰宅困難者⽀援情報提供 12 道路啓開 13 ⽔防活動 14 救急法指導 15 ゴミ収集 16 仮設救護所 17 トイレ設置 18 ライフライン施設応急復旧 19 防疫活動 20 ⾼層建物救出救助 21 倒壊建物からの救出援護 22 救援物資輸送 23 地震災害消防活動訓練 24 広域応援物資輸送 |
| 訓練の特徴 |
1 ⽕災防ぎょ訓練 2 町内⾃治会、⾃主防災組織及び防災関係機関が⼀体となった訓練 3 倒壊建物からの救出・救助訓練 4 通信衛星やインターネットを活⽤した訓練 5 防災ボランティア対応訓練 6 広域応援活動訓練 7 模擬避難所体験訓練 8 海上における津波対策訓練 9 国及び関係省庁との連携 |