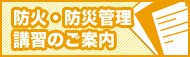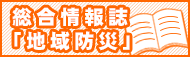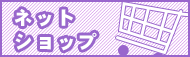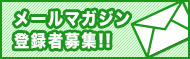―(⽉刊「近代消防」論説委員)防災アドバイザー森⽥ 武⽒の調査報告から―
去る4⽉25⽇午前9時18分頃JR⻄⽇本尼崎駅北東約1キロ地点で起きた脱線事故は、死者107⼈、負傷者およそ550⼈の⼤惨事となり、⼤きな衝撃を与えました。
事故処理に当たった消防活動等については、さまざまなメディアを通じ報道・報告されておりますが、事故発⽣とほぼ同時に近隣の住⺠や事業所の従業員により多数の負傷者応急救護措置などが始められており、その状況を「近代消防」誌7⽉号に報告された森⽥⽒の調査の中から近代消防社のご好意により転載させていただきました。
住⺠や近隣事業所の従業員などの救助・救急活動
この事故現場の管轄である尼崎市消防局は、午前9時22分に事故覚知し、緊急出動して同9時25分に先着消防隊が現場到着した。到着と同時に活動を開始したが、その時すでに近隣の住⺠や事業所の従業員により多数の負傷者の応急救護処置などが始められていたという。
現場で応急救護活動をされたという住⺠や事業所の従業員などに、その時の状況をうかがったが、住⺠や事業所の従業員などの活動概要は次のとおりである。
事故現場の近隣の住⺠や事業所の従業員などは、事故発⽣時の⼤きな⾳とともに事故を知り、現場へ駆けつけ救助や救護活動を実施した。
事故現場へは、消⽕器をはじめ救助に役⽴つバール・ジャッキ・クリッパーなどの器具、救急薬品、タオル、氷、あるいは⽔などを持って駆けつけ、列⾞から出て線路上や路上に倒れていた⼤勢の乗客の救護にあたるとともに線路⻄側では線路脇のフェンスを切断して線路内への通路を設定した。
そこから、列⾞内に⼊り倒れている⼈のうち⾃分たちで救助可能な⼈を列⾞外へ救出するとともに、列⾞の座席をはずして列⾞外へ持ち出し担架代わりに使⽤して救護にあたった。
なお、座席などに挟まれているなどして、容易に救助できない⼈については消防救助隊に任せた。
事故現場では、多数の死傷者があり病院搬送されるまでに相当時間があったため、その間負傷者の傷⼝をタオルで拭いたり氷で傷⼝を冷やしたりして救護にあたるとともに負傷者を激励したという。
⼀⽅、トラックやライトバンなどの⾞を現場へ搬出し、電⾞の座席を剥がし担架代わりにして乗客をトラックに収容して病院搬送した⼈は、「トラックは物を運ぶものであり、トラックで負傷者を運ぶことに躊躇したが、あまりの負傷者の多さに、到着している救急隊員に搬送の可否を確認した後、トラックへ多数の負傷者を収容し、救急隊員に同乗してもらって警察の⽩バイの先導で病院へ搬送した」という。
事業所の⼥性従業員の中には、負傷者の声を聞き取るなどして、負傷者の病状を救急隊員に伝えたりした⼈もいたという。
また、たまたま現場に居合わせた⼈々の中には、救助・救護等の活動に加わり応急処置をしたり負傷者を介護し励まし、中には負傷者を乗⽤⾞で病院へ搬送した⼈もいたということである。
これらの活動は、救助や応急処置、あるいは搬送だけではなく激励にまで及んでいて、多数の負傷者の救護に非常に役⽴ったものと考えられる。
なお、負傷者の救助・搬送などの活動を実施したという⼈に聞くと、「この事故現場では、市⺠と事業所の従業員などが、消防隊や警察隊と⼀体になって必死に活動していた」ということであるが、これは、この地域は阪神・淡路⼤震災で被災した家庭や事業所が多かったことから、震災を契機に住⺠や事業所が救助・救急・救護の重要性を認識していて、消防署などが⾏う応急処置や救命講習を受けていたことや家庭内や事業所内に応急薬品を置いているところも多かったことから備えが出来ていた結果であると考えられる。
※ 尼崎市消防局では、これまでに市⺠や事業所の従業員を対象に、3万⼈を超える⼈々に応急処置や救命講習を実施してきたということであるが、同市の⼈⼝約45万⼈からすると、約15⼈に1⼈の割合で講習を受けていることになり、その成果がこのような形で表れたものと考えられる。
HOME > 防火ネットニュース6月号 > JR福知山線脱線事故から学ぶ
2005年6月
JR福知山線脱線事故から学ぶ
|
|