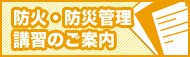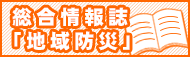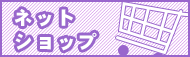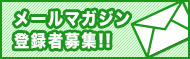「サバイバルクッキング」シリーズ連載
-災害時に役⽴つ知恵と技術-
昨年は、⾃然災害が各地で猛威を振るいました。被災地の皆様には改めてお⾒舞いを申し上げます。
私ども⽇本防⽕協会も北陸地⽅を中⼼に⼤きな被害をもたらした7⽉豪⾬災害では、福井県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会の要請で、近県婦防連の⽅々に被災地に赴いていただき、住⺠への炊き出し⽀援を⾏いました。
10⽉の新潟県中越地震では、⼩千⾕地域の婦⼈防⽕クラブ連絡協議会の要請により、同じく近県婦防連の皆様ともども余震の続く⼩千⾕市に炊き出し⽀援に参りました。
7⽉豪⾬では⼭村の美⼭町蔵作(くらづくり)地区へ。“夏の⽔害”という極度に“⾷と⽔”の安全性が要求される中、同時に⽔道などライフラインが停⽌した条件下で「⼭の⽔」の浄化から始まった炊き出し⽀援でした。
住⺠の皆様が持ち寄る野菜などの限られた⾷材で、連⽇30度を超える炎天下、各被災家屋から汚泥や岩⽯の除去に疲労困憊した住⺠への⼣⾷の提供、それは、通常の防災訓練等に⾒られる、おにぎりや豚汁のような限られた炊き出し訓練では応⽤の効かない状況でした。
さすがに⽀援にかけつけた婦防の⽅々は、味付けにも⼯夫を凝らしたメニューに腐⼼し、住⺠の皆様に本当に喜んでいただきました。
中越地震災害、10年前の阪神淡路⼤震災とも規模こそ違え発災時の緊急輸送路の遮断による物資輸送の困難や“冬季の⻑期避難”という条件は類似しましたが、「⾷」をめぐる⼤きな環境の違い、それは中越地震災害では、避難住⺠に「多数の⾼齢者」を擁したことでしょう。ショック死やエコノミー症候群など災害時における⾼齢者への対応は、今⽇的課題として議論を投げかけておりますが、「⾷」についても救援物資や避難所運営のあり⽅について様々な観点からの検証が待たれるところです。
このような実体験や現地で⾒聞させていただいた「⾷」をキーワードとした災害時対応を改めて考えて⾒ますと、例えば⼤震災が東京や横浜のような⼤都市部を襲ったとき、ライフラインが全く停⽌した中で、輸送路が各所で寸断された場合に⾷の確保はどうすれば良いのか、町内に防災倉庫を有していても⻑期の備蓄には限界もあります。また、昨今の⼦供たちばかりか若年層もナイフなどの道具に触れたこともないとか、⾼齢者の中には、リンゴの⽪をむくにも⾃⼒ではナイフを握れない⽅もおられますし、アウトドアーでの⾃然の⽕を⽤いた調理経験もない、いざという時⾷べられる植物を知る、汚れた⽔を浄化する⽅法など極限状況での⽣きる知恵に都市住⺠は乏しいと⾔わざるを得ません。
そして、それが夏の炎天下なら、⾼齢者を多く抱えた場合は、などなど多くの場⾯が想定されますが、もちろん、⼤都市部に限らず⽣き残る、それもなるべく豊かに「⾷」を基軸に⽣き残る知恵と技術を会得しておくことの⼤切さを考えさせられました。
そこでメールマガジン読者に次号7⽉号から毎⽉のシリーズで「サバイバルクッキング」をお届けしようと企画いたしました。
先ず、基本編では、“2週間⽣き延びるために”必要なリスト作りから、⽔の確保の⽅策、“⽕の作り⽅”、⾝の回りのものを道具に変えるスーパーメイク術などを、継いで応⽤編では、“どんな状況でも温かい⾷べ物を作り、⾷べる”をテーマに、⾝近な⽯や⽵を道具に使う、鍋がなくてもご飯は炊けるなどの裏ワザを公開していただきます。
読者の皆様、ご家族で試していただくのはもちろんですが、とくに婦⼈防⽕クラブの皆様には、炊き出し訓練の新しい実践的な訓練メニューのヒントとして活⽤していただきたいと思います。
執筆者は、「かざま りんぺい」さんです︕
1952年東京⽣まれ、⼤学では教育学を学んでおられました。ボーイスカウトのリーダーや国内外のアウトドア経験を⽣かし、今では、こどもや親⼦遊びを⽀援する「アソベンチャークラブ⽇本」代表です。
1972年発刊の「冒険⼿帳」(主婦と⽣活社)をはじめ「できる男は料理も上⼿い」(旬報社)「完全図解冒険図鑑 ⼤冒険術」(誠⽂堂新光社)などアウトドア、料理・⽣活関連の執筆活動も幅広く⼿がけておられます。
少し遊びの感覚も取り⼊れていただいたシリーズ新企画、読者の皆様と楽しみながら学ぶコーナーです。ご期待ください︕
■メルマガ配信のご希望の⽅はこちらからご登録ください。
⽇本防⽕協会メルマガ担当
HOME > 防火ネットニュース6月号 > マガジン購読者の皆様へ 次号7月号からの新企画ご紹介
2005年6月
マガジン購読者の皆様へ 次号7月号からの新企画ご紹介
|
|
目次
- 1.「がんばれ消防」の開催
- 2.都道府県予防事務担当者会議
- 3.平成17年春の叙勲
- 4.婦人防火クラブ新会長紹介
- 5.防火管理再講習講師担当者会議
- 6.新住宅防火対策推進会議
- 7.地方からの便り
- 8.あなたも危険物取扱者・消防設備士
- 9.日本防火協会からのお知らせ
- 地域防災の総結集
- JR福知山線脱線事故から学ぶ
- マガジン購読者の皆様へ 次号7月号からの新企画ご紹介