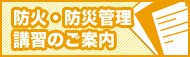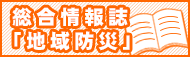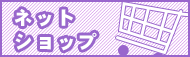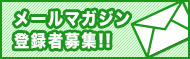平成17年9⽉27⽇、内閣府中央防災会議より「⾸都直下地震対策⼤綱」が公表されました。そのな かで、⾃主防災組織及び婦⼈防⽕クラブの活動についての記載がありますので掲載いたします。
『⾸都直下地震対策⼤綱』26ページ「第4節 広域防災体制の確⽴ 3.消⽕活動(1) 消防⼒の充実・強化」より抜粋。
地⽅公共団体は、初期消⽕を迅速かつ的確に実施するよう、平常時からの地域コミュニティの再構
築、⾃主防災組織の育成・充実、婦⼈防⽕クラブの活性化、防災教育の充実、訓練の実施等を⾏うと
ともに、常備消防及び消防団を充実、強化することによって、初期消防⼒の充実・強化を図る。
(中略)災害発⽣時に、⾃主防災組織及び婦⼈防⽕クラブは、消⽕活動、避難路等の危険物除去
等、消防機関が実施する応急活動に協⼒する。
また、内閣府政策統括官(防災担当)室に「先⽇、政府の中央防災会議で⾸都圏での発⽣が 懸念されている⼤地震対策の基本指針が決定されたと報道でしりましたが、どういう内容の ものなのですか教えて下さい。」とお尋ねしたところ、次のとおりご回答を頂きました。
<お答えします>
(回答者名)内閣府政策統括官(防災担当)付参事官付 橘 清治様
1 お尋ねの基本指針は、公式には「⾸都直下地震対策⼤綱」といいます。⼤綱では、予防段階から
発災後の全ての段階において地震防災対策を⾏う主体としての政府や地⽅公共団体、⺠間事業者等が
どのような対応をとればいいのかといった基本指針を定めています。
2 ⾸都地域においては、歴史的に200〜300年間隔で関東⼤震災(1923年)のようなマグニチュー
ド8クラスの海溝型の地震が発⽣すると考えられていますが、その間にプレート境界に蓄積された歪
みの⼀部がいくつかのマグニチュード7クラスの直下の地震として放出される可能性が⾼く、マグニ
チュード7クラスの⾸都直下地震の発⽣の切迫性が指摘されています。
3 中央防災会議の⾸都直下地震対策専門調査会の想定では、マグニチュード7.3の東京湾北部地震の
ケースで、死者数は、建物倒壊及び⽕災延焼による死者が膨⼤で、冬18時・風速15m/sの場合で約
11,000⼈、風速3m/sの場合で約7,300⼈と予測しています。さらに、これに伴う膨⼤な経済被害の
発⽣が予測され、直接被害、間接被害を併せて冬18時・風速15m/sの場合で約112兆円、風速3m/s
の場合で約94兆円の被害額を予測しています。また、避難者も最⼤で約700万⼈、帰宅困難者も約
650万⼈と膨⼤な被害を予測しています。
4 被害の特徴は、「⾸都中枢機能障害による影響」と「膨⼤な⼈的・物的被害の発⽣」の2点です
が、政治、⾏政、経済の中枢機能の障害は、応急対策の中枢的役割としての機能の障害でもあり、
「膨⼤な⼈的・物的被害の発⽣」を拡⼤させます。
⾸都直下地震対策では、これらの特徴を⼗分に踏まえる必要があり、⼤綱では、「⾸都中枢機能の
継続性確保」と「膨⼤な被害への対応」を対策の2本柱とし、これらの対策を効果的に進めるために
「国⺠運動の展開」により社会全体で減災への取り組みを進めることとしています。
5 「⾸都中枢機能の継続性確保」については、発災後3⽇程度の応急対策活動期においても⾸都中
枢機能の継続性を確保するための目標を設定し、その目標を達成するために、国会、中央省庁、中央
銀⾏等⾸都中枢機関のバックアップ機能の充実、事業継続計画(BCP︓Business Continuity
Plan)の策定・実⾏、⾸都中枢機関へのインフラ・ライフラインの多重化等の対策を⾏うべきとして
います。
6 「膨⼤な被害への対応」については、
- 耐震改修促進のための補助や税制等の制度整備や公共施設の耐震化等の建築物の耐震化対策
- 疎開・帰省の奨励、ホテル・空き家等の既存ストックの有効活⽤等の避難者対策
- 帰宅困難者のルール(「むやみに移動を開始しない」)の徹底、企業による従業員の収容・安否確 認システムの強化、さらにはボランティアによる周辺地域の救援活動への参加等の帰宅困難者対策
- 被災後可能な限り短時間で重要な機能を再開させるための対策を定めたBCPの策定及び実践等企 業の防災⼒向上 等多角的な観点から対策を⾏うべきとしています。
7 「国⺠運動の展開」については、膨⼤な規模に及ぶ被害を軽減させるためには、⾏政による「公
助」だけでは限界があり、社会のあらゆる構成員が相互に連携しながら総⼒を挙げて対処していく必
要があるとしており、すなわち「公助」だけでなく、「⾃助」「共助」による社会全体での減災への
取り組みが不可⽋であるとしています。
8 今後は、⼤綱を具体化するための指針等の策定を予定しています。