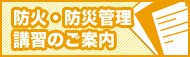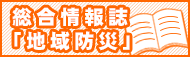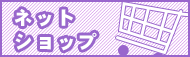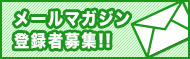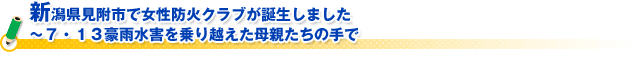

⾒附消防本部による実演■⼦育て中の働くママたちが⼥性防⽕クラブを設⽴︕
11⽉20⽇(⽇)、⾒附市太⽥町において太⽥町⼥性防⽕
クラブが、⾒附市消防本部・(財)⽇本防⽕協会による救急講習
会を受けました。
⾒附市は、2004年7⽉13⽇に豪⾬災害に⾒舞われてお
り、市の中⼼部を流れる刈⾕⽥川と稚児清⽔川で越⽔や破堤が
起こって濁流があふれ出し、テレビや新聞を通じて市街地が広
範にわたって⽔につかる被害を受けた様⼦が映し出されことか
らも、まだわたしたちの記憶に⼤変新しいところです。

⾃分達の命・くらしは⾃分達で守る。
真剣な⾯差しのクラブ員のみなさん そんな⾒附市の中でも、稚児清⽔川が刈⾕⽥川に流れ込むあ
たりに近い太⽥町でこのたび、新たに⼥性防⽕クラブが設⽴さ
れました。それがこの太⽥町⼥性防⽕クラブ、通称・「さくら
クラブ」です。
昨年の豪⾬では、メンバーのほとんどが、お⼦さんを学校や
保育園へ送り出しつつ、⾃分も中⼼市街地や近隣市へ出勤して
しまったすぐ後に、越⽔・破堤によって地区全体が⽔没してし
まいました。お⼦さん達の様⼦がどうなのか⼼配がたいへん
募ったのですが、道路が⽔につかってなかなか⾃宅に帰れず、
とても苦労したそうです。さらに、10⽉23⽇に発⽣した中
越地震にも遭い、災害の恐ろしさを⾝をもって経験しています。
そんな⼦育てにも仕事にも奮闘している若いママたちが中⼼となってのクラブ設⽴です。
 ■さっそく普通救命講習に挑戦
■さっそく普通救命講習に挑戦
講習会の開催場所は地区内の上北⾕地域開発センターで、あ
いにくの⾬模様にもかかわらず朝9︓00にクラブ員たちは集
合。この⽇は⼦ども達のスポーツイベントが会場のすぐ隣であ
り、⼦どもの送り時間に合わせて設定したのです。
最初に⾒附消防本部の⽯⿊予防課⻑があいさつし、今回のク
ラブ設⽴にあたっては、昨年の⽔害時に⽇本防⽕協会が、全国
の婦⼈防⽕クラブ員が中⼼となって集めた募⾦をもってきてく
れたことが⼤きなきっかけでもあったことがあらためて紹介されました。また今回の⼥性防⽕クラブ
設⽴を機に、さらに会員を広げ、他の地区にも⼥性防⽕クラブができればとの、期待のメッセージが
贈られました。次に(財)⽇本防⽕協会からもあいさつをしました。
そして早速、⾒附消防本部の指導により講習開始です。
最初は⽌⾎法です。三角⼱を⼿にとって、クラブ員は⼆⼈⼀組で講師の説明をうけながら直接圧迫⽌
⾎法を実践。また⽌⾎帯の巻き⽅も学びました。
次に⼼肺蘇⽣法です。救急⾞が現場に到着する全国の平均時間は6分、⼀⽅で⼈間の脳は4分間⾎
液が送られないと細胞が死に始めてしまい、死んだ脳細胞は⼆度ともとには戻らないということを
しっかり胸に刻んだのち、気道確保・⼈⼯呼吸・⼼臓マッサージと、3つの構成要素を学び、その後
訓練⽤の⼈体モデルを使⽤して実際に練習を⾏いました。
そして最後は、まだあまり⼀般に知識が普及していないAED(⾃動体外式除細動器)の使⽤⽅法
についても、最新の講習⽤キッドを⽤いて説明を受けました。


※⽇本防⽕協会の提供資材⼀覧
| ⼼肺蘇⽣法教育⼈体モデル(JAMYⅣ RECO) | 1式 |
| AED(⾃動体外式除細動器)トレーナー | ⼀式 |
| 気道確保指導モデル気道確保原理の可動パネル | 1式(5枚組み) |
| 三角⼱(105*105*150cm) | 115個 |
| 清浄綿 | 200枚 |

⼼肺蘇⽣法教育⼈体モデルと
AEDトレーナー

AEDトレーナー(拡⼤)
●新潟県⾒附市消防本部からのリポートです
『⼥性防⽕クラブ員救急講習会』を開催
(財)⽇本防⽕協会から交付を受けたAED(⾃動体外式除細動器)トレーナー等の救急講習資器
材を活⽤して、『⼥性防⽕クラブ員救急講習会』を実施しました。
1回目は11⽉20⽇(⽇)、上北⾕地域開発センターにおいて開催しました。参加者は24名と少⼈
数でしたが、今年6⽉に当市で初めて結成された太⽥町⼥性防⽕クラブ員を主体とし、クラブ員以外
に地域の⼥性の皆さんからも参加していただきました。講習会では、ほとんどの皆さんが学校等で開
催された救急講習を受講されていましたが、AEDの取り扱いは初めてのため関⼼が⾼く、真剣に⼼
肺蘇⽣法に取り組んでいました。
また、当⽇は、⽇本防⽕協会から塩⾕様と浅野様が来市され、講習を⾒学された後、クラブ員や町
内役員を対象に、昨年、当市を襲った7.13新潟豪⾬災害時のヒアリングと被災箇所の視察を⾏われ
ました。
ネーブルみつけでの講習の様⼦
2回目は12⽉3⽇(⼟)、ネーブルみつけを会場に45名の
参加で開催しました。この会場には親⼦で受講されるなど若い
⼥性の参加が多く、当⽇は、今年初の降雪が観測され寒さの厳
しい⽇でしたが、皆さんの熱⼼な⼼肺蘇⽣法の練習は、寒さを
吹き⾶ばす熱気で、活気ある講習となりました。
当市では、太⽥町の防⽕クラブ結成以来、次の結成が⾜踏み
状態となっていますが、今回の救急講習を受講された皆さんか
らは、⼥性防⽕クラブについての理解を得られたことから、今
後の⼥性防⽕クラブ新結成に向けて弾みがつくことを望んでい
ます。
■⽔害であのとき町は︖
113世帯・約400⼈の住⺠が暮らし、⼩学校・中学校にあわせて3〜40⼈ほどが通う太⽥地
区。
この⽇は、被災前後のなまなましい地域の様⼦を、現在太⽥町の地区⻑で、⽔害時は副地区⻑として
危険箇所の⾒回りや連絡・調整、救援活動に携わった⻫藤さんにもお聞きすることができました。

当⽇の切迫した状況を佐藤区⻑(左)と
⾒附消防本部の⽯⿊予防課⻑(中央)
にうかがう 昨年7⽉13⽇の当⽇は朝8︓00ごろ、その少し前から危
険を感じて川の⽔位など⾒回りにでていた地区⻑からの電話で
すぐに役員全員が参集しましたが、異常な豪⾬によって周辺の
⼭からも⽔が流れ込み、排⽔しきれなかったため、この時点で
すでに地区をひざ下ぐらいまで覆っていたということです。
しかも平⽇の昼間はもっとも町に⼈⼿がいない時間です。稚
児清⽔川の様⼦を橋の上から監視しながら、やはり危険だとわ
ずかな⼈⼿で⼟嚢をつみはじめたそばから、⽔がどんどんあふ
れだしました。そしてみるみるうちに、⽔は広がり、場所に
よっては⽔が胸の辺りまで来るほど⽔没してしまったそうです。
実はこの⽇の13︓00ごろ、増⽔した刈⾕⽥川は、隣接した上流の地区で越⽔してあふれ出し、
⽥んぼを流れていったその⽔が今度は地区のすぐ⻄を通って刈⾕⽥川に合流する稚児清⽔川に流れ込
みながら、東岸の堤防を破壊し、稚児清⽔川の⽔とともに太⽥町を襲っていたのです。
事前に予防策を講じていたとしても、災害の規模や地形などによって、予測を超えた災害はいつで
も起こりえます。そこで発揮されるのが、地域の「⼈」の⼒や信頼関係です。

稚児清⽔川の破堤箇所(14⽇・⽯川県消防本部ヘリ撮影)写真右上を蛇⾏する刈⾕⽥川から溢れた⽔
が、⽥んぼを流れて⽀流の稚児清⽔川に流れ
込み、⼤⽥町近くの東岸の堤防を破った様
⼦。左⼿の向こうに市街地があり、そこへ向
かって⼀気に⽔が流れていき、さらに多くの
住宅が浸⽔した。
(引⽤-⾒附市消防本部「災害記録写真」)
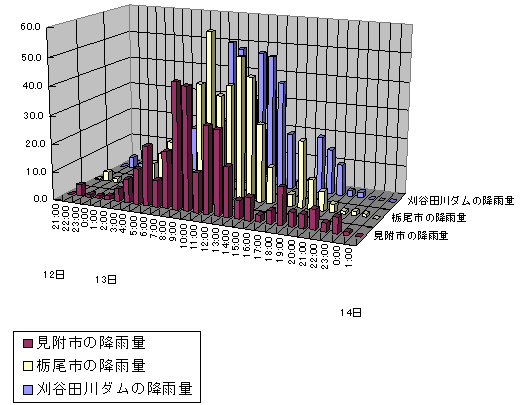
※⾒附市の降⾬量(⾒附市消防本部提供のデータから抜粋)
下表―降⾬量と刈⾕⽥川⽔位のデータ、上図―データをもとに降⾬量をグラフ化したもの。
ごく短時間に、上流の栃尾市・刈⾕⽥川ダムとともに⼤量の⾬が降ったことがよくわかります。これ
らの⾬⽔が栃尾市、そしてさらに下流の⾒附市・中之島町で氾濫しました。
 | 右は稚児清⽔川、左は川にかかる橋で、この 上から地区役員達は川の様⼦を監視していた |
 | ⽥崎医院付近18メートル道路(13⽇) |
■⼥性防⽕クラブ員はこれからも地域のつながりのなかで
佐藤さんによると出⽔してしばらく後、学校から連絡が⼊り、当⽇地区内にある⼩学校に給⾷が届
く前に⽔が出てしまったため、⼦ども達の給⾷が⽤意できないので炊き出しをしてもらえないか、と
の要請があったそうです。そこで佐藤さんは地区でなにかと地域活動を積極的に取り組んでいる⼥性
に声をかけて依頼をした結果、即座に炊き出しを⾏ってくれたそうです。
また、後⽚付けについては、⼿の⾜りない家については、ご近所同⼠で⼿伝いあって復旧に取り組
んだということです。
さらに⽔害時の様⼦を、クラブ員のみなさんにもうかがいました。当⽇は⻑岡市などへ仕事にでて
いたため、⽔浸しのまちに⾃宅には帰るに帰れない状況で、会社に泊まって翌⽇帰ってきた⼈、命が
けで⼭を越えて帰ってきた⼈など、家族の安否を気遣いながら⼤変な時間を過ごされたことがわかり
ます。
地区にいたというクラブ員は、お⼦さんは学校、お連れ合いは会社で、お⼀⼈の状態。そこへ学校
から、迎えに来るように電話がかかってきて、決死の覚悟で⽔の中を⻑靴で歩いていったそうです。
また娘さんが中学⽣という⽅によると、⼀旦帰るように⾔われた⽣徒達が、学校を出たところで
あっという間に腰まで⽔につかってしまい、結局学校に引き返したとのことです。学校のすぐ横の堤
防が越⽔して⼀気に⽔が流れ込んだためでした。
そんな状況下で、地区外にいたクラブ員たちは、⼦ども達の安否が最⼤の不安だったので、同居し
ている⽗⺟や、親族と連絡を取り合いながら、お迎えに⾏っていただいたり預かってもらったりして
乗り切ったということでした。
そんな経験をしたみなさんからは、やはり災害時には情報が⼤変重要であるという意⾒が多く聞か
れました。また同居している⽗⺟や親族などに本当に助けられたとの意⾒もたくさん出、⼈の⼒、普
段からの助け合いの関係などがとても⼤切であるということを改めてかみ締めあいました。
このように太⽥地区は、コミュニティや家族の持っている⼒が潜在的に⾼いといえるでしょう。消
防機関と住⺠のみなさんとの間に信頼関係が強くあることもわかりました。
しかし、どうしても昼間は若⼿がいないといった現状などを考えると、今後も地域全体での災害対
応⼒を⾼めていくことが⽋かせません。
今回、若い⼥性たちによってこのように⼥性防⽕クラブ設⽴に⾄りました。地域には⼀陣のさわや
かな風が吹いてきたのではないでしょうか。これを⼒に、さらに地域全体の防災⼒を、楽しく、お⼦
さんたちも巻き込む形で、⾼め、広げていっていただければと思います。